長野県日中友好協会のホームページへようこそ
![]() 2020.1~12
2020.1~12
トップページはこちら
長野県日中友好協会のホームページへようこそ
| 第24期日中連続市民講座②、中国語と日本語-日中文化比較(12/19) 主語と動詞をはっきりさせる中国語と主語と動詞があいまいな日本語の特徴に触れた後、日常のあいさつと配偶者の呼称、漢字から見た古代女性の社会的地位、老子・孔子・荘子・孟子など古代思想家が中国語と中国文化に与えた影響、詩詞が中国語と中国文化を豊かにしたこと、中国の4大名作と4大奇書(「三国志演義」「西遊記」「水滸伝」「金瓶梅」が4大奇書と言われていたが、「金瓶梅」の代わりに「紅楼夢」を加えたものが4大名作と呼ばれるようになった)へと話が進みました。 更に、『漢委奴国王』(紀元1世紀、後漢の光武帝が日本の奴国王に与えたと「後漢書」に記されている「漢の倭奴国王」)金印と漢字の日本伝来、明代にイタリア人宣教師マテオ・リッチが漢字をローマ字表記することをはじめ、これが、現代中国で広く使われている「漢語ピンイン法案」へとつながっていったこと等興味深い話が続きました。また、明治期には革命、科学、共和、哲学、自由など多くの社会科学用語などが日本から中国に逆輸入されたこと、峠や辻、切符、切手などは和製漢字単語であることも紹介されました。玉や紅が好きな中国人、気の毒な犬、四君子と尊ばれる「梅・蘭・竹・菊」など話は中国文化に幅広く及び講義時間もあっという間に過ぎました。 |
||
| 東京五輪・パラリンピックホストタウン・オンライン講演会 上原大祐さん「パラスポーツの魅力を語る」(12/16) 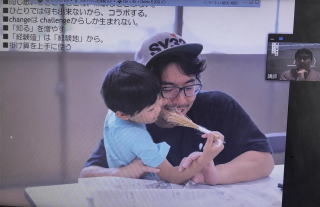 東京オリ・パラホストタウン長野県実行委員会(高波謙二会長)は12月16日長野市生涯学習センターにおいて上原大祐さんを講師に迎えオンライン講演会を開催しました。上原さんは軽井沢町出身で、パラリンピック・アイスホッケーの日本代表選手として、2006年トリノ、2010年バンクーバー、2018年平昌冬季パラリンピックの3大会に出場し、2010年バンクーバー大会では準決勝で決勝ゴールを決め、銀メダル獲得に貢献しました。引退後は、「誰もが夢を持ち挑戦する世の中を作っていきたい」との思いから、2014年にNPO法人D-SHiPS32、2017年に一般社団法人障害者攻略課を設立、障害のある子供たちとその家族のサポートを行いながら、企業や自治体と連携し、全国でパラスポーツの普及を通じた地域作りに取り組んでいます。 東京オリ・パラホストタウン長野県実行委員会(高波謙二会長)は12月16日長野市生涯学習センターにおいて上原大祐さんを講師に迎えオンライン講演会を開催しました。上原さんは軽井沢町出身で、パラリンピック・アイスホッケーの日本代表選手として、2006年トリノ、2010年バンクーバー、2018年平昌冬季パラリンピックの3大会に出場し、2010年バンクーバー大会では準決勝で決勝ゴールを決め、銀メダル獲得に貢献しました。引退後は、「誰もが夢を持ち挑戦する世の中を作っていきたい」との思いから、2014年にNPO法人D-SHiPS32、2017年に一般社団法人障害者攻略課を設立、障害のある子供たちとその家族のサポートを行いながら、企業や自治体と連携し、全国でパラスポーツの普及を通じた地域作りに取り組んでいます。宮原茂県国際担当部長(実行委員会副会長)が講演に先立って、長野県と6市町村が中国を相手国とする東京五輪ホストタウンとなって各種事業に取り組んでいることや東京大会の後、2022年には北京冬季五輪・パラリンピック大会も控えていて、長野県は冬季スポーツ団体と協力しながら支援・交流を深めていることを紹介した後、「コロナ禍で活動が制約される中、オンライン講演会を開催することとなった。パラリンピアンだった上原さんの活躍の体験をお聞きしパラスポーツの魅力に理解を深めていきたい」とあいさつしました。 上原さんは子供の頃の体験に触れ、決してあきらめない精神、こんな工夫をすれば楽しんでできると思って次々といろいろなことに取り組んできた事例を紹介しました。 原点は、生まれつき両足が不自由だったが、自転車に乗りたいと言うと母は無理だと言わず八方手を尽くし手こぎの自転車を手に入れてくれ、自転車に乗れるようになったこと。母は「ごめんね」から「誇れる我が子」へと、認識を改めてさせてくれた。できないと思われていることは実際はやればできることが多い。どうしたらできるかを考える。「1クラス1畑」で車いすでも楽しめる畑を作った。車いすキャンプや陸のカーリング=ボッチャの開催、車いす用着物の開発、長野県民パラスポーツ大会を始めたが各県に広げて全国大会を目標にしていきたい。他人事を自分事にし友達ごとにして共生社会を作っていく。共生社会を作るにはチョコチョコ行い、ちょっとしたことでも良いから発信し続けることが大切。障がい者体験だと言って大変だねを届ける体験は逆効果で、こんな工夫をすれば楽しんでできるという発想が必要と思うなどなど、アイデアとそれを実践していく上原さんのエネルギーは聞く人に感動を与えてくれました。 <ホストタウンの取り組み紹介>東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、地方自治体がホストタウンとなり、住民と一体となって相手国の選手や関係者、オリンピアン・パラリンピアンとの交流を行い、地域の活性化などをはかる取り組みです。長野県と4市(長野市・上田市・須坂市・飯山市)2町(下諏訪町・山ノ内町)が中国を相手国とするホストタウンとして国に登録しています。長野県としては2022年の北京冬季オリンピック・パラリンピックも見据えて、スキーやスケート、アイスホッケー、カーリングなど冬季スポーツ交流を行ってきました。上原さんの精神を受け継いだ後輩選手の皆さんがパラアイスホッケーで好成績を収めることを期待したいと思います。 |
||
| 河北省張家口市に五輪ジャンプ台が完成(12/3)
ジャンプ台は国家スキージャンプセンターの中に作られ、外観がかつて中国の宮廷で吉祥の象徴として用いられた器物「如意」に似ていることから「雪如意」と名付けられました。標高差が160メートル以上もあり、競技エリアの中で最も施工量が多く、建設のハードルが高い競技場の一つだそうです。2018年5月1日から正式に着工し、昨秋9月にスキージャンプの国際大会開催基準を満たす段階まで工事が終わりました。今はジャンプ台の内装工事や周辺の整備作業が着々と進められているところです。写真は先方から送られてきたものなので、皆様のご参考になりましたら幸いです。 ちなみに、北京から張家口市までの新幹線も19年12月に開通しましたので、22年には北京から新幹線に乗って、張家口の最新の競技施設までオリンピック選手の応援に行ってみたいですね!(県国際交流員・李妮) |
||
| 第24期日中関係を考える連続市民講座スタート(11/21)
-戦後75年、日中国交正常化から48年を経過し、日中関係の改善加速が期待された中でしたが、新型コロナの世界的感染拡大によって、人的交流がストップし、経済、文化学術、スポーツなどの分野の交流においても困難が続いています。早期の平穏化を願いつつ、コロナ禍後を見据えて、両国国民の相互信頼関係を醸成していくことが望まれます。 歴史的に深いかかわりを持ち、日本の最大の貿易相手国である中国はGDP第2位の経済大国となり巨大な変化を遂げています。14億人が住む隣国中国に対する理解を深めることは日本にとって一層重要となっています。中国を多面的に理解するため県内で活躍している大学・短大などの先生を講師に迎え第24期講座を計画しました。お誘いあってご参加ください。 詳細はこちら――>第24期日中関係を考える連続市民講座「中国の歴史・文化と日本」 第2回は12月19日(土)王秋菊・清泉女学院短大中国語講師が中国語と日本語・文化比較について話します。 第3回は1月23日(土)小池明・上田女子短大学長が米大統領選と米中対立について話します。 第4回は2月20日(土)谷口眞由実・県立大学教授が漢詩のユーモアについて話します。 第5回は3月13日(土)豊岡康史・信州大学准教授が清朝の対外政策決定方と現代中国について話します。 第6回は4月24日(土)兼村智也・松本大学教授がコロナ禍で変わる日中ビジネスについて話します。 |
||
コロナに負けず第18回日中友好マレットゴルフ大会楽しむ(10/31) 長野市日中友好協会主催の第18回日中友好マレットゴルフ大会が10月31日、長野市犀川第2運動場マレットゴルフ場で開かれました。雨のため2度延期されていましたが3度目の正直、この日は快晴で風もなく穏やかな日和で、絶好のプレー日和になりました。 長野市日中友好協会主催の第18回日中友好マレットゴルフ大会が10月31日、長野市犀川第2運動場マレットゴルフ場で開かれました。雨のため2度延期されていましたが3度目の正直、この日は快晴で風もなく穏やかな日和で、絶好のプレー日和になりました。
コロナ禍の中での開催でしたが、中国帰国者14名、国際交流員1名、協会会員10名、総勢25名で18ホールのストロークプレーを楽しみました。 OBを多発した人もいましたが、エチケットリーダーと協力して和気あいあいとプレーができました。結果は男子が戸井田靜男さん、女子は帰国者の中村国子さんが優勝しました。たくさんの賞と景品が用意されていました。参加賞は石家庄市から贈られたサージカルマスクで、参加者に好評でした。 |
||
| 中国語スピーチコンテスト長野県大会、コロナにめげず若者が活躍(10/10)
朗読部門には高校生・大学生の部6人と一般の部7人が参加、それぞれの全国統一課題文を発表し発音や表現力を競いました。 スピーチ部門では安曇野市出身で小松大学の学生、溝邉幹太さん(21)が優勝しました。溝邉さんは中国南京に4か月間短期留学した時、色々な国からの留学生と交流した体験を語り、「本音で話し合う中で真の友人ができた。国同士も仲良くなれると」と述べました。準優勝の久保田弘樹さん(19)は長野高専の学生で、「祖父と100年前日本に留学した中国青年との間の手紙を見て友好の大切さを感じた」と発表しました。 |
||
HSK中国語検定に18名が挑みました(9/19)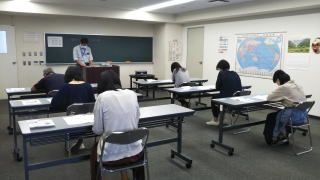 HSK中国語検定が9月19日、長野ラジオ孔子学堂教室において開催されました。当日は中学生から、高校生、大学生、一般社会人ら18名が2級から6級までの検定にチャレンジしました。 HSK中国語検定が9月19日、長野ラジオ孔子学堂教室において開催されました。当日は中学生から、高校生、大学生、一般社会人ら18名が2級から6級までの検定にチャレンジしました。会場には、午前9時には受験生が入室、9時半から2・4・6級の試験が始まりました。午後は1時半から3・5級が行われました。リスニング(聞き取り)、続いて読み取り、作文と続きます。皆さん真剣な面持ちで試験に挑みました。 感想は「リスニングが難しかった」とのこと。 長野ラジオ孔子学堂では、次回は来年3月27日にHSK検定を予定しています。地元長野で受験でき、学生割引もあり喜ばれています。 |
||
ワールドフェスタin長野、長野市日中も参加出展、民族楽器演奏も好評でした(9/12) 長野市日中友好協会は9月12日、長野市セントラルスクゥエアで開催されたワールドフェスタin長野に参加出展し、あわせて民族楽器フルス演奏を披露し好評を博しました。 長野市日中友好協会は9月12日、長野市セントラルスクゥエアで開催されたワールドフェスタin長野に参加出展し、あわせて民族楽器フルス演奏を披露し好評を博しました。セントラルスクゥエアのオープン記念もかねて行われ、加藤久雄市長らが出席し、22年前の長野オリンピック表彰式が行われた記念の場所が市民の憩いの記念公園として再出発することを祝いました。くす玉割りの後、地元鍋屋田小学校の子供たちの”輪になって踊ろう”のダンスなども披露されました。そしてワールドフェスタに参加した各国際交流団体の舞台披露が行われました。 中国文化サロン・フルス教室メンバーによる民族楽器フルス(ひょうたん笛)の演奏は、澄み切った楽しい音を会場いっぱいにとどろかせ、来場者の注目を集めていました。指導に当たっている中国帰国者の関亜菊さんはタイ族の民族衣装を身にまとい情感溢れる曲を披露し拍手を浴びました。 長野市日中のブースでは、中国語教室や中国文化サロンの紹介、「市日中40年記念誌」、「人民中国」の紹介が市日中役員のみなさんによって行われました。コロナ禍のため開催が危ぶまれましたが、アウトドアでの開催となり、大勢の皆さんが来場いただき盛り上がりを見せたつどいとなりました。 |
||
オンラインで遠隔会議やインタビュー(8/27・8/31) 8月27日、日中友好協会全国本部の広報委員会がZoomを用いてオンラインで開かれ、長野県日中友好協会事務所のパソコンから西堀正司副会長(本部専務理事)が参加しました。岡崎理事長や吉田広報委員長ら8名が画面に映し出され、司会者の指名に基づいて話し手の顔が大写しになり、臨場感もあって、濃い内容の会議となりました。長野県協会としては初めての経験でしたが、全国本部では、若手青年委員会をはじめ、積極的な活用にシフトしてきているとのことです。終了後長野県でも導入を検討していきたいなと話し合ったところです。 8月27日、日中友好協会全国本部の広報委員会がZoomを用いてオンラインで開かれ、長野県日中友好協会事務所のパソコンから西堀正司副会長(本部専務理事)が参加しました。岡崎理事長や吉田広報委員長ら8名が画面に映し出され、司会者の指名に基づいて話し手の顔が大写しになり、臨場感もあって、濃い内容の会議となりました。長野県協会としては初めての経験でしたが、全国本部では、若手青年委員会をはじめ、積極的な活用にシフトしてきているとのことです。終了後長野県でも導入を検討していきたいなと話し合ったところです。長野高校は文部科学省から「地域との協働による高等学校教育改革推進事業校(グローカル型)」に指定されていて、「SDGs持続可能な開発目標から見た長野のグローカル戦略(2学年)」という授業を探求学習の一環として実施していて、この取り組みでは生徒たちが研究テーマごとにグループを作り県内の企業や団体を訪問するフィルードワークを実施して研究を深めているそうです。その関係で8月31日、長野高校の2年生Ⅿさんから日中友好に係るインタビューを対面で行いたいと申し込まれていましたが、コロナ禍の感染拡大もあって、オンラインでのインタビューになりました。布施正幸理事長がパソコンの前に座ると、双方の顔が画面に映し出され、インタビューが始まりました。Mさんの自己紹介とプレゼンテーションのあと中国人の対日感情、日中の個人間交流の現状、中国人が感じる日本人の課題、個人間交流としてできることなど熱心な質問が出され、真剣に答えました。1時間ほどの対話でしたが相手の表情や熱心さが直接伝わってきてオンライン対話も良いもんだと実感しました。 Mさんからは、次のようなお手紙をいただきました。若い世代が真剣に中国に関心をもって受け止めていただいたことをうれしく思いました。 ――フィールドワークにご協力いただきありがとうございました。日中友好という課題について中国側からの視点で見た実情や日中関係の歴史的背景など非常に参考になるお話をたくさんいただきました。特に、歴史認識の薄さという日本人の課題には改善の余地を感じたり、中国人の方々の魅力について伺って研究のモチベーションを得たりと実り多いフィールドワークとなりました。今回の成果をもとに課題研究を進めていきます。ありがとうございました。 |
||
| 県日中学術交流委員会総会を開催(8/3) 濱田州博会長(信州大学学長)は「コロナ禍にあって5月の日中学長会議が延期となるなど、日中間の交流がストップしていることは大変残念だ。信州大では留学生が大勢いるが実験実習などができず困っている。一方協定を結んでいる大学からマスクの寄贈があった。相互に訪問して対面交流することは当面むずかしと思うが、オンラインでの交流等工夫していきたい。再開に備えて準備していきましょう」とあいさつしました。 席上、宮原茂県国際担当部長と西堀正司県日中友好協会副会長よりあいさつをいただきました。宮原部長は「長野県として上海駐在員に加えて新たに北京駐在員を増やす方向で準備している。昨年は中国要人の来県や知事訪中も実現した。国同士の関係は難しい面もあるが、地方民間交流をしっかり進めていきたい。中国を相手国とする東京五輪ホストタウン事業には大学生の皆さんにも参加いただきたい」と述べました。西堀副会長は「コロナ禍で諸交流がストップして、友好協会70周年記念活動も延期となっている。習近平主席の4月訪日も延期となったが、友好協会は引き続き国賓としての来日を歓迎することを決めた。中米対立の激化は人々の憂うるところだが、日本はバランスをとって役割を発揮してもらいたい」とあいさつしました。 |
||
| 松本日中友好協会定期総会、コロナに負けず友好活動(7/13)
|
||
| 東山魁夷館30周年記念で「漓江暮色」を展示(7/3) 唐招提寺の障壁画の制作の依頼を受けて、鑑真和上の魂を慰めたいと考えた魁夷画伯は第1期の制作分に日本の海と山を描くこととし、6度目盲目の身となって日本の土を踏んだ和上にこれをささげ、第2期には和上の故郷の揚州、桂林、黄山の景観を水墨画で描く構想を持ったと言われます。1973年から80年まで足掛け8年の歳月をかけこの制作に打ち込んだ魁夷画伯の姿勢には並々ならぬ決意が感じられます。 1976、77、78年に三度中国を訪れ、関係各地でスケッチをしています。改革開放前の中国にあっての現地写生訪問は特別許可を必要とするもので困難もあったでしょう。 「漓江暮色」や「桂林月夜」は一見水墨画の様に見えますが、岩絵の具をもちいた日本画として描かれています。この絵は「色彩を止揚した水墨画の世界への歩み」と評価されているそうです。是非実物をご覧ください。 なお、以前、中国研究者の矢吹晋横浜市立大学教授からお聞きしたことですが、1972年9月田中角栄首相が日中国交正常化のために中国を公式訪問した折、毛沢東主席へ贈られた記念品は魁夷画伯の作品「春暁」であったとお聞きしました。展示の年表のなかにその記載があることを確認して往時を思い浮かべながら松林に囲まれた魁夷館を後にしました。 <東山魁夷、関係年表>
|
||
| 中国文化サロン講座もスタート(7/2) 二胡教室は長谷川宗利先生の指導で、入門から初級・中級までの皆さんが挑んでいます。教え方がうまく、先生に褒められながらコツをつかんで二胡らしい音色が出せるようになったと喜んでいました。バイオリンと似通った味わい深い音色です。 フルス教室は関亜菊先生。フルスは少数民族の民族楽器で、日本の縦笛に似た明るい音がでます。初級と中級コースがあり音を出すコツをつかむと曲目をだんだん増やしていきます。帰国者のつどいなどで舞台に上って演奏したこともあります。 中国茶の先生は張淑華先生で、中国茶をいただきながら、中国茶の歴史=医薬効用のある貴重な飲み物であったことを学習し、種類、作法更にツボ・マッサージまで解説していただき皆さん満足でした。 中国の歌は範為為先生。カラオケで「月亮代表我的心」「夜来香」を思い切り歌い、その後中国語の歌詞を丁寧に解説、中国語の学習も十分しての2時間でした。 各教室への参加を希望される方は長野ラジオ孔子学堂事務局まで(TEL026-224-6517担当:戸井田) |
||
| 県日中スキー交流委員会20年度総会(6/23)
太谷陽一県スキー連盟副会長は「中国スキー協会との太い連携のもとに40年にわたり日中スキー交流の成果を上げてきた。中国は22年の北京冬季オリンピックを目指して頑張ってきた。新型コロナの逆風があるが、これに負けず、しっかりと歩みを進めていきたい」とあいさつしました。宮坂雅昭県スポーツ振興係長、根橋幸夫県国際交流課長、西堀正司県日中友好協会副会長があいさつし「コロナウイルスとの共存との考えに立って中国との交流、オリンピックに向かってのスキー交流を一歩一歩進めていきたい」などと述べました。 本年の計画として、中国スキー訓練隊の受入れ、県ジュニアスノーボード訓練隊の派遣・オリンピック開催地での訓練などをあげています。 |
||
| HSK中国語検定に17名が挑む(6/14) 会場となった長野ラジオ孔子学堂教室には、午前9時には受験生が入室、9時半から2・4・6級の試験が始まりました。午後は1時半から1・3・5級が行われました。最初はリスニング(聞き取り)、続いて読み取り、作文と続きます。皆さん真剣な面持ちで試験に挑みました。 学生、社会人で女性が多かったです。終わってからの感想は「やはりリスニングが難しかった。でも自信はあります」とのこと。「これからも一つ上を目指して頑張ります」意欲的な答えが返ってきました。 長野ラジオ孔子学堂では、次回は9月19日にHSK検定を予定しています。地元長野で受験でき、学生割引もあり喜ばれています。 |
||
|
程永華前中国駐日大使が中日友好協会常務副会長に就任(6/12) この度、中日友好協会常務副会長に就任しましたことを謹んでご報告します。 まず、9年余りに亘る中国駐日本大使在任中に、先生をはじめ貴会から多大なご支持ご協力をいただきましたことに対し、改めて御礼申し上げます。この度の中日友好協会常務副会長就任は、四十数年に亘る日本とのお付き合いの延長線にあり、民間友好事業に努める上での新たなスタートであると認識しております。今後とも、友好の初心を忘れず、引き続き貴会ひいては日本各界と協力し合い、各分野における友好交流を積極的に展開し、両国民間の友情増進と、中日友好事業の更なる発展のために努力してまいる所存です。 新型コロナウイルスの感染という困難な局面にあたり、中日両国の人々が助け合い立ち向かう姿は、中日民間友好の厚い基盤の現れであると思います。中国と日本が共に困難を乗り越えられることを強く信じており、これにより両国民間の絆はより固く結ばれ、中日関係の歩みもより力強いものになると私は確信しております。 先生のご指導の下、貴会が長きにわたり中日友好の精神を堅持し、両国友好事業を推進するために貢献してこられました。今後ともご支持ご協力を心よりお願い申し上げます。 皆様のご健康を祈り、皆様と再会し、旧交を温める日を心待ちにしております。 まずは略儀ながら書中にてご挨拶申し上げます。 敬具
|
||
| 中国語講座2カ月ぶりに再開、教室に賑わい(6/11) 消毒と換気に心がけ、間隔を十分あけて、先生も受講生もマスクをつけての授業ですが、皆さんこの日を待ちわびていたそうです。2か月ぶりに教室に賑わいが戻り、中国語が響きました。 休むことなく継続することが語学学習の常道だそうです。同学の頑張りを感じながら学んでいる様子に喜びが伝わってきました。 中国語講座は初級・準中級・中級・上級クラスに分かれていて、それぞれ午前の部と夜の部があります。関心おありの方は、授業参観もできます。 |
||
|
新型コロナウイルスには負けない!友好の絆で難関を乗り越えよう ! (6/1) 須坂市日中友好協会では「日本と中国須坂市版45号を発行し、”友好の絆で新型コロナを乗り越えようと会員、市民に呼びかけ、友好都市の吉林省四平市との間でマスクの相互贈呈・支援や市長や議長、中学生の応援メッセージのやり取りなどを紹介しています。全文はこちら <須坂市と四平市の中学生が応援メッセージを交換>
●新型コロナウイルス感染が拡大して行く中、僕はとても心配しています。皆さんどうお過ごしでしょうか。感染が落ち着いて自由に行き来できるようになって、四平市を訪れてみたいです。皆さんもいつかぜひ須坂市に来てください。大歓迎します。また会える日を楽しみにしているので。皆さあん頑張りましょう。(常盤中・長岡佑真) ●新型コロナウイルスのことが、日本でも毎日のように新聞やニュースで報道されています。皆さん、大変なことが多いでしょうが頑張ってください。四平市の皆様のことを、すごく心配しています。今、すごく大変なときですが、体調に気をつけて、力を合わせて頑張ってください。(相森中・王鉅琦) ●今や全世界にコロナウイルスが広まり、現在、みなさんの心には「不安」「心配」という感情が渦巻いていることと思います。半年前の訪問時のような温かい笑顔が溢れることを祈っておりますが、もし不安に押しつぶされるようなことがあれば思い出していただきたいことがあります。私は「応援」している、ということです。みなさんの笑顔が一日でも早く戻られますように。お元気で。(東中・小山華穂) ●今、中国と日本はコロナウイルスが流行していて大変な状況です。しかし、友情はいつもでも変わらないと僕は思います。僕たちも頑張るので、中国・四平市の皆さんも頑張ってください。僕はまた、中国・四平市に行きたいと思っています。そして四平市の皆さんも須坂市に来てください。 (東中・別所宏哉) ●私は昨年8月に迎え入れてくださった方々の優しさに振れ、中国に親しみを抱きました。中国の皆さんありがとうございました。新型コロナウイルスの流行により日本国内でも発症者が出ており、不安が広がっていますが、中国ではさらに大きな不安を抱えられていることでしょう。いつか日本に来ていただけたら嬉しいです。私の住む長野県でも昨年10月に台風19号により大きな被害を受けました。その際には「日本加油」などの声援をいただきました。今回の困難も力と想いをあわせて乗り越えていきましょう。中国加油!(墨坂中・坂本あかね) <四平市第三中学校からの返信> ▼坂本あかねさん、こんにちは。前回の交流の後、日本の文化への理解が深くなりました。日本の富士山と桜はとても綺麗で、温泉も快適だと聞きました。これから観光に行く時はまたお邪魔するかもしれませんよ。今回の新型コロナウイルス感染による肺炎は突然発生しましたが、私達は慌てることなく、整然と防疫作戦を進めています。日本の友人からの心遣いは、私たちに大きな励ましを与えてくれました。あなた達の支持が集まり、冬の寒さを和らげてくれます。私達は「冬は必ず春となる」と確信になりました。(吉林省四平市第三中学校8年18組・ 宋伯瑜) ▼小山華穂さん、こんにちは。気にかけてくれてありがとうございます。中国全国は一丸となり、新型コロナウイルスに立ち向かっています!ビデオ通信で授業を受けています。多くの先生が初めてネットに触れるので、大変です。先生は私たちのために心血を注ぎます。とても感謝しています。須坂市が四平市にマスクを寄贈してくれたことに感謝します。手を携えて難関を乗り切りましょう。また中国に来てください。(四平市第三中学校8年18組・宋佳興) ▼石井天さん、こんにちは。手紙をもらって、とても嬉しいです。中国のことを心配してくれてありがとうございます。中国はきっと乗り越えられますと思います。先生はオンラインで授業をしています。須坂市は四平市にマスクを寄贈してくれて、第三中学校のみんなは感謝しています。中国頑張れ!日本頑張れ!中日友好が長く続くこと、温かい春が来て花が咲く時に、すべての平穏に戻り、マスクを外して、太陽の下を走ることができるよう祈ります。また中国を訪問することを歓迎します。(吉林省四平市第三中学校 8年17組・程梓恒) ▼長岡佑真さん、こんにちは。長岡さんの心のこもった挨拶に対して感謝します。同時に日本の皆さんが元気でいられるよう祈ります。去年の夏、私達は一同に楽しく集い、須坂市と四平市の友情をいっそう深めさせました。須坂市がマスクを寄付してくれて、寒い冬の中の暖かさを与えてくれてありがとうございます。春はすでに来ています。新型コロナウイルスは必ず過ぎ去っていきます。みんなで頑張りましょう。また皆さんの笑顔に会える日を楽しみにしています。(四平市第三中学校8年17組・籍悦莱) ▼別所宏哉さん、こんにちは。私たちのことを気にかけてくれてありがとうございます。我が国で爆発した新型コロナウイルスはすさまじい勢いですが、必ず乗り越えると思います。私達はネット中継で授業を受けています。須坂市が四平市のためにマスクを寄贈されたと聞き、とても感動しました。中日の友情が変わりことなく長く続けられるよう、今の状況が早く終わるよう祈ります!(四平市第三中学校8年17組・王若丞) 四平市からマスクの寄贈を受けました 去る4月7日、四平市から日本の新型コロナウイルス感染拡大に伴い、須坂市でマスクは足りているか、もし不足しているなら四平市の在庫から支援をしたいとのメールが届きました。 須坂市では、ウイルス感染拡大に伴い、マスク不足になっており、医師会や介護事業者等からマスク確保の要請が来ているところから、四平市からのマスクの支援を受けることになりました。2月に四平市からの要請で、須坂市からマスクの寄贈をしましたが、コロナウイルス感染の封じ込めにほぼ成功した四平市から、今度は拡大する日本の状況を心配し、支援したいという申し出になったものです。 四平市からのマスク1万枚は5月7日に到着しました。不幸な新型コロナウイルス感染拡大ですが、須坂市・四平市両市の友好都市としての絆が一層深まることにもなりました。 |
||
| 第58回長野県日中友好協会定期大会―友好協会の原点を踏まえ新時代に備えようー(5/21)
<書面決議で実施、新年度方針と新役員を選出> 活動方針では、友好協会創立70周年にあたり、新型コロナ禍を乗り越え、友好協会創立の原点に立ち平和友好条約を基礎に交流の再開、国民感情の改善、友好関係の発展を目指すことなどが掲げられています。役員改選では高波謙二会長はじめ新役員を選出しました。 |
||
| 深圳市の企業から長野県に3万枚のマスク、県協会にも8千枚が寄贈(5/20) 高波謙二県日中友好協会会長、西堀正司副会長らはこの日県庁を訪れ、阿部守一県知事と会見し、深圳市易聯技術有限公司から送られてきたサージカルマスク3万枚を届けました。 2016年4月に同公司の華青副社長が、中国大使館の呂克倹元公使とともに長野県観光部や県友好協会を訪問交流したのを縁としてこの度の寄贈となったもの。県協会あてにも別途8千枚のマスクが寄贈されました。 高波会長から贈呈書を渡された阿部知事は、「新型コロナにとの闘いが続いている中で大変ありがたい。県内の医療機関や社会福祉施設等に配布、活用していきたい。あたたかい支援に心から感謝したい。中国との交流に力を入れてきた長野県として、コロナ禍が一日も早く収束し、再び交流が再開されることを祈っている」と述べました。  日中両国旗が飾られ3万枚のマスクの入った段ボール箱の前で記念撮影をしました。 日中両国旗が飾られ3万枚のマスクの入った段ボール箱の前で記念撮影をしました。箱には「一衣帯水 守望相助」(一衣帯水の隣国同士互いに助け合っていきましょう)と記された鮮やかな紙が添付されていました。 |
||
| 哈爾濱市の日本遺孤児養父母連絡会よりマスクが届きました(5/15) 5月15日、哈爾浜市の「日本遺孤児養父母会」(胡 暁慧会長)より、「コロナウイルス感染に打ち勝ち、頑張りましょう」と満蒙開拓平和記念館(寺沢秀文館長)ならびに飯田日中友好協会(清水可晴会長)宛に《友情のマスク》が贈られて来ました。 輸送手段等が大変困難の中、贈られてきたもので、早速、養父母会の皆様の温かいご支援に感謝しつつ、かつて中国の養父母の皆さんに助けられ、立派に養育して頂いた「飯伊中国帰国者連絡会(多田清司会長)」に贈呈しました。 因みに本年は敗戦から75年の節目の年に当たります。一方で、新型コロナウイルスの感染が急激に広がっています。今こそ、平和友好を中心にした行動こそが、第一と痛感しています。頂いたマスクは,帰国一世の皆さんを中心に配布しようと事務局で進めています。 ありがとうございました。 |
||
人民中国雑誌社からマスク1000枚が届く(4/30) 人民中国東京支局(于文支局長)から読者会あて感染予防のマスク1000枚が届きました。早速、茂木博読者会会長はじめ役員が同封されていた激励のメッセージとともに会員の皆さんに配布しました。 人民中国東京支局(于文支局長)から読者会あて感染予防のマスク1000枚が届きました。早速、茂木博読者会会長はじめ役員が同封されていた激励のメッセージとともに会員の皆さんに配布しました。茂木会長は「長野県は感染者の増加が比較的低く抑えられているがマスク不足は深刻で、大変ありがたい。友人の皆さんの思いを受け止め、今後とも読者会活動に取り組んでいきたい」と語っていました。 メッセージには劉徳有先生の和歌と王衆一先生の漢歌が添えられていました。 漢歌は和歌の5・7・5・7・7にあわせて作られた漢詩の一種です。ちなみに俳句の5.7.5にあわせて作られたものは漢俳と言われています。愛好者が広がっています。
|
||
| 中国体育総局が長野県にマスク1万枚寄贈、大使館や友人からも友好協会に(4/15) マスクは段ボウル5箱分で、箱には、中国と日本の国旗と、「一衣帯水」、「両心相依」(近い隣国で心が通い合っている)と記した紙が貼られていました。日本のマスク不足を知った同局から4月2日、県に寄贈を申し出るメールがあり、10日に届いたものです。 同封されていた親書には「日本が感染症対策に悩んでいることを、わが身の事の様に思っています」などとつづられていました。根橋幸夫県国際交流課長は「大変ありがたい。この危機を乗り越え、東京五輪のホストタウンとして中国選手を迎えたい」と述べました。 なお、4月15日、公益社団法人日中友好協会を通じて県協会あてに中国大使館から1200枚のマスクが届きました。先に全国本部の呼びかけに応えて義援金を贈ったことに対する感謝の意を込めて届けられたものです。(短期間でしたが義援金は総額721万円、県協会からは147名の協力で61.8万円が集約され、中国大使館に託されました。) 更に以前、長野に滞在したことのある中国国際放送局の鄧徳花さんからマスクを沢山贈っていただきました。「北京もまだ事態は厳しいですが、マスクの生産は徐々に回復してきて、買えるようになりました。ワクチンが開発されるまで、まだ今のような生活が続くと思いますが、でもきっとみなさんと会える日が来ると信じています。今までのような日常が戻ると信じています。また会える日を楽しみにしながら、一緒に頑張りましょう」とのメセージが添えられていました。心のこもった思いに胸を打たれました。 |
||
| 長野ラジオ孔子学堂中国語講座2020年度受講生募集がスタート(3/1) おもてなし中国語、始めませんか! 2020年度受講生の募集が始まりました。 ≪毎週2時間の学習! 月謝は3,000円!≫ 新年度の授業は4月の第1週からスタートします。 お誘い合ってご参加ください。 お申し込みは、長野ラジオ孔子学堂中国語講座まで |
||
長野ラジオ孔子学堂のホームページが開設されました!(1/17) 長野ラジオ孔子学堂のホームページガ開設されました。 長野ラジオ孔子学堂のホームページガ開設されました。中国語講座や中国文化サロン、HSK中国語検定の申し込みもできます。 閲覧してください。 ここをクリック→長野県日中友好協会ラジオ孔子学堂 |
||
| 孔鉉佑駐日大使、阿部長野県知事と会見(2020.2/17) 孔大使は次のように述べた。習近平主席の堅固な指導の下、中国人民は現在一致団結して新型コロナウイルス肺炎の感染と戦っており、現在、情勢にプラスの変化が見られる。日本各界の中国に対する積極的支援は隣国同士、互いに見守り助け合う良き伝統を十分体現している。現在、感染は日本国内でも広がっており、中国は日本と情報を共有し、有益な経験を共有する用意があり、積極的に協力し、感染予防抑制阻止の戦いに共に打ち勝ち、今年の中日両国間の政治的交流や東京オリンピックなど重要日程のために良好な雰囲気をつくることを願っている。長野県は長年、中国との友好往来に尽力している。観光資源が豊富で、中国の観光客にずっと人気がある。中国は長野との観光、食品・農産物など各分野の交流・協力を引き続き強化することを願っている。 阿部知事は中国の新型肺炎感染に見舞いの言葉を述べ、長野県の支援を紹介し、現在、日本国内も感染の拡散を全力で阻止しており、中国と引き続き連携を強め、感染に早期に勝利することを願っていると表明した。知事は次のように述べた。長野県は対中友好関係を一貫して重視しており、両国の重要ハイレベル往来を契機とし、対中交流・協力を持続的に深めることを願っている。県と県内の幾つかの市は東京五輪で中国選手団を受け入れるホストタウンとなっており、受け入れに積極的に取り組み、ホストとしてしっかりもてなしたいと願っている。冬季五輪の元開催地として長野県は中国の2022年北京五輪開催を引き続き支援する。(中国大使館ホームページより) |
||
日中友好新春女性のつどい、変わらない友情エールを送る(2/6) 県日中友好協会女性委員会は2月6日、長野市のホテル信濃路において2020年日中友好新春女性のつどいを開きました。つどいには各地区協会の女性委員会の代表や女性会員ら40名が出席し、交流懇親を深めました。 県日中友好協会女性委員会は2月6日、長野市のホテル信濃路において2020年日中友好新春女性のつどいを開きました。つどいには各地区協会の女性委員会の代表や女性会員ら40名が出席し、交流懇親を深めました。宮沢信代委員長は、日ごろの活躍協力に感謝した後、「日中間の交流が前向きに進みつつあり希望の光が差してきている。英知を働かして課題を解決し、変わらない友情で自分を守りながら中国の友にコロナウイルスに負けないようエールを送っていきましょう」とあいさつしました。 お話し講演では、国際中医薬膳指導員の山岸美智子先生が「人生100年、今こそ薬膳養生ー健康な体で豊かな人生を過ごすためのヒントー」と題してお話していただきました。漢方理論を基本とした薬膳養生のお話しに続いて、ストレス社会にあって深呼吸して体をリセットし、日々の刺激によって脳に栄養を送り、毎日次のことを実践しましょう。一回は笑う、十人と会う、百の文字を書く、千字読む、万歩歩く--愉快な話に皆さんうなずきながら聞き入りました。 懇親交流会ではなごやかな語らいと交流が続きました。最後に大きな輪を作ってふるさとを合唱しました。 高波謙二県日中会長も出席して、日ごろの協力に感謝しエールを送りました。また会に先立って、バザーが行われ、各自が提供した物資をそれぞれが買い求め資金作りに役立てました。 |
||
| 「新型コロナウイルス肺炎」に対する緊急支援募金のお願い(2/4)
このような状況の中で、日中間の人的交流や文化交流などが中断されており経済交流にも影響が及んでいます。一日も早い終息を願ってやみません。県協会は、公益社団法人日中友好協会全国本部(丹羽宇一郎会長)の呼びかけに応え、下記により義援金の募金活動に取り組んでいきたいと存じます。 つきましては、下記の通り皆様のご支援ご協力をお願い申し上げます。 2020年2月 長野県日中友好協会 会長 高波 謙二 |
||
| 日中友好新春座談会・新年会開催(1/15) 第1部の日中友好新春座談会では、高波謙二会長があいさつし、日ごろの会員の皆さんの協力に感謝し、あわせて、昨年10月の台風災害で被災された皆さんへお見舞いを申し上げた後、「日中関係は首脳の相互交流が継続され大きく改善してきている。中国国民の日本に対する好感度は、訪日者数1000万人、世論調査の数字を見ても大きくアップしているが、日本人の対中好感度は、あまり変化しておらず、訪中者数も260万人と大分ギャップがある。相互信頼増進のため引き続き努力したい。10月には友好協会創立70周年祝賀大会が北京の人民大会堂で開催される。県協会も10年前の時の様に大勢で参加し、河北省も訪問したい。東京オリンピックイヤーにあたり、青年交流に弾みをつけ、友好交流を発展させ、後継者を育てていきたい」と述べました。 また、花岡徹県国際担当部長が日ごろの協会の協力に感謝した後、「友好協会のみなさんの活動の土台の上に県の河北省や北京市などとの交流が活発に行われている。東京五輪・パラにあたって中国を相手国とするホストタウンの取り組みを進めており、昨年は中国国家体育総局の苟仲文局長、北京市党書記の蔡奇北京五輪組織委員会主席を迎え、長野冬季五輪の経験を紹介し交流した。スキー場視察団や訓練隊受入れなどが行われている。県スキー連盟がクロスカントリーの訓練隊を派遣し吉林の地下壕を活用した人工コースで河北省チームと合同訓練が実現した。日中関係改善の中で、県も一層交流を進めていきたい」とあいさつしました。 中澤保範事務局長が第2回理事会(11/26)で決定された今年の主な事業計画を報告し、「日中関係好転のチャンスを活かし、日中友好協会創立70周年にあたり、友好交流の活性化と信頼関係の増進に努める。*日中友好協会創立70周年記念祝賀大会(北京人民大会堂)に合わせて長野県日中友好協会訪中団はじめ各種訪中団の派遣 *講演と祝賀のつどい開催 *中国を相手国とする東京五輪ホストタウン交流の取り組み *北京冬季五輪への協力) などにとりくんでいきたい」と述べました。 続いて布施正幸理事長の司会でディスカッションに入り、日中関係の現状と課題について西堀正司副会長の解説の後、地区活動や各分野の交流などについて活発に意見交換が行われました。 日中友好協会創立70周年に当たり、地域に根差した交流活動を通じて県民にPRし新会員の入会や後継者の養成に力を入れていくことなど抱負が語られました。 小岩副知事、倪健公使参事官、井出庸生・杉尾秀哉代議士、荒井武志県会副議長、小林東一郎・中川博司・高島陽子県議から祝辞をいただき、竹節義孝山ノ内町町長の音頭で乾杯しました。 倪健公使参事官は、「長野県では官民一体となった交流が進められ、地方民間交流の模範となっている。中国を相手国とする東京五輪のホストタウンとなり更に北京冬季五輪に向けての交流を進めている。中国は長野冬季五輪の精神、やり方を勉強している。昨年、日中関係は大変重要な1年だった。年末には習近平・安倍会談が行われた。今春、習近平国家主席の訪日が予定されており、更なる友好の新時代を作っていく大きなきっかけとなるものと期待されている。長く青年組織の仕事に携わってきたので日中青年交流を通じて長野県にも友人が多い。日本の中心に位置する長野県日中の一層の活躍に期待したい」と、激励いただきました。 親しく懇談交流が行なわれ会場は和やかな雰囲気に包まれました。花岡徹県国際担当部長の音頭で万歳が行なわれ、西堀正司副会長の閉会あいさつで閉会となりました。 来賓として前記各氏のほか付博二等書記官、根橋幸夫県国際課長、太田昌孝(代理)代議士、若林健太・小松裕(代理)前国会議員、王昌勝県華僑総会会長、謝宏宇中国国際放送局長野孔子学堂中国側責任者、市村洋長野市国際室長、横山秋一白馬村副村長、春原直美県国際化協会センター長、市村和久長野大学常任理事、矢ケ崎雅松本歯科大学理事長(代理)、梶田龍孝県経営者協会次長、渡辺義作県中小企業団体中央会連携支援部長、高橋孝一県商工会連合会常務理事、馬場進一県商工会連合会参事役、西川勝県信用保証協会常勤理事、岡村重信県プロフェッショナル人材戦略拠点事務局長、松澤佳子県平和人権環境労組会議議長、中本栄部落解放同盟県連書記長、今井正子前県議らのご臨席をいただきました。 |
||
|
明けましておめでとうございます。日ごろの日中友好事業へのご理解ご協力に厚く感謝申し上げます。また、昨年10月の台風19号で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
|
||
中国スキー協会代表団来県、スキーの大衆化に向けて、インストラクターシステム学ぶ(12/21)2019 李佳軍・中国国家体育総局冬季運動管理中心大衆氷雪部副部長一行3名が12月20日から22日長野県日中スキー交流委員会の招きで長野県を訪れ、県スキー連盟や県日中友好協会、白馬村スキークラブ関係者らと交流し、中国におけるスキーの大衆化にむけて、インストラクターシステムを熱心に学びました。 李佳軍・中国国家体育総局冬季運動管理中心大衆氷雪部副部長一行3名が12月20日から22日長野県日中スキー交流委員会の招きで長野県を訪れ、県スキー連盟や県日中友好協会、白馬村スキークラブ関係者らと交流し、中国におけるスキーの大衆化にむけて、インストラクターシステムを熱心に学びました。一行は、県スキー連盟の太谷陽一副会の案内で、白馬八方スキー場やジャンプ台を視察した後、白馬スキークラブの事務所を訪れ、日本のインストラクターシステムの説明を受けるとともに今後の交流について熱心に意見交換しました。 また歓迎会には、太谷副会長、西堀正司県日中友好協会副会長はじめ、県スキー連盟、県日中友好協会、長野・白馬・野沢温泉の各スキークラブ関係者が出席し、一行を歓迎し、交流を深めました。 |
||
| W杯スピードスケート・長野大会 中国選手団へ熱い声援 (12/13~15) 2019
日本を代表する小平奈緒さんや高木菜那・美帆姉妹の活躍で大会も盛り上がりを見せましたが、2年後に迫った北京冬季オリンピックが開催される中国からも男女合わせて29名もの選手のエントリーがありました。 中国を相手国とするホストタウン事業を実施している長野県と長野市の日中友好協会では、この機会に中国選手の応援をしようと関係者に呼びかけ、競技会場のリンクコーナーに応援席を設けて、小旗を振りながら「加油(ジャーヨ!=ガンバレ!)中国」の声援を送りながら、東京オリンピック後の北京冬季オリンピックの成功も祈念したところです。 |
||
| 長野孔子学堂中国語教室年末交流会、訪中報告や中国語の体験を発表(12/7) 2019 竹内勲学堂長は「長野ラジオ孔子学堂中国語講座は県日中友好協会と中国国際放送局が2007年に提携してスタートしたが、中国語を学ぶ会時代から数えると40数年になる」と振り返りつつ、「継続は力。友好の懸け橋としての中国語学習の輪を広げていきたい。今日は中国語学習者同士の交流を深めてください」とあいさつしました。 訪中団に参加した伊藤iさんは中国国際放送局日本語部の皆さんからあたたかい歓迎を受け交流した状況や、故宮や万里の長城、世界園芸博覧会などを参観した様子を映像を交えて報告しました。 中国語学習の体験発表では伊藤kさんや大矢さんらが発表しました。千里の道も一歩から、孔子学堂の老師から熱心に指導をいただき、HSK中国語検定で新たな目標をもって頑張ってきたこと、歳はとっても学び続ける意気込み、スピーチコンテストに出場してレベルアップにつながったこと、学生とともに中国でのインターンシップ体験をし交流を深めてきたことなど興味深い話に皆さん熱心に聞き入っていました。 第2部の交流懇親会では西堀正司・孔子学堂理事長があいさつし、謝宏宇・国際放送局孔子学堂責任者の音頭で今後の中国語学習の普及と向上のために来年も頑張って行きましょうと乾杯しました。中国文化サロンで学んでいるメンバーが民族楽器フルスや、二胡の演奏を披露したり、お楽しみビンゴゲームで盛り上がり、なごやかな交流会となりました。 |
||
| 河北省冬季オリンピック弁公室訪日団、人材養成協力を協議(11/27~29) 2019
|
||
| 第23期 日中関係を考える連続講座スタート、第1回は「令和・万葉歌人と漢文学」(11/23)
|
||
河北省農業庁訪日団来県、りんご園など参観,(11/20~22) 河北省農業庁訪日団(王国発・河北省農業農村庁長一行15名)が11月20日から22日長野県を訪問しました。一行は21日午前、JA会館を訪れ、県日中農業交流委員会会長の武重正史・JA長野中央会専務はじめ、県農政課佐藤源彦企画幹、県国際課の春原直美企画幹らから歓迎を受けました。席上10月の台風19号による被災話題となり、鋭意生活拠点の再建に取り組み、引き続いて果樹園など生産拠点の復旧に取り組んでいる様子を紹介するとともに、農業交流について意見交換しました。王団長からは甚大な被災に対し、お見舞いの言葉があり、今後とも農業技術や農産物の加工技術、人材交流などを進めていきたいとの要望が出されました。引き続いて担当者から長野県農業の概況及びJAの仕組みと役割などの紹介が行われました。農協組織の役割などに熱心な質問が行われました。 河北省農業庁訪日団(王国発・河北省農業農村庁長一行15名)が11月20日から22日長野県を訪問しました。一行は21日午前、JA会館を訪れ、県日中農業交流委員会会長の武重正史・JA長野中央会専務はじめ、県農政課佐藤源彦企画幹、県国際課の春原直美企画幹らから歓迎を受けました。席上10月の台風19号による被災話題となり、鋭意生活拠点の再建に取り組み、引き続いて果樹園など生産拠点の復旧に取り組んでいる様子を紹介するとともに、農業交流について意見交換しました。王団長からは甚大な被災に対し、お見舞いの言葉があり、今後とも農業技術や農産物の加工技術、人材交流などを進めていきたいとの要望が出されました。引き続いて担当者から長野県農業の概況及びJAの仕組みと役割などの紹介が行われました。農協組織の役割などに熱心な質問が行われました。一行は、この日午後、飯綱町の原山武文さんが経営するりんご農場を訪れ視察交流しました。原山さんは同町日中友好協会の会長で、中国の遼陽市にりんご栽培の技術指導に何度も訪れるなど交流しています。4haのりんご栽培をしていて、富士を中心とした収穫の真っ最中でした。10人近くの皆さんがもぎ取り作業をしていました。また町の農政課長さんや友好協会役員の皆さんも歓迎してくれ真っ赤に色づいたりんごのもぎ取り体験もして全員で記念写真に収まりました。河北省にも技術指導に来ていただきたいとの要請もありました。 続いて山ノ内町の乳牛飼育・加工場を行っている山本宏之さんの飼育場・加工場を視察しました。小規模ですが乳製品の加工などを手掛けている様子を紹介いただきました。 視察を終えてホテルへの帰路、千曲川沿いの被災地を通りましたが、生々しい災害の爪痕をが残っており、一行はじっと見入っていました。 夜の歓迎会には武重・県交流委員会会長、高波謙二・県日中友好協会会長、草間康晴・県農政参事ら長野県側から関係者20名余りが出席しました。なじみの深い河北省外事弁公室の紀竑さんが同行されていてなごやかな懇親交流会となりました。席上王団長より団員の皆さんのお見舞いの志として、被災地への義援金10万円が高波会長に託されました。(この義援金は11/25高波会長が阿部守一知事を訪ね趣旨をお話しして復興に役立てていただくようお渡ししました。) 一行は翌日、農産物加工の長野興農㈱長野工場を訪れ、竹中保義次長らの案内をいただきました。 |
||
県高校生選手が吉林省スキートンネルで合宿、河北省選手とも交流(11/12~17) 長野県スキー連盟は県日中スキー交流委員会の2022年の北京冬季オリンピックに向けての支援交流の一環として、クロスカントリーの強化合宿を11月12日から17日の6日間、中国吉林省の北山四季クロスカントリースキー場のスキートンネルにおいて行いました。このスキートンネルは、かつて地下壕に使われていたものを利用して整備したもので、アップダウンのある1.2kmを周回する素晴らしいコースで通年利用できます。 長野県スキー連盟は県日中スキー交流委員会の2022年の北京冬季オリンピックに向けての支援交流の一環として、クロスカントリーの強化合宿を11月12日から17日の6日間、中国吉林省の北山四季クロスカントリースキー場のスキートンネルにおいて行いました。このスキートンネルは、かつて地下壕に使われていたものを利用して整備したもので、アップダウンのある1.2kmを周回する素晴らしいコースで通年利用できます。 合宿には長野県高校強化選手の男子4名、女子4名とコーチ陣ら11名が参加しました。一行は河北省バイアスロン強化選手とともに数日にわたり一緒にトレーニングを行い、お互いのテックニックの特徴の把握やスピードトレーニングをしながら、しっかりと交流も深め、今後のライバルとして刺激し合うことができました。 中国ナショナルチームをはじめ各省の強化選手たちが北京オリンピックを目指し、国全体で施設管理・選手強化している方針には驚かされました。 滞在先の松花湖プリンスホテルも快適でホテルの皆さんも我々選手に対しサービス精神で対応していただきました。 国の政策としてスノースポーツ人口を3億人に増やすという国家プロジェクトは到底まねできることではありませんが、長野県選手が世界に羽ばたき活躍することで日本・長野を更に認知してもらうことはできます。まずは選手強化育成をしっかりと行い、選手のそれぞれの課題克服のためにしっかりと指導していきたいと思います。 我々コーチ陣も良い経験をさせていただき充実した遠征となりました。(県スキー連盟強化委員長・祢津和利/ヘッドコーチ・川辺俊一郎) |
||
| 人民中国読者会、50回記念に陳文戈社長迎え記念講演と歓迎交流会(11/9) 主催者あいさつで茂木会長は、「読者会は2011年設立以来、隔月で例会を開催してきたが、この度、50回を迎え、会員は中国の最新事情を紹介する『人民中国』を愛読し多くのことを学んできた。陳先生をお迎えして50回を記念することができ大変うれしく思います」と述べました。同行した人民中国東京支局長の于文先生も、50回の会を祝し、毛沢東の言葉を引用して継続することの重要性を称えました。山根敏郎読者会顧問も長年の「人民中国」の愛読者として親しく一行を歓迎しました。 陳先生は講演の中で、50回の記念を祝い、また先ごろの台風19号の被災者に対してお見舞いを述べた後、概略次のように話されました。 --民間交流は日中両国関係の基礎であり、「人民中国」は両国人民の友好交流と相互理解を進めることを編集の基本にしている。日ごろ皆さんから貴重な意見をお寄せいただき感謝している。 11月の北京東京フォーラムの開催に協力したが、その際両国の世論調査結果が発表された。中国では日本に対する好感度がアップしているが日本人の中国に対する好感度はアップしていない。メディアの報道の仕方や空気汚染、人口差などの要素はあるが、訪日した中国人は昨年830余万人に達し、日本に対する好感度アップに貢献している。一方日本からの訪中者は260万人と横ばいで特に若者の訪中が少ないように思う。訪中した方の感想は違ったものになってくだろうし好感度もアップすると思う。是非大勢の方に訪中していただき中国の現実に触れていただきたい。 人民中国社として雑誌の発行のほか、日本の多くの若者に中国の実情を知ってもらうためニューメディアにも力を入れている。またいろいろなイベント開催にも協力している。1つは2014年からパンダ杯中国語作文コンクール(「私と中国」)を共催している。述べ2000人の応募があり20人近い優秀者を招待しているが訪中した学生などの感想を聞くと行く前は両親が心配するケースもあったが、訪問してみて中国の食文化や案内してくれた中国人の優しさに触れ感激し良い印象を持つようになったと述べていた。もう1つは北京東京フォーラムの開催。両国の政治・経済・文化界のハイレベルの関係者が参加してかなり大きな影響を持つものとなっている。いずれも友好に貢献することを目的にしている。 「国交わり、民親しむ。民交わりてその心を知る」と言われる。隣国は選ぶことはできないし、引越しもできない。けんかしたら共に傷つき、仲良くすればウインウインの関係になる。中国は建国70周年を迎えたがこの間の変化は巨大で、日本の皆さん特に若者に今の中国を知ってほしい。アメリカは自国第一主義、保護主義で他国を犠牲にしているが、自由貿易と協力によってウインウインの関係を築くのが主流であるべきだ。日中両国は2千年の交流の歴史がある。中国と日本は運命共同体であり両国人民の心が通じ合うことにより明るい未来を展望できると確信している。読者会は50回の節目を迎え新たな始まりを迎えた。今後の一層のご活躍を期待したい。-- 歓迎交流会では、西堀正司県日中友好協会副会長が歓迎お祝いのあいさつを述べ、布施正幸県日中理事長の音頭で乾杯の後なごやかな懇談交流が行われました。「北国の春」や「草原情歌」「ふるさと」「我愛北京天安門」などが次々と披露され、陳先生も一緒に歌う場面も見られ、大きな拍手がおくられました。 |
||
| 被災地で災害ボランティアに参加、中国友人も汗流す(11/2・3) しかし、被災地の人々は日が経過していく中で、気を取り直して、家の中をかたずけ、前に進もうとしていました。ボランティアの呼びかけがおこなわれ、徐々に現地に向かう人々が増えてきました。本当にボランティアはありがたい、切なる声がテレビで紹介されていました。しかしまだ圧倒的に足りない、もっと参加してほしい、もっと応援してほしい――。 丹羽宇一郎会長の『死ぬほど読書』を読んでいたら、三国志の劉備の「悪、小なるをもって之を為すなかれ。善、小なるをもって之を為さざるなかれ」という言葉が出ていました。こだまの様に胸に残こりました。 友人の謝宏宇さん(中国国際放送局から長野孔子学堂に派遣され長野市滞在中)と被災状況について話し合った中で、やはり現地に行ってボランティア活動に参加しようということになりました。3連休の11月2日、時間が取れたので、ボランティアに参加しました。(謝さんは3日に参加。) まず柳原総合市民センター脇に設置されている長野市北部災害ボランティアセンターで受け付けを済ませます。マスクとゴーグル、(軍手)が渡されます。(長靴と昼飯と飲み物は必ず持参する必要があります。)5人ずつのグループに分けられて、その中に経験のある人がいるとリーダーに指名されます。付箋2枚に名前と携帯番号を書き入れ2枚のA4用紙にそれぞれ付箋を各自1枚ずつ張ります。一方の用紙はセンター事務局の方に提出し、1枚は各グループリーダーが持つという簡単だが合理的な方法です。4グループほどが一緒にマイクロバスに乗り込んで被災地に向かいました。我々のグループはみな長野市の方でしたが1人は豊野の勤め先の工場が被災し機械類が全滅、工場のかたずけは終わったが、現在自宅待機となっているとのことでした。 この日のボランティアは2300人、被災がひどかった地区に優先的に投入されたようで、長野市長沼津野に入りました。堤防が70mにわたって決壊した集落でした。長野市の施設である長沼公民館がボランティアセンターの津野サテライトになっていました。ここは決壊した堤防から100mほどのところにあって天井近くまで洪水が押し寄せたことがわかる建物でした。構造がしっかりしていたので鉄骨の柱と天井はしっかり残っていて、昼食時の休憩場所などにも使われていました。この建物の北側には農家の立派な入母屋造りの2階建ての建物が建っていましたが、1階は濁流に流され今は家財道具も畳も床もみんなはがされ周辺の納屋などはひん曲がって無残な姿をさらしていました。災害ごみとかき出された泥の量は半端ではありません。(写真参照) 南側には体育館があり、形はしっかり残っていますが、間にある民家は土台だけで上は姿かたちも残っていません。濁流が直接押し寄せ何件も持ち去っていったようでした。集落センター入口の近くに災害ごみの仮置き場があって雑然と積み重ねられた家電、戸棚あらゆるごみが目に飛び込んできました。(業者さんなどの車が入ってどんどん正規の集積場所に運んでいますが、次々にごみが出されて満杯状態が続いているといいます。) グループリーダーが室内に集められて、ボランティアに入る場所を指示されます。いよいよスコップなどを受け取り、現場に向かいます。入った先のYさん宅は果樹農家で2階建ての立派な構えのお宅でしたが、一階が背丈ほど浸水し土砂も流れ込んで大きな被害を受けたとのこと。すでに家財は運び出され床や土壁もはがされ、床下の泥もかき出され吹き抜け状態となっていて大分片付いているように一見見えましたが、よく見ると庭にうずたかく中から運び出された泥が積まれていました。犬走部分にも泥の山、庭の植木も泥に埋まり他所から流されてきたファンヒーターや屋根のトタンらしきもの、絡まり合った大小のごみくず、中には祭りの幟を掲げる長い柱まで、植木にのしかかっているありさまでした。15人ほどで、さっそく泥を土のう袋にスコップで詰め道路沿いのスペースに一輪車で運び出す作業に取りかかりました。慣れない手つきの人が多かったですが、みんな積極的に作業していました。中に東京から参加した若い男女がいました。スコップの疲れない扱い方を教えてやると「すごく楽です」と感謝されました。昼はサテライトに戻って、持参したおにぎりをほおばります。愛知県や鳥取県から参加した方と話ができました。大きな災害があると各地に出向き今回6度目といいます。頭が下がりますと話しました。休み時間を利用して、決壊した堤防と周辺を歩いてみました。堤防は仮修復がなされ2重構造で当面の憂いが無いような構造になっていました。堤防道路から津野の集落に入っていく標識が土手下に転がっていました。また土手下の公園の遊具が完全に水没した後をとどめていて3mほどの高さのところまでごみがまとわりついていました。付近の神社やお寺も大きな被害を受けたといいます。360度の風景を心に留め静かに深呼吸しました。 現地に入っての活動は午前10:30に始まり、午後3:00まででしたが、庭の泥搬出がようやく一段落したところでした。復旧にはかなりの時間を要すると実感しました。Yさんは70代の年配の方で、大変感謝されました。家はリフォームか建て替えか思いを巡らせているようでした。差し入れのみかんをおいしくいただきました。Yさん宅を後にしサテライトに集まり、再びマイクロバスで柳原のセンターに戻ったのは4:15頃でした。皆さん疲れてはいましたが、被災地に思いを馳せながら家路につきました。この地区はまさに泥との闘いであり、泥水に浸かった家財ごみとの闘いだと実感しました。 謝さんに連休明けに再会し話を伺うと、入った先は同じく津野で道路脇側溝の泥出し作業を行ったとのこと。これは一段と労力のいる作業です。中国の友人が慣れないスコップを手にして、汗を流してくれたことは本当に感謝の念を禁じ得ませんでした。ご苦労様でした。中国の方はよく四川大地震の際の日本の支援に感謝を述べ、東日本大震災の際には日本頑張れと様々な支援をしてくれました。日中両国の人々の友情を想起しながら友好を進めていきたいと強く思いました。 広範囲にわたる今回の災害では引き続きボランティアの支援が必要ですが、国県地元市町村、特に国による強力な財政投下による、生活の拠点の整備支援、生業の再構築支援が必要だと痛感しています。みんなで声援を送るとともに、みんなで強く要請していきたいものです。地球温暖化の中で100年に一度と言われていた自然災害は今後多発していく可能性が高いと言われています。自分たちの身近なこととして考えていきたいと思います。(F) |
||
| 満蒙開拓平和記念館のセミナー棟が完成(10/19)
新館セミナー棟は、本館西側に増築された木造平屋建て建物で、床面積が約90坪。メインは、120人規模のセミナールーム、40人規模の映像ルームなどを備え、特に本館の一番の特徴である「光の回廊」を真っ直ぐに進むと、渡り廊下で今回のセミナー棟に一直線につながる構造となっています。設計者によるとこの「光の回廊」を象徴する館は、平和を祈る聖堂として記憶に残る空間を表しているとのこと。 満蒙開拓平和記念館は、2013年4月、全国で最も多くの開拓団を送出した長野県下伊那地区に全国で唯一の「満蒙開拓」に特化した記念館として誕生しました。日中双方を含め、多くの犠牲者を出した満蒙開拓の史実を通じて、戦争の悲惨さ、平和の尊さを学び、次世代に語り継ぐと共に国内外に向けた平和発信拠点としてスタート、以来様々な平和活動、友好活動に取り組み今までに17万人余りの来館者を受け入れています。 これまで会議室スペースが狭く修学旅行など大人数の受入れに支障をきたしていましたが、セミナー棟の完成によりスムーズな受け入れ体制が整いました。 式典で挨拶に立った寺沢秀文館長は、セミナー棟建設に関わったすべての人に感謝を述べ、「セミナー棟の完成が目的ではない。当館から何を発信するか、平和の種まきのスタートと考え歴史の中から未来に向け平和発信を語りつなげて行きたい」と力強くあいさつしました。また、来賓代表として、大月良則・県健康福祉部長は「国策で長野県から多くの満州開拓団を送り出した。その歴史を語りついでいく責任がある。この記念館は日中友好交流の拠点、平和活動の拠点、新たなスタート拠点であり、平和を次の世代に語り繋げていく大きな役割を果たしていけるよう行政も協力していきたい」と述べました。最後に松川高校ボランティア部長の大平一真さんより、「満蒙開拓の歴史を私たちが後世に伝え、平和の種まき、学びを通じてメッセンジャーとして心の目を磨いて取り組んでいきたい」と誓いの言葉を述べました。長野県日中友好協会から布施正幸理事長、中澤保範事務局長が出席し、関係者の労をねぎらい今後の発展に期待を述べ激励しました。 |
||
| 台風19号、千曲川流域洪水被害に対するお見舞い(10/18) 今回の台風19号は、東北信地方の広い範囲で大量の雨をもたらし、県内アメダスの観測点で13日までの48時間の最大雨量は、南佐久郡北相木村で411.5ミリと観測史上最多を記録、上田市、佐久市、軽井沢町、高山村の観測地では、300ミリを超え、、軽井沢町を除き雨量は観測史上最多を更新し大きな被害につながったと見られています。 犠牲になられた方に哀悼の意を表しますとともに被災された方に心からお見舞い申し上げます。日中友好協会会員の中にも被災された方がおられ、また親戚、知人の皆様の中にも被災された方がおられると聞いております。心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早く平常な生活に戻られますよう願っております 長野県の被災の状況は中国でも詳しく報ぜられており、中国の友人からも次々とお見舞いのメッセージをいただいております。河北省外事弁公室、中日友好協会、中国国際放送局、「人民中国」雑誌社、中国大使館、吉林省、日中友好会館後楽寮留学生など友人の皆さんのあたたかい励ましに感謝いたします。 2019年10月18日 長野県日中友好協会 会長 高波謙二 役 職 員 一 同 |
||
| 中華人民共和国建国70周年講演と祝賀のつどい、宮本元大使大いに語る(10/10) 高波謙二・県日中友好協会会長が主催者を代表して、「本年、中華人民共和国建国70周年を迎えた。中国は急速な変化と発展を遂げ、国際社会における比重を高めており、日中の貿易額も対米貿易を大きく引き離して、往復33兆円を記録した。日中関係は21世紀に入って歴史認識問題、尖閣問題によって困難な状況が続いてきたが、昨年の両国首脳の相互訪問、首脳会談によって好転し、正常な軌道に戻った。このチャンスを活かし、長期的視点で安定した日中関係を築いていきたい。宮本雄二先生を講師に迎え、平和で安定した日中関係を築くためにはどうしたらよいかをともに考えたい」とあいさつしました。 宮本先生は冒頭、長野県が(開拓団送出日本一の)歴史を踏まえ中国との関係を大切にし草の根から友好関係が出来上がってきたことにかねがね敬意を抱いてきたと述べ、大使在任中に方正の日本人公募を参拝したこと等も紹介したうえで、これから中国とどう付き合うかについてわかりやすく、深い洞察に富むお話をしていただきました。(概略下記参照) ――将来の日中関係を考える上で、なぜ日本が中国侵略に始まる対米戦争という過ちを犯したのか総括する必要がある。かつて日本は中国のナショナリズムを過少評価し、対中侵略を進め更に全く展望のない対米戦争まで突き進んでしまった。第1次世界大戦後の平和構築に向けた世界の大きな流れを見ることに失敗した。これから中国とどう付き合うかを考える上で、このことをしっかり押さえておく必要がある。 中国の発展は目覚ましくGDPで今や日本の約3倍規模になっておりやがて米国を追い抜くだろうが、中国がダントツの1位になることはないだろう。世界は多極化の時代に入っており、中国は経済では自由貿易を、国際政治では常任理事国として国連憲章に基づく国際的なルールを支持している。その点で、大きな方向で中国と日本は一致している。そこを突破口に政治、経済の国際的枠組みを日中がともに支え、強化することを全面的に打ち出すべきだ。中国は変わり続けており、中国共産党の統治力や変わる力に注目すべきだ。今までこうだったという固定観念は捨てたほうが良い。日中は共通の言葉を持つに到った。 日中関係を考える上で、中国人の対日観が急速に変わってきている。訪日観光客の増加やスマホなどを通じて日本に対する好感度がアップしてきている。両国の歴史認識問題については以前は大きな障害だったが世代交代が進み脇における時代になった。閣僚らによる靖国参拝など日本がきっかけを作らなければ問題は起こらないと思う。過去の歴史より、改革開放の実績と今後の中国の発展を自信をもって進んでいける状況が生まれ、対日観も客観性を持つようになった。 米中関係が激化している。アメリカは自分に追いつき追い越そうとする国が出現するのは面白くない。かつてソ連、次に日本がバッシングの対象になった。経済、軍事・安全保障面で、アメリカは中国の台頭を押さえつけようとしている。軍事・安全保障面では軍人は最悪を想定して相手を過大評価し軍拡→戦争と進んでいってしまう傾向がある。中国人は考えている最中だが、冷静に考えれば中国を攻める国はない。軍事力に頼ることなく、自由貿易、国連強化などソフトパワーをもって、安全と尊厳を守ることが賢明であることは言うまでもない。日本は米中を衝突させない役割があり、貢献できるのではないか。 日中関係は国民の信頼関係が低下していると言われるが、一番関係が悪化したときでも10%すなわち1200万人の日本人が中国が好きとの世論調査結果だった。国民同士の交流を通じて等身大の中国を理解することによって両国関係は安定する。号令一下右向け右という中国人はいない。中国人は「義」の価値観が一番強いように思う。中国人は道理が無ければ従わない。留学生に温かく接し、日中関係を大切にしたい。今後の日中関係を考えるとき、一番心配なのは日本の若い世代が中国との関係にあまり関心を持っていないこと。日本にとって中国の重要性は年々増している。中国とどう付き合うか、自分たちの問題として考えてほしい。―― 講演後、宮本先生を囲んで濱田州博信州大学学長をパネラーに、西堀正司・県日中理事長がコーディネーター役をつとめ、パネルディスカッションが行われました。参加者は熱心に耳を傾けました。 第2部の祝賀パーティーでは、高波県日中会長、濱田県日中学術交流委員会会長のあいさつに続き、花岡徹県国際担当部長、太田昌孝(代)・井出庸生(代)衆議院議員、小松裕(県卓球連盟会長)・若林健太前国会議員の祝辞の後、犛山典生県経営者協会事務局長の音頭で乾杯しなごやかに懇談交流しました。また高橋要長野市商工観光部長、大月良則県健康福祉部長、、樋代章平八十二銀行常務執行役員、根橋幸夫県国際課長、岡村重信県プロフェッショナル人材戦略拠点事務局長、埋橋茂人県議(代)、李妮県国際交流員、娜日蘇長野市国際交流員、石家庄市研修員の魏薇・王瑶さんらからも祝辞をいただきました。また長野ラジオ孔子学堂のフルス教室のメンバーが日ごろの練習成果を発表し、研修生や女性会員らが「北国の春」や「ふるさと」などを披露し拍手を浴びました。王昌勝県華僑総会会長が締めのあいさつを行い、盛り上がりの中懇親会が終了しました。 |
2015年1~12月
2014年1~12月
2013年1~12月
2012年1~12月
2011年1~12月
2010年1~12月
2009年1~12月