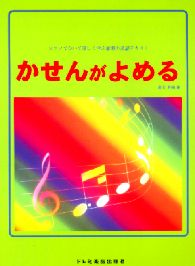 |
やさしいものから難しいものへ、段階を追って無理なく勉強できる | |
| たくさんの課題を集中的に徹底的に学習できる | ||
| 「メロディーを歌う、ピアノで弾く」という具体的な音楽活動を通して、加線の音を実践的に学ぶ | ||
| 簡単にひけるように書かれているので、加線の学習に専念できる | ||
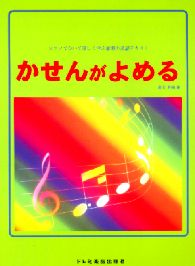 |
やさしいものから難しいものへ、段階を追って無理なく勉強できる | |
| たくさんの課題を集中的に徹底的に学習できる | ||
| 「メロディーを歌う、ピアノで弾く」という具体的な音楽活動を通して、加線の音を実践的に学ぶ | ||
| 簡単にひけるように書かれているので、加線の学習に専念できる | ||
同じ形の音符でも、加線の位置によって読み方が違う加線は、覚えることのとても難しい音符ですね。しかし、どのピアノテキストも、こと加線の指導のプログラムに関しては、体系的に分かりやすく学習できるようには、残念ながらなっていません。新しい現代のテキストでさえ、加線が出たところでの思いつきのような指導プログラムになっているものもあります。
「ピアノテキストの加線学習プログラムの研究」参照
また、実際の学習曲の中には、肝心の加線の音が多く使われていません。そのため、実践的な加線の読譜練習の機会が乏しいといったこともあります。これでは、それでなくても難しい加線の音符が、なかなか読めるようにならないのは無理もありませんね。
熱心な先生の中には、読譜の力をつけるために、ピアノテキストとは別にソルフェージュのテキストを使っている先生もいると思います。しかし、これらのテキストもかなり上級のテキストを含めて、五線の範囲内の音を主に扱っていて、加線の音はあまり出てきません。特にへ音譜表の下の加線となると、これを十分に扱っているテキストは、全くといってよいほどありません。
このような事情を考えると、加線の譜読みが体系的に分かりやすく学習できる「かせんがよめる」は、生徒たちが一番苦手にしている加線の読譜力をつけるために、大いに役に立つことと思います。
| 「かせんがよめる」の構成と学習内容 |
第1部
- 新しく習う加線の音が、それまでに勉強してきた音の延長上に並んだ音として導入されます。それにより、新しい加線の音が導入されるときは、それまでに自分が習って知っている音から推測して、それらの音が何の音であるかを、自分で考えて書き入れるようになっています。生徒が迷っているときは、先生はその推測を助ける助言をして、生徒自身にその音が何であるか、発見させるようにしましょう。
第1部のサンプル楽譜
第2部
- 加線の音を個々に取り上げます。短いメロディーを読んだり、歌ったり、弾いたりして、新しい加線の音に慣れます。書く練習もして、しっかり覚えるようにします。 第1部と同様に、新しく習う個々の加線の音は、生徒自身がそれまでに習った音から類推して探せるよう、既習の音から順次進行して出てくるようになっています。生徒自身に自分の力で発見していくように、上手に指導しましょう。
第2部のサンプル楽譜
第3部
- 加線の音を含んだ8小節の短い曲をたくさん読んで弾く、実践的な勉強の場です。ピアノの上で弾くように書かれていますが、このテキストは加線の勉強のためのテキストですので、弾くことの難しさを極力なくしてあります。そのためにすべての曲は、原則として次のような制限のもとに書かれています。
●5指ポジション上で片手奏/フレーズの呼応
すべての曲は、5本の指を置いたままの位置で弾けるように書かれています。また、片手だけで弾くように書かれていますが、右手左手と交互に片手で弾かれるメロディーが、フレーズの呼応を感じて弾けるようになっています。これにより、譜読みも、ピアノで弾くことも、フレーズのまとまりを感じ取ることも、たいへんに分かりやすくなっています。(数曲の両手奏あり)
●加線のポジションの譜読みから、五線内のポジションの譜読みへ
原則として、最初のフレーズが加線の位置のメロディーを扱うと、それに続くフレーズは、五線の中の位置のメロディーを弾きます。それにより、生徒は加線の位置の譜読みから、別のポジションの譜読みに頭を切り替えられて、再び加線の位置の譜読みをすることになります。このようにして、加線を読む実践的な力を養っていきます。
●「ドは1の指」といった固定的な指使いは避ける
一般に教則本の多くは、例えば「ドは1の指」でひくというポジションが、かなり長期にわたって維持されます。そのため、譜読みをしなくても指使いを見れば音が分かってしまい、実際には譜読みの力があまり育っていなかったということがよくあります。「かせんがよめる」では、そのような指使いを使わなくてもすむところでは、意図的にそのような固定的な指使いを避けています。
また、次のような工夫をして、学習に気分転換の楽しみを入れました。
●力試しに有名な曲の楽譜を読んでみる
それぞれの加線の学習曲の合間に、いくつかのよく知られた曲を入れました。力試しに、有名な曲の譜読みを楽しみましょう。
第3部第1頁のサンプル楽譜
第3部第6頁のサンプル楽譜
[ホームページ][エッセイ集][ピアノテキスト研究][夏目先生の指導の提言][コース案内]
Copyright(c) 1998 Yoshinori Natsume, All rights reserved.