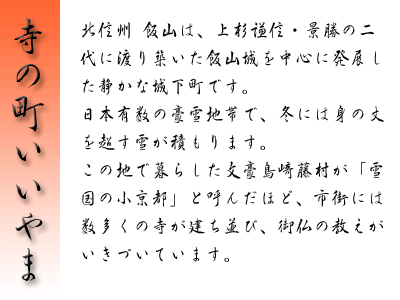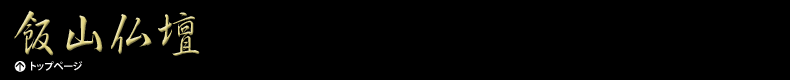

▲飯山城主本多氏菩提寺 忠恩寺
飯山市は、長野盆地の北端、千曲川に沿い、すぐ隣は越後の国新潟県である。天正7年(1579)上杉謙信が築城し、江戸時代は本多氏の城下町として、千曲川舟便の起点であり、物資の集散地として栄えた街でありました。
島崎藤村の代表作の冒頭の一節に「さすが信州第一の仏教の地、古代を眼前に見るような小都会、奇異な北国風の屋造、板葺の屋根、または冬期の雪除けとして使用する特別の軒庇から、ところどころに高く顕われた寺院の樹木の梢まで一すべて旧めかしい町の光景が香の烟の中に包まれて見える。」とあります。

▲長野県スキーの父市川逹譲氏ゆかりの 妙専寺
この地にいつ頃から、仏壇作りが始められたのか定かな記録はありません。ただ室町時代から浄土真宗が北陸から伝播し、飯山を中心とする北信地方に広く根を降ろしていった事実が、仏壇作りの素地としての地域性をもたらしていたことは確かであります。
一般に地元では元禄2年(1689)甲府から寺瀬重高なるものがきて、素地仏壇を手がけたのが始まりだといわれています。塗仏壇が用いられるようになったのは、それからずっと遅れて越後潟町から来た鞘師屋佐七なる者によるというのが真実のようであります。
幕末の頃、稲葉喜作が出て、彼は仏壇彫刻の名手でありましたが、この稲葉家の祖先で彦次郎清久、彦佐吉弘らが京都に住み、或いは仏門に帰依し、仁兵衛に至って飯山に定住したということは、飯山仏壇が京都の流れをくむものであり、喜作の頃からその声価を高め製作方法も分化したものと思われます。

▲稲葉喜作 作 お仏壇
発展の要因
飯山の地で仏壇作りが盛んになったことには次のような要因が挙げられます。
- 仏教信仰の厚い場所である。
- 城下町政策および寺社政策。
- 仏壇原材料(木材など)が地元にあった。
- 漆塗りに最適な清澄な空気と適度な湿気をもつ気象条件と豪雪および立地条件による産業の特殊性。