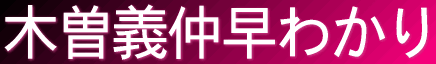|
|||||||||||||||
 徳音寺所蔵 |
日義の里に兵を挙げ,平家追討の令旨(れいし):天皇の命令文書)を大義名分にして只ひたすら戦い抜き,若くして31年の生涯を駆け抜けた。乱世の改革の為に奮い立ち後世にも残る傑出した傭兵をもって,朝日の昇るごとに眩しく輝いた。 木曽義仲は,大将軍(官軍の長)としてあくまでも反乱を鎮圧すべく果敢に駒を進めて熱き炎を燃焼し尽くしていった。ふる里の美しい山や川と共に,我ら唯一の誉れ高い武将である。 里人は,華々しくも儚く散った朝日将軍木曽義仲公を偲び,旗挙げの地やゆかりの史跡を中心に,纏わる物語を大切に伝承し,,遠く800余年を経た今日もなお,公の功績を愛おしみその歴史を今に伝承している。 朝日将軍木曽義仲公は,歴史上にも燦然(さんぜん)と輝く数少ない征夷大将軍(せいいたいしょうぐん)の一人である。 |
 ささりんどう紋章 |
|||||||||||||
| お知りになりたいこと | ご 説 明 | 出典の分類 | |||||||||||||
木曽義仲の 生い立ちは 生まれは 母者は 父者は 名前は |
生まれは 久寿元年(1154) 武蔵国(埼玉県)比企(ひき)郡嵐山(らんざん)町鎌形郷 (かまがたごう)が通説。 大藏,また上野の国多胡とも。 父の名は 源義賢(みなもとのよしかた) 前帯刀先生(さきのたてわきせんじょう:朝廷を護武官の長) 母の名は 小枝御前(さえごぜん) 幼名は 駒王丸(こまおうまる)といわれた。 |
図書文献 平家物語 源平盛衰記 岐蘇古今沿革誌 縁の地物語 嵐山町 |
|||||||||||||
| 木曽義仲は なぜ木曽へ |
父が,甥源義平(義朝の長男ー悪源太とも言われた)に大蔵館を急襲され,憤死の憂き目にあったため, 久寿2年駒王丸2歳(吾妻鏡3歳)の時,母小枝御前と共に木曽土豪中原兼遠(中三権守:国司の長官)の元へ逃れた。 中三は:宮中三殿,権守(頭)(ごんのかみ) 駒王丸が生き存えるのは,武将畠山重能(はたけやましげよし),斉藤別当実盛(さいとうべっとうさねもり)の温情によるものであった。真盛がしばらく匿い,木曾へ逃した。 遠く追っ手の届かない木曽山中に,乳母が中原兼遠の妻になっていたのが幸いだった。 |
図書文献 平家物語 吾妻鏡 |
|||||||||||||
| 中原兼遠の 館は何処 |
長野県木曽郡木曽福島町この尻 断崖急峻な山間の地形の中にある。その高台に珍しく開けた平坦地があり,一方向は高い山脈,三方は大川に護られ自然の要塞で難攻不略の館である。 この地に文武両道に励んだ縁(ゆかり)の天神様がある。日義の里に隣接した史跡。 |
縁の地史跡名勝 手習い天神 |
|||||||||||||
木曽義仲は 何をしたのか |
「平家を滅ぼすは平家」 時の為政者の「平清盛」による”六波羅政権”は権勢を誇った。 そのために,平家による勝手気ままな振る舞いが横行して,世の中に暗い影を落としていた。 時代を先取し乱れた世の中の改革を目指して立ち上がり,時の権勢に敢然と立ち向かった。新しい世の中の創造に勇気ある先鞭をきった行動は,現世にも相通じ範たるものがある。 これこそ正に時代を超越した英雄ではある。 |
図書文献 玉葉 平家物語 源平盛衰記 岐蘇古今沿革誌 |
|||||||||||||
旗挙げと合戦 |
治承4年(1180)長野県木曽郡日義の里宮の原で旗挙げ 上野の国へ進出したが源頼朝軍との衝突を避け一端帰還 ・・・佐久の依田(よだ)城に攻め上り軍勢立て直し・・・義和元年(1181)上野国(上野の国)横田原の戦い・・・越後直江津城長茂を破る・・・般若野(はんにゃの)の戦・・・倶利伽羅峠の戦 ・・・篠原の戦・・・燧ヶ城の戦・・・京都入京・・・水島の戦 京都凱旋後頼朝と不和 ・・・元暦元年(1184)鎌倉軍勢の源範朝,源義経に追われ,連勝を誇った木曽義仲軍も遂に命脈がつき,近江の国粟津ヶ原(あわづがはら)の戦いに敗れ討ち死。 享年31歳。 |
図書文献 平家物語, 源平盛衰記等 |
|||||||||||||
女性たち |
巴御前(ともえごぜん)・・・中原兼遠の子。兼光・兼平の妹で木曽義仲の乳母子 木曽義仲と最後まで一緒に戦った。美人にして男勝りの力持ち。 伊子(いし)・・・木曽義仲の妻 才色兼備の類い稀な美人と謳われた。関白藤原基房(ふじ はらのもとふさ)の娘。 山吹姫(やまぶきひめ)・・・木曽義仲に従い上洛した女武者。上野の 国沼田太郎家国の娘。姫が創建した班渓寺(はんけいじ) 武蔵国(埼玉県) 比企(ひき)郡 嵐山(らんざん)町 鎌形郷(かまがたごう)に義仲をともらった。 |
図書文献 平家物語 |
|||||||||||||
| 兄弟や子供は |
兄弟・・・兄は,仲家 妹は宮菊。 子供・・・長男義高(巴),二男義重, 三男義基(巴),四男義宗(山吹), 長女鞠子かくし(伊子) |
図書文献 吾妻鏡,玉葉 岐蘇古今沿革誌 |
|||||||||||||
| (ぎちゅうじ) | (ぎちゅうじ) 大津市馬場 国指定史跡 近江の国粟津ヶ原(あわづがはら)の戦いに敗れ討ち死。 享年31歳の木曾義仲の霊を弔らった。境内には,寳篋 印塔(ほうきょういんとう)の墓と,義仲をこよなく愛した芭 蕉ガ眠っている。 |
史跡ゆかりの地 |
|||||||||||||
| (ひよし) | 木曾義仲のふる里はこの地。 戦勝祈願の「南宮神社」,宮の原に旗挙げの「旗挙八幡宮」ゆかりの史蹟やまつわる景勝地「巴淵」,「山吹山」などがたくさん所在。 木曾義仲が,母小枝御前を弔うために建立した「徳音寺(柏原寺)」には,義仲と巴の他樋口兼光,今井兼平など一族ガ眠っている。徳音寺境内には「資料館」もある。養育の父兼遠の菩提「林昌寺」,築城の際の水源「岩華観音(いわはなかんのん)」,屋敷の原の「根井行親の屋敷跡」,【御魂の森(みたまのもり)「樋口次郎兼光の屋敷跡」】, 「御霊(おたま)の森」(手塚太郎の陣屋跡)等数多。 |
史跡ゆかりの地 |
|||||||||||||
| ) |
中原兼遠の子(四男),巴御前の兄で木曽義仲四天王の一人。 幼少の頃から義仲と共に,兄弟同然の養育をうけた。挙兵から最期まで常に義仲に従い,最後まで各地を転戦した勇猛な武将。 粟津ヶ原で木曽義仲と共に討ち死。 |
図書文献 平家物語, 源平盛衰記 |
|||||||||||||
  |
|||||||||||||||