

長野市中御所岡田町166-1
TEL026-224-6517
 トップページはこちら
トップページはこちら長野県日中友好協会のホームページへようこそ
 第29期第3回日中関係を考える連続市民講座が1月24日、日中友好センター教室において開かれ、長野県立大学講師の王孫涵之先生が「佚存書(いつぞんしょ)とは何なにか—新たに発見された『論語義疏(ぎそ)』をめぐって」」と題して講演しました。20人が出席し熱心に聴講しました。
第29期第3回日中関係を考える連続市民講座が1月24日、日中友好センター教室において開かれ、長野県立大学講師の王孫涵之先生が「佚存書(いつぞんしょ)とは何なにか—新たに発見された『論語義疏(ぎそ)』をめぐって」」と題して講演しました。20人が出席し熱心に聴講しました。
きわめて専門的なお話でしたが、日中間の文化交流の時代背景に触れながらのお話で興味深く聞くことができました。講義内容は1.佚存書とは何か、2.『論語義疏』という注釈書について、3.新発見の「論語義疏」についてでした。(以下概略を紹介します。)
1.佚存書とは何か
◇佚存書とは、中国ではなくなったが、日本に伝来した漢籍で保管されている書をさす。その呼称は林羅山の子孫、林述齋が編纂した『佚存叢書』に由来する。彼は「かの国に亡くなった書籍は少なくない。わが国だけに伝存している漢籍については万が一滅びてしまえば天地の間から永遠に消えてしまう。これは誠に残念なことだ」と記している。
◇中国本土でなくなったのに、なぜ日本では伝存しているのか?
陳舜臣氏:中国人はカタログマニア、日本人は保存の天才。
井上進氏:中国での内乱、科挙制度で個別の家系は永続せず蔵書の長期の伝承は困難。
王孫私見:上記の原因のほか、日本では公家や仏教の蔵書として伝承、中国では書籍の淘汰や写本から印刷本への転換で伝承されないケースが多かった。
◇佚存書をめぐる日中の交流
①『論語義疏』の逆輸入:1764年根本遜志が校定した『論語義疏』が刊行→1774年(乾隆40)王亶望、のちに鮑廷博翻刻、刊行。乾隆49年には『四庫全書』に収録して書写。乾隆52年には内府の武英殿で刊行。
②近代の交流:楊守敬1880年来日、佚存書を収取して『古逸叢書』を刊行、帰国後『日本訪書志』出版。但し、『論語義疏』は未収録。
渋江抽斎・森立志:明治期の日本は漢学の人気がなく清国の援助で1885年上海で『経籍訪古志』(日本に伝存した漢籍の古写本・古版本の書誌情報を記した本)を出版。
③現代の動向:中国政府は伝統文化を重視し、古典籍の出版や研究に助成。教育部配下に「全国高等院校古籍整理研究工作委員会」(1981年~)を設置。中国社会では伝統文化ブームで民間の蔵書家が増えている。漢籍を求めて来日する中国人も多く、中には日本で漢籍の古本屋を経営する者も現れている。オークションで出品されたものの中には5千万円を超えるものもある。(日本の文化財の流失ともいえる。)
2.『論語義疏』という注釈書について
◇『論語義疏』の構成は、⓵経(『論語』の本文=孔子の言行録)、②注(魏の何晏による『論語集解』)、③疏(南朝梁の皇侃による『論語義疏』)よりなる。疏は経だけでなく注に対しても詳細な解説を行う。
◇『論語義疏』の性格は、⓵経典を知識の対象として扱い、その妥当性を持つか論証する。②道家や仏教の概念を用いて、『論語』を説明する。③『論語義疏』は北宋の景徳元年まで最も読まれた論語の注釈書であった。したがって、日本や敦煌にも伝わった。その後、邢昺(けい
へい)の『論語正義』に取って代わられた。宋の真宗の勅令を受け『五経正義』を基準として道家や仏教の説を削除し、皇侃の『論語義疏』に対して大幅な修訂を行った。『論語正義』は国定であったので『論語義疏』は勢力を失い、南宋ごろには中国本土ではなくなった。
◇7世紀後半に日本に伝来し、現代まで伝承した。伝来後まず大学寮(国の最高教育機関)で講義され平安時代以降は清原家などの世襲貴族の中で家の学問として伝承された。室町時代では足利学校の禅僧たちも『論語義疏』を用いて『論語』を学習していた。『論語義疏』が日本に根付いていたため、『論語正義』が伝来してもその地位は揺るがず、現代まで伝承され続けた。
3.新発見の『論語義疏』について
◇発見から公開までの経緯:2016年3月、都内の古書店が『論語義疏』の古写本を入手したものを、慶應義塾大学図書館が購入、研究チームで研究、20年公開、21年11月出版。
◇書写の年代について:北朝の異体字を用いていることから、隋もしくはそれ以前の写本であることがわかり、皇侃(488~545)の生卒年と南朝から北朝に伝わる時間を考慮すると6世紀後半から7世紀前半の写本と思われる。
◇発見の意義:①文献学上、『義疏』の最古の写本であるとともに、『集解』の最古写本であり、『論語』の最古写本といえる。今回の発見によって『論語義疏』の本来の姿が明らかとなった。②学術史上、中国で南北朝隋唐期、『論語義疏』が成立した後、早く北方地域に伝わって受容されたことが分かった。日本への伝来については、従来南朝から百済経由で伝わったと言われてきたが、今回の発見によって、中国の長安・洛陽などの北方地域を訪ねた遣隋使・遣唐使が直接日本にもたらした可能性が高いと推測される。(但し、隋から百済経由で日本医伝わった可能性もある。)
 第29期第2日中関係を考える連続市民講座が12月20日、日中友好センター教室において開かれ、中国伝媒大学教授で長野ラジオ孔子学堂中国側代表の夏丹先生が「人工知能の新時代:AIはどのように教育を再構築するのかー中国の探索・実践・思考」と題して講演しました。講座には20人が出席し熱心に聴講しました。
第29期第2日中関係を考える連続市民講座が12月20日、日中友好センター教室において開かれ、中国伝媒大学教授で長野ラジオ孔子学堂中国側代表の夏丹先生が「人工知能の新時代:AIはどのように教育を再構築するのかー中国の探索・実践・思考」と題して講演しました。講座には20人が出席し熱心に聴講しました。
夏先生は、はじめに、2022年にOpenAIがChatGTPを発表して以来、人工知能技術は急速に発展し、仕事や生活を急速に変え始めていて、教育分野も例外ではない。AIは教育に何をもたらすのか?人々はAIに大きな期待を寄せる一方、大きな不安を抱いていると述べ、次の5項目について報告しました。
(1)AIの中国における興起と発展、(2)AIはどのように中国教育を全面的に支援しているか①基礎教育②高等教育③中国メディア大学の実践、(3)AI教育が直面する道徳的リスクと対応、(4)政府の政策と未来展望、(5)AI教育と日中協力
参考になると思われるので以下紹介したいと思います。
☆こちらをクリック→AIはどのように教育を再構築するのか
 第29期日中関係を考える連続市民講座が11月29日スタートしました。県内の大学や県日中友好協会などで作る県日中学術交流委員会主催で、毎月1回のペースで文化、歴史、経済関係などをテーマに明年3月まで、計5回の講座が開かれます。第1回は長野大学の塚瀬進教授が、「近年の中国留学生の動向―長野大学の事例を中心に」と題して講演しました。20名の受講者は熱心に聞き入りました。
第29期日中関係を考える連続市民講座が11月29日スタートしました。県内の大学や県日中友好協会などで作る県日中学術交流委員会主催で、毎月1回のペースで文化、歴史、経済関係などをテーマに明年3月まで、計5回の講座が開かれます。第1回は長野大学の塚瀬進教授が、「近年の中国留学生の動向―長野大学の事例を中心に」と題して講演しました。20名の受講者は熱心に聞き入りました。
塚瀬先生は、長野大学に在籍し、中国近現代史が専門ですが、長野大学での留学生受け入れに長年携わってきた立場から今回中国人留学生の動向についてお話しいただきました。
中国人留学生は1980年代後半以降に増加し、現在ではどの大学にも在籍することが普通になっています。中国人留学生の受け入れの変化について歴史学的考察を加えた興味深いお話でした。
◎以下講演概要です―――
① 中国人留学生の受け入れ開始:1979年に48名の国費留学生が来日。1983年には中曽根首相21世紀初頭までに10万人の外国人留学生受け入れ計画を発表。1984年中国政府は「自費留学に関する暫定規定」を発表し、自費留学の制限を緩和。日本、中国とも留学生を増やす政策を推進した。1980年代後半に入ると、日本語学校に在籍する中国人留学生の「就学ビザで不法就労」問題が浮上。日本政府は法制面・制度面の整備を進める
② 入管法の改正、留学生受け入れ制度の整備(1990年代):1990年「改正出入国管理法及び難民認定法」施工。在留資格が再編成され、新入管法の原型ができる。目的は外国人労働者の受け入れ拡大にあった。日系人の入国が容易になり、日本語学校に入学する日系外国人が増える。日本語学校の抱える問題の顕在化と対策の強化。1998年留学生の就労は1週間に28時間以内とすることが入管法施行規則で明文化される。(長期休みは1日8時間以内かつ週40時間以内)
③ 大学の状況変化と中国人留学生の状況:1992年~2006年の間に大学が184校増加、各大学による入学者の獲得競争が激化。01年酒田短期大学問題が注目を集める。(授業に出ずに東京で就労、定員100名のところ在校生は352名うち中国人339名)→定員割れを中国人留学生で補填する大学の状況が明らかになる。03年入管当局は中国人の就学生・留学生の入国を厳格化。萩国際大学問題起こる。07年以降、東和大学、三重中京大学、聖トマス大学、神戸ファッション造形大学、愛知新城大谷大学、創造学園大学など9大学が学生募集を停止。08年留学生「30万人計画」発表。インドネシア人看護師・介護福祉士候補者の受け入れ開始
④ 09年「出入国管理及び難民認定法」改正法公布。→在留資格の「就学」が廃止され、「留学」に1本化。在留外国人を一元的に入国管理局が管理する在留カード制度の導入。25年「不法就労助長罪」の罰則が強化され、雇用者には5年以下の禁固刑または500万円以下の罰金が科せられる。(以前はそれぞれ3年、300万円)
⑤ 長野大学の状況:
(1)2000年受験者数1000人を割る。01年受験者減少に対応するため中国人留学生の募集に力を入れる。06年定員400名に対して379名で定員割れになる。13年まで定員割れは続く。14年「長野大学の公立大学法人化に関する要望書」を上田市に提出。→入学者は定員を上回る。17年公立大学法人となり、以後受験者は定員を上回り、現在、競争率3倍という状況となっている。
(2)長野大学の中国人留学生の状況:02年45名(うち内モンゴルから20名)以後協定校を増やし、10年には最多の165名になる。17年以降、中国人留学生数は減少。15年55名、17年26名、25年16名。長野大学の総定員は1400名なので中国人留学生の割合は1.1%。
⑥中国の変化:
(1)中国経済の成長により、海外留学をめぐる状況は大きく変化。塚瀬教授が留学していたころ1990年代前半と比べて日本円の価値は4割減少。→日本で働いてもあまりもうからない。
(2)中国人留学生の変化→18年ごろから留学費用のすべてを両親が負担しアルバイトをしない留学生が表れ始める。日本の大学・大学院に進学を希望する中国人が増えている。(東大、早稲田大学など人気)
⑦終わりに
中国経済の成長に対して、日本経済は低迷しており、両国の格差は縮小した。日本の大学による中国人留学生の受け入れは新たなステージに立っている。各大学がどのような留学生教育を行い、いかなる分野・場所に送り出すのか、改めて大学の姿勢が問われている。

 長野県日中友好協会・県日中経済交流促進協議会・県日中学術交流委員会は10月7日、戦後80年・日中友好協会創立75周年を記念して講演と祝賀のつどいを長野市内のホテル犀北館で開きました。講演会には、約110名が出席。「現代ビジネス」編集次長で元講談社北京副社長の近藤大介氏を講師に迎え「現代中国事情と日中関係の今後」と題して記念講演が行われました。終了後、先生と西堀正司県日中会長の対談がおこなわれました。中国留学や中国駐在経験を持ち、「現代ビジネス」のコラムニストとして日々最先端の中国事情を追跡、論陣を張っている先生ならではのお話で、直前の自民党総裁選の結果を踏まえての新政権下の日中関係の注目点、中国経済の現状、4期目を目指す習近平体制、トランプ関税と戦う中国外交などをわかりやすい資料を基に解説いただき、今後の日中関係の在り方を考える大変良い機会となりました。
長野県日中友好協会・県日中経済交流促進協議会・県日中学術交流委員会は10月7日、戦後80年・日中友好協会創立75周年を記念して講演と祝賀のつどいを長野市内のホテル犀北館で開きました。講演会には、約110名が出席。「現代ビジネス」編集次長で元講談社北京副社長の近藤大介氏を講師に迎え「現代中国事情と日中関係の今後」と題して記念講演が行われました。終了後、先生と西堀正司県日中会長の対談がおこなわれました。中国留学や中国駐在経験を持ち、「現代ビジネス」のコラムニストとして日々最先端の中国事情を追跡、論陣を張っている先生ならではのお話で、直前の自民党総裁選の結果を踏まえての新政権下の日中関係の注目点、中国経済の現状、4期目を目指す習近平体制、トランプ関税と戦う中国外交などをわかりやすい資料を基に解説いただき、今後の日中関係の在り方を考える大変良い機会となりました。第1部の司会を大月良則・県日中友好協会理事長が務め、徳武高久・県商工会議所連合会専務理事の開会あいさつに続いて、西堀正司・県日中友好協会会長が主催者を代表して、「本年、戦後80年・日中友好協会全国本部創立75周年を迎えた。日本は新政権が誕生することになる。日中関係は様々な困難や課題に直面している。激動する世界にあって、日本も、中国も、米国も不確かな状況にある。友好協会は創立時の原点を踏まえ、官民協力して日中不再戦、友好協力を粘り強く進めていきたい。近藤先生を講師に迎え、中国の現状に対する理解を深め、平和で安定した日中関係を築くためにはどうしたらよいかをともに考えたい」とあいさつしました。布施正幸・県日中副会長が講師の近藤先生を紹介し、講演に入りました。
◇近藤大介先生の講演「現代中国事情と日中関係の今後」
近藤先生は冒頭、長野県が戦前開拓団を送り出し悲惨な逃避行で多くの犠牲を出した歴史を踏まえ中国との関係を大切にし地方民間交流に力をいれ全国の模範的な交流活動を進めてきたことに敬意を表したいと述べ、激動する国際情勢の中で、新政権下の日中関係、中国の経済、政治、外交について興味深いお話をしていただきました。(概略下記参照)
<はじめに>
長野県日中友好協会の活躍に敬意を表したい。インバウンドで中国人観光客は国慶節連休で大勢来日している。コロナ明けの海外旅行は日本が一番人気という。10年前は爆買いが注目されたが、今は体験の時代で趣が変わってきている。今や中国はAIなど世界の先端分野で活躍しており、キャッシュレス社会、厳しい競争社会。中国人にとって日本は20世紀が体験できる歴史的文物が残っていて自然も豊かな国であり、心を洗う癒される旅が体験できる国として人気がある。
<新政権下の日中関係>
10月4日の自民党総裁選で高市早苗候補が勝利した。日本の新政権に対して、中国はどう向き合うのか?石破政権の時のように日中関係は健全に進んでいくのか?中国は「靖国参拝首相」が誕生すること、特に最も右派の高市氏を危惧していた。在任中の首相・外相・官房長官の不参拝を確約させようとするだろう。いずれにしても「親台派」の高市政権下では、当面「政冷経冷」となることは避けられない。台湾の頼政権は「熱烈歓迎」している。
丸3年に及んだゼロコロナ政策や「総体国家安全観」(政権保持優先政策)を優先させたことなどで経済が悪化。不動産バブルが崩壊し、地方自治体が疲弊した。政府は「V字回復」に全力を挙げているが、苦戦が続いている。
鄧小平・江沢民・胡錦涛時代の高度成長が鈍化した中で、習近平体制の主な経済政策と影響を受けた層を見ていきたい。①2012年~贅沢禁止令→幹部・富裕層に悪影響、②15年~証券市場引き締め、人民元切り下げ→株主・投資家・輸入業者に影響、③16年~供給側構造改革→大企業、④18年~米中貿易摩擦→貿易業者、不動産引き締め→不動産業者・金融機関・中間層、⑤21年~共同富裕→富裕層・大手IT企業、⑥20~22年ゼロコロナ政策→全国民、⑦23年~総体国家安全観→全国民、⑧25年米中貿易戦争→全国民。
中国主要経済統計(25年10月5日現在)上半期GDPは対前年同期比5.3%、8月の大企業工業増加値+5.2%、1~8月大企業利潤+0.9%、8月の小売総額+3.4%、全国固定投資+0.5%、1~8月貿易総額+2.5%、日中貿易総額+4.2%、8月の全国住民消費価格-0.4%、若年層失業率は14.5~16.9%、7月は17.8%、上半期の外資系企業の投資金額は-15.2%、上海総合指数(株価)は年初の3351から10月5日3882などなど。総じて言えるのはデフレの傾向が強くなっている。
GDPの3割を占めていた中国不動産の関連主要統計を見ると、8月の不動産開発景気指数は93.05と5か月連続の前月比割れ。不動産の回復には程遠い状況。恒大など元トップ3⃣は上場廃止など悲惨な状況。4年で不動産価値23%、金額29%、面積35%に下落した。
2024年9月26日、党中央政治局会議で「3つの新処置」(安定成長・内需拡大・リスク防止)を打ち出す。11月8日、藍佛安財務相「地方債務の解決のための財源として10兆元を緊急財政支出する」。25年2月17日、習近平主席、民営企業座談会開催し、民営企業の合法的な権益をしっかり保護していくと強調。3月5日、全国人民代表大会で李強首相政府活動報告し、今年の主目標GDP成長5%前後、都市部失業者5.5%などとし、今年の任務は消費の押し上げ、内需の全面拡大(買い換え促進)、未来産業育成=AI+行動持続的推進などと強調した。1月にはDeepSeekの成功をアピールした。3月16日には中国政府が「消費振興特別行動計画」を発表。賃金所得の増加促進、消費拡大など30項目。5月20日、民営経済促進法施工。7月・8月には中国版ニューデール政策(①チベットのブラマプトラ川水力発電プロジェクト、②新疆チベット鉄道=和田・シガツェ・ラサ=建設プロジェクト)を発表。
民営企業が不景気で採用をへらしているので学生の公務員志向が強まっている。24年12月1日実施の国家公務員試験には325万人余りが殺到、平均倍率69倍、最高倍率は1万5千倍だった。本年7月には1222万人が大学・大学院を卒業したが、就職は「超超超超氷河期」。トランプ関税の影響で浙江省義烏の卸売市場もSHEIN村も不況に陥り「雪上加霜」(泣き面に蜂)状態。
中国は冷戦終結以降4回の危機を乗り越えてきた。①1992年社会主義体制危機:鄧小平が社会主義市場経済を採用し高度経済成長を開始し天安門事件の後遺症を払拭した。②2001年国有企業危機:WTOに加盟し、2008年の北京オリンピックを獲得したことで、国有企業改革の後遺症を払拭した。③2008年世界金融危機:北京オリンピックを成功させ4兆元(当時のレートで約58兆円)の緊急財政支出でアメリカ発の金融危機(リーマンショック)を克服し、「米中2大国時代」の到来を印象づけた。④2015年株と人民元暴落危機:スマホ決済をはじめとするビックデーターを駆使したIT革命によって株価暴落などの危機を脱した。⑤2025年経済不況と米中貿易戦争危機はDeepSeekなどのAI革命によって5回目の順風は吹くのか?注目される。
<4期目を目指す習近平体制>
2022年10月の第20回中国共産党大会で、異例の3期目に入った習近平総書記。27年秋の21回大会では、超異例の4選を狙う。10月20~23日の「4中全会」で引き締めを図る。もしも27年引退なら後継候補は李強・蔡奇・丁薛祥・陳吉寧・胡春華の5人と目される。
<トランプ関税と戦う中国外交>
2期目の米トランプ政権と、早くも貿易戦争が勃発した。1期目の時に貿易戦争で叩きのめされた中国は、今回は賢くトランプ政権と対峙している。そんな中で8月31日~9月1日、天津での上海協力機構、9月3日北京での「抗日戦争・世界反ファシズム勝利80年軍事パレード」を主催し存在感を見せつけた。
米中新冷戦は2018年から始まった。①第1次貿易戦争(追加関税)18年3月~、②5G戦争(ハーウェイ、スマートフォン、EV)18年4月~、③人権戦争(香港、ウイグル、チベット)19年6月~、④金融戦争(為替、デジタル通貨、証券市場)19年8月~、⑤疫病戦争(COVID19、ワクチン)20年1月~、⑥外交戦争(領事館封鎖、留学生・研究者追放)20年7月~、⑦半導体戦争(半導体規制)22年10月~、⑧AI戦争(チャットGTP対DeepSeek)22年10月~、⑨第2次貿易戦争(追加関税)25年2月~、⑩軍事戦争(台湾、東シナ海、南シナ海)??。
第2次貿易戦争、米中共に「誤算」の中でのチキンレースが繰り広げられている。中国が貿易で「脱アメリカ」化を加速し、世界に輸出攻勢をかけている。貿易戦争での米中双方の武器は、◆アメリカの武器は米証券市場からの中国系企業の放逐、香港ドルのドルベッグ制の終了。◆中国の武器はレアアースの対米禁輸、アメリカ国債の売却、中国国内の米製品不買運動などがある。
第1回交渉5月10~11日ジュネーブ、米中互いの追加関税を115%引き下げ。第2回交渉6月9~10日ロンドン、中国が米国にレアアース供給で合意。第3回交渉7月28~29日ストックホルム米側がさらに90日間制裁猶予を延長。第4回交渉9月14~15日マドリッド、TikTok売却問題で基本合意。トランプ大統領を北京に呼びたい習近平主席、しかし内外問題山積のトランプ政権は中国問題にまで手が回っておらず北京訪問の日程は定まっていない。―――以上、詳細なデーターを元に、お話しいただきました。
講演後、近藤先生と西堀会長との対談が行われました。
西堀会長は、戦後80年(中国からすると抗日戦争勝利80周年)に当たり、中国に多大な損害を与え、日本も広島・長崎の原爆に見舞われた、あの悲惨な戦争の災禍が再び繰り返されないよう、中国と仲良く付き合っていく意義を再度確認したい。中国は長い歴史の視点に立って日中友好のために戦争賠償を放棄してくれた。中国は100年に1度の激変期にあり、今後が注目されている。近藤先生のお話しは大変参考になった。日中近代史を顧みる時、両国は手を携えて平和を求めなければならない。日中友好は最大の安全保障という言葉をかみしめたい、と述べました。
続いて「4中全会」後の展望、環境問題、一帯一路、青少年交流などが取り上げられ興味深い語らいが続きました。
また中国から県内への観光誘客をめぐり、近藤先生は、現地では長野冬季オリンピック開催地・白馬などのスノーリゾートへの憧れがあると述べ、スキー場や日本酒などをPRしながら「ファンを地道に増やすことが大事」と指摘しました。参加者は熱心に耳を傾けました。
平井利博・長野大学理事長が閉会のあいさつを行い、第1部を終了しました。
◇第2部の祝賀パーティーは中沢保範・県日中事務局長が司会を務め、保谷康弘・県経営者協会総務部長が開会あいさつ。西堀県日中会長のあいさつに続き、来賓として、井出庸生・篠原孝・中川宏昌(代)の各衆議院議員、杉尾秀哉参議院議員、若林健太前衆議院議員の祝辞の後、峯村健司・信濃毎日新聞総務局長の音頭で乾杯し、なごやかに懇談交流しました。米澤正太郎・八十二銀行国際部長が締めのあいさつを行い、懇親会は終了となりました。
 第28期第5回日中関係を考える連続市民講座が3月23日、日中友好センター教室において開かれ、早坂俊廣信州大学人文学部教授が「陽明学と現代」と題して講演しました。参加者は熱心に聴講しました。
第28期第5回日中関係を考える連続市民講座が3月23日、日中友好センター教室において開かれ、早坂俊廣信州大学人文学部教授が「陽明学と現代」と題して講演しました。参加者は熱心に聴講しました。◇早坂先生は、冒頭、昨年秋10月31日、王陽明の誕生日に合わせてゆかりの地、浙江省紹興市で開かれた王陽明生誕記念大会に出席した時の様子を報告し、紹興市を挙げての一大イベントであったことなどを紹介し、現代中国における「王陽明熱」について解説しました。『陽明心学大全』の著者である浙江大学王陽明研究院の銭明院長との交流の様子や、習近平国家主席が王陽明の「知行合一」に言及し、人間の主体的能動性を高める思想として「誠意正心」「知行合一」に学んで人々の模範になろうと呼び掛けている(光明日報)ことなどを紹介しました。 続いて、三島由紀夫の『行動学入門』と松川健二の『王陽明のことば』を取り上げて解説しました。
◇では、孔子の思想を王陽明はどう受け継いだのか。孟子は孔子の思想を受け継ぎ発展させたといわれる。「性善説」も「仁義」も孔子そのものの教えではない。儒教はすべて自己責任論であるといわれる。何が正しい理解なのか?陽明学は人間の主体性を高めるといわれる。戦前は「国のために命をささげる」軍国主義に利用されたとの反省から戦後はすたれてしまった。マルクス主義者である習近平はなぜおしているのか?習近平氏も三島由紀夫氏も「知行合一」説を陽明学の中心思想ととらえていた。習氏は陽明学を学び「人の模範」になれると考えているのに対し、三島氏は陽明学を「革命哲学」「善悪を超越する哲学」と評していた。王陽明自身は、「人が生まれながらに身につけている「良知」(善なる本心)をそのまま発揮して自由に生きる」ことを大切にしていた。善悪を超越していたわけではないが、かといって為政者の言うことに率直に従うべきと考えていたわけでもない。
◎朱子学と陽明学の違い、現代中国でなぜ注目されているのか、三島由紀夫の行動(三島事件)についての疑問など活発な質問や意見が出されました。
2月22日、第28期連続市民講座が日中友好センター教室において開催されました。今回は「日中経済交流の現状と課題―県内企業の動向-」と題して松本大学大学院の兼村智也教授が講演しました。
兼村教授からは、昨年11月30日から短期の中国渡航ビザが免除された機会を利用し、本年1月4日から一週間ほど上海・無錫等の長野県から進出している企業を視察訪問した生々しい情報を提供頂き、参加者20名弱も熱心に聴講しました。
経営の現地化(経営のトップを中国人に)などでの成功は限られていて、進出企業の多くが、中国経済の景気減速(不動産バブルの崩壊)、人件費の高騰、EV車の普及拡大による受注減少、中国から他国への生産移管などの影響を受け、困難が続いている。更に
負債の清算、進出時に受けた優遇措置の返済、従業員への退職金補償などの理由により撤退も困難な厳しい状況、との内容でした。
(長野市日中友好協会 吉岡 弘海)
 第28期第3回日中関係を考える連続市民講座が1月25日、日中友好センター教室において開かれ、中国文学専門で長野県立大学教授の谷口真由実先生が「心にひびく漢詩を読むー紫式部に導かれて」と題して講演しました。講座には25人が出席し熱心に聴講しました。
第28期第3回日中関係を考える連続市民講座が1月25日、日中友好センター教室において開かれ、中国文学専門で長野県立大学教授の谷口真由実先生が「心にひびく漢詩を読むー紫式部に導かれて」と題して講演しました。講座には25人が出席し熱心に聴講しました。谷口先生は、平安時代の紫式部が大きな影響を受けたとされる中国唐代の詩人白居易の「長恨歌」を中心として白居易の心にひびく作品を取り上げて解説いただきました。(下記参照)
先生は最後に、「平安時代の紫式部や清少納言は和漢両方の深い学識があった。その学識の重要な部分に中国の文学や歴史書、哲学書などがあったことを意識しながら、彼女たちの文学を読むことでさらに理解は深まり、感動を新たにすることができるのではないか」と締めくくられました。
【講演の概略】
1⃣ 紫式部について『源氏物語』の作者として名高い紫式部はどのような人物だったのか。生年978年(973年、970年説あり)、父藤原為時は『新古今集』などに詩がとられており、文章生(史記、漢書、後漢書、文選などを学び、詩賦の試験に合格した者)出身の漢学者で詩文に優れていた。(為時は地方官の受領どまりであったが、曾祖父兼輔は堤中納言と称され『古今集』などにもその詩が収められている。)母は早く亡くなったらしく、姉と弟がいた。紫式部はとても聡明で、漢学者の父が弟に漢籍を教えるのを傍らで聞いて、弟より先に覚えたといわれる。宮使えに出たとき中宮彰子に『白氏文集』の楽府を進講するほど漢籍に対する素養が深かった。彼女は漢籍によって得たものを『源氏物語』に十分生かし物語の文学性を高め得た。藤原宣孝と結婚し一女賢子が生まれるが、疫病によって宣孝は他界、その後この世を浮世と思うようになり、本来好きだった物語の創作に励み『源氏物語』が生まれたと考えられている。
② 白居易「長恨歌」
「長恨歌」の作者白居易(772~846)字は楽天、太原の人。盛唐時代の李白や杜甫の後、中唐時代の代表的詩人。地方官の家に生まれ、優秀な成績で進士に及第し翰林学士、皇帝を諫める左拾遺になるも、左遷と中央復帰を繰り返した。最後は刑部尚書に至る。平易な用語で分かりやすい詩を意識的に制作した。平易であるだけでなく巧みな表現と素晴らしい韻律を工夫した詩は、ひろく愛唱された。現存する詩はほぼ3000首に上り、自身でそれを諷喩詩(政治の風刺)、閑適詩(自然を楽しむ)、感傷詩(男女の愛を描く)、雑律詩(その他)に分け詩文集『白氏文集』(75巻)を編集し、我が国の平安文学に大きな影響を与えた。『和漢朗詠集』には白居易の詩が多数収められている。「長恨歌」は感傷詩に属する。
◇「長恨歌」は4つの段落に分かれる。
<第1段落> 「漢皇 色を重んじて傾国を思ふ」「春寒くして 浴を賜ふ華清の池」「三千の寵愛一身にあり」---ここでは漢皇(実は玄宗)と楊貴妃の出会いと二人の愛の日々が詠じられている。そして驪山宮で歓楽を尽くす中、突如、安禄山の反乱軍が大地を揺るがす戦太鼓を響かせて押し寄せ、栄華の夢は一瞬にして破られた。「漁陽の鼙鼓 地を動かして来り」の句は急転直下の場面転換を鮮烈に表している。
<第2段落> 都長安に賊軍が迫ったために、玄宗が蜀へと落ち延びるところから始まる。そして、馬嵬坡でこの反乱は楊一族が元凶と近衛兵に迫られ、楊貴妃は死を賜る。「六軍発せず 奈何ともする無く」「宛転たる蛾媚 馬前に死す」「君王 面を掩ひて救ひ得ず、 回看すれば血涙相和して流る」と描かれ、さらに続けて、蜀に到着後、玄宗の傷心の日々が描かれる。
<第3段落> 玄宗が上皇として都長安へ還御する途中、楊貴妃が落命した馬嵬坡に差し掛かり、悲しみに暮れる場面が描かれ、帰還後、最愛の楊貴妃を失った喪失感にさいなまれる様子が詠じられる。「馬嵬の坡下 泥土の中、玉顔を見ず むなしく死せし処」 「翡翠の衾 寒くして誰と与共にせん」
<第4段落> 傷心に沈む玄宗を見かねて、死者の魂を招くという道士が楊貴妃を尋ねる場面が描かれる。道士(方士)はあちこち探した後、仙山に楊貴妃を訪ねあてる。姿を現した仙女の太真(楊貴妃)は、現世の栄華を洗い流した清澄な存在として描かれ、玄宗と隔てられた悲しみに涙を流し、証拠の品を道士に預け、別れ際にかつて七夕の夜に玄宗と交わした二人の愛の誓いを伝える。「天に在りては 願わくは比翼の鳥となり、地にありては 願わくは連理の枝と為らん」
「長恨歌」の最後は、「天は長く 地は久しきも 時有りて尽く、此の恨みは 綿々として絶ゆる期無からん」の二句で結ばれている。
平安中期の宮廷社会の人々に愛された白居易の詩を見てみたい.。
① 『源氏物語』須磨の巻で光源氏が流謫の身を悲しむ際に口ずさむのは、白居易の「八月十五夜、禁中に独り直し、月に対して元久を想う」詩である。この詩は白居易が翰林学士の職にあった時、親友元慎の身を思いやって作ったものである。元慎はこの年3月に江陵(湖北省)に左遷されていた。② 中宮定子に仕えた清少納言の『枕草子』の“香炉峰の雪は簾を上げてみる”のエピソードが良く知られている。これは白居易の「香炉峰下、新たに山居を卜し、草堂初めて成り、偶たま東壁に題す」(『白氏文集』七律)を彼女が知っていたからできたパフォーマンスである。この詩は『和漢朗詠集】にも収められている。「遺愛寺の鐘は枕を欹けて聴き、香炉峰の雪は簾を撥ねて看る」「故郷は何ぞ独り長安にのみ在らんや」
平安時代の紫式部や清少納言は和漢両方の深い学識があった。それだけでなく、身の回りの事柄や、宮中の出来事、人々の様子などを子細に観察して物語や随筆に綴っているのは驚嘆するばかりである。その学識の重要な部分に中国の文学や歴史書、哲学書などがあったことを明確に意識しながら、彼女たちの文学を読むことでさらに理解は深まり、感動を新たにすることができるのではないか。
 第28期第2日中関係を考える連続市民講座が12月21日、日中友好センター教室において開かれ、中国伝媒大学教授で長野ラジオ孔子学堂中国側代表の夏丹先生が「建国75周年の中国の今日―中国市民の生活と関心事」と題して講演しました。講座には30人が出席し熱心に聴講しました。
第28期第2日中関係を考える連続市民講座が12月21日、日中友好センター教室において開かれ、中国伝媒大学教授で長野ラジオ孔子学堂中国側代表の夏丹先生が「建国75周年の中国の今日―中国市民の生活と関心事」と題して講演しました。講座には30人が出席し熱心に聴講しました。
当日配布された資料は(1)中国経済の発展、(2)生活の変化、(3)教育と就職、(4)高齢者の生活、(5).科学技術、(6)経済発展がもたらした問題についてなどとなっており、現代中国を理解するうえで参考になると思われるので以下紹介したいと思います。
 第28期日中関係を考える連続市民講座が11月30日スタートしました。県内の大学や県日中友好協会などで作る県日中学術交流委員会主催で、毎月1回のペースで文化、歴史、経済関係などをテーマに明年3月まで計5回の講座が開かれます。第1回は長野大学の塚瀬進教授が、「日露戦争と満州」と題して講演しました。30名の受講者は熱心に聞き入りました。
第28期日中関係を考える連続市民講座が11月30日スタートしました。県内の大学や県日中友好協会などで作る県日中学術交流委員会主催で、毎月1回のペースで文化、歴史、経済関係などをテーマに明年3月まで計5回の講座が開かれます。第1回は長野大学の塚瀬進教授が、「日露戦争と満州」と題して講演しました。30名の受講者は熱心に聞き入りました。
日露戦争の原因、経過について解説した後、この戦争に長野県民がどのようにかかわったのかを紹介しました。
1.日露戦争前の満州をめぐる状況1890年以降、ロシアが太平洋を目指して極東への東進政策を推し進める。1891年シベリア鉄道敷設開始、96年清朝から満州内を通る東清鉄道敷設権を得る。98年遼東半島の旅順・大連の租借権を獲得。一方日本は朝鮮を勢力圏にしようとしていた。
1900年の義和団事件が起こる。欧米列強による中国への勢力拡大への反発→東清鉄道の破壊、ロシア人などへの襲撃→ロシア軍の侵攻→鎮圧後も満州に居座る→朝鮮を勢力圏としたい日本と対立激化。以上が日露戦争前の満州をめぐる状況だった。
2.日露戦争の経緯 1904年2月10日、日露開戦に至るが。その後の経緯は以下の通りであった。
① 3月 日軍第1軍が朝鮮に上陸し、5.1清国領に入り、5.3 旅順のロシア艦隊を閉じ込める閉塞作戦を実施しロシア艦隊の出入りを封じる。
② 5.5 日軍第2軍、ロシア艦隊の脅威がなくなったので、遼東半島に上陸し、8.30 遼陽への攻撃開始。9.4 遼陽占領(日軍=13万人:露軍=22万人)。
③ 05年1.1 旅順の露軍降伏(日軍死傷者6万人)→3.1 奉天会戦始まる。3.10 日軍奉天占領(日軍25万動員、死傷者7万、露軍31万動員、死傷者6万)。
④ 5.27 日本海海戦でバルチック艦隊壊滅、日海軍圧勝。
⑤ 9.5 アメリカのポーツマスで日露講和条約
*ロシアでは05年1.9 圧政に反対する血の日曜日事件が起こって社会不安が広がっていて戦争どころではなかった。日本も戦争継続の余力がなく不可能だった。アメリカの仲介によって講和。国民は人的な被害と大増税に耐えて日露戦争を支えたが、賠償金が取れない講和条約に不満を爆発させ、日比谷公園で講和反対大会が開かれたが、暴動に発展した。
3.日露戦争下の状況
現地にいたイギリス人宣教師『奉天30年』より:われわれの周囲には戦争が荒れ狂っていた。中国農民は自分たちの戦争でなかったが、被害は大きかった。
どちらにも加担しなかったが、ロシアの軍政に飽きていたので日軍の進出で自由が回復されると期待した面もあった。
日軍の従軍兵士の日誌より:マキの調達で、現地の中国人が抵抗し泣き崩れる様や戦闘において前線では見る間に死骸の山、友が即死する場面等が記されている。
4.日露戦争と長野県
『軍事郵便は語る 戦場で綴られた日露戦争とその時代』(信濃毎日新聞社2021年刊)
小県郡県村(現東御市)の母校の校長先生のもとに送られてきた550通余りの軍事郵便が残されていた。その中から2通を紹介。
Kは、奉天会戦について「我が重砲兵も7、80名の死傷者を出したが敵は不意に退却したのであっけにとられました」と記し、Oは現地の清国人の悲惨な様子を書いている。(日清戦争後で清国人をさげすむ風潮が文面にも表れている。)
『日露戦役忠勇列伝 長野県之部』
長野県の死者総数は、2,328名に上り、その戦功(忠勇の様)が記されている。戦死者には、「功7級金鵄勲章、年金百円、勲八等白色桐葉章」が授けられているが、病死者には、年金等がないなど差がみられる。
ーーーーーー
明治維新後、富国強兵、欧米列強に伍してアジア侵出を進める出発点ともなった日露戦争の具体的な経緯と長野県とのかかわりを知る良い機会となりました。

第1部の司会を大月良則・県日中友好協会理事長が務め、井出康弘・県中小企業団体中央会専務理事の開会あいさつに続いて、西堀正司・県日中友好協会会長が主催者を代表して、「本年、中華人民共和国建国75周年を迎えた。中国は急速な変化と発展を遂げ、国際社会において重きをなしている。日中国交正常化から52年を経過し、日中関係は様々な困難や課題に直面している。激動する世界にあって、日本も、米国も政権が変わり不確かな状況にある。宮本雄二先生を講師に迎え、平和で安定した日中関係を築くためにはどうしたらよいかをともに考えたい」とあいさつしました。布施正幸・県日中副会長が講師の宮本先生を紹介し、講演に入りました。
◇宮本雄二先生の講演「新しい時代の新しい日中関係構築は可能か」
宮本先生は冒頭、長野県が歴史を踏まえ中国との関係を大切にし地方民間交流に力をいれ全国の模範的な交流活動を進めてきたことに敬意を表したいと述べ、激動する国際情勢の中で、これからどのように新しい日中関係を築いていくべきかについて、深い洞察に富むお話をしていただきました。(概略下記参照)
<はじめに>
私が当たり前と思っている中国の現状をお話しするとびっくりされることがある。日本の皆さんに中国の現状をお伝えすることが重要だと思うようになった。相手のことを理解しないとどのように付き合うのかがわからない。相手のことをとことん知ることは重要だ。経済も外交も同じだ。
<変わり続ける中国>
中国は中華人民共和国成立75周年を迎えた。この間紆余曲折はあったが大きなな成果を上げた。日本も支援したが、中国人自身が良くやった。過去の連続の中に今の中国がある。中国革命が成功し中華人民共和国が成立した。毛沢東の急進路線(文化大革命などの極左路線)は挫折し中国は混乱に陥ったが、鄧小平は改革開放路線で市場経済を導入し経済を大きく発展させた。しかし腐敗汚職などの問題も深刻化した。習近平は胡錦涛の解決できなかったこれらの問題にメスを入れ、党の指導体制の強化をはかり、「中国の夢」を実現しようとしている。世界大国となり国際社会の発言権も増大し3期目以降の長期政権体制を確立したように見えた。しかし現在、習近平路線が挑戦を受けている。ゼロコロナ政策は、コロナを抑え込んで経済への打撃を最小限に抑え成果を上げたとされたが、国民の信任を揺るがす事態を引き起こし、ゼロコロナ政策は突然終結した。さらに米国との対立も付け加わり経済の復活がうまくいかない。習近平の経済思想は「中国の特色ある社会主義市場経済」であり、中国的ガバナンス=すべて党が指導するということになるが、市場との対話は上手ではない。(胡錦涛時代までは、政治は経済に手を出さず市場原理に任せた。)習近平路線は曲がり角に立っており中国は現在少しずつ軌道修正しつつある。
この問題にメスを入れ、党の指導体制のタガをはめさらなる経済発展に導いた。GDP世界第2位となり国際社会の発言権も増大し3期目以降の長期政権体制を確立した。しかし現在、習近平路線が挑戦を受けている。ゼロコロナ政策は、コロナを抑え込んで経済への打撃を最小限に抑え成果を上げたとされたが、国民の信任を揺るがす事態を引き起こし、ゼロコロナ政策は突然終結した。さらに米国との対立があり経済の復活がうまくいかない。習近平の経済思想は「中国の特色ある社会主義市場経済」で中国的ガバナンス=すべて党が指導するということになるが、市場との対話ができていない。(胡錦涛は、経済に手を出さず市場原理に任せた。)習近平路線は曲がり角に立ち中国は現在軌道修正しつつある。
<世界を変えた中国の成功・発展と新たな問題>
米国は中国を自分を超えることのできる初めての挑戦者ととらえられている。この点、民主党も共和党も変わらない。戦後の世界秩序をリードしてきた米国の相対的な力の低下が進み、習近平は鄧小平の韜光養晦(とうこうようかい)路線(才能を隠し時期を待つ)を放棄して、米国との対等の大国関係を目指している。トランプの米国は自国第一主義、世界への関与からの撤退を志向するが、米中関係の緊張は続く。米欧民主主義国の社会の劣化、グローバルサウス諸国の自信と自己認識の変化が進んでいる。中国は中国式歴史認識からくる過剰な自意識、すべてにおいて過剰に反応する。中国は自身ではそんな自覚はないが、東シナ海や南シナ海の島はもともと中国のものなのに、他国に占拠されていると思って行動しており、相手から見ると覇権主義だと映る。
<日中はどういう国際環境におかれているのか>
日本と中国の発展を支えてきた戦後の国際秩序が動揺している。トランプの米国は、多国間主義からの離脱、保護主義(反自由貿易主義)など戦後の国際秩序(第3次世界大戦を防ぐための国際連合憲章、平等・平和、自由貿易等)を否定しようとしている。ヨーロッパも極右民族主義の台頭など一昔前のヨーロッパでなくなってきている。国連の一層の弱体化、ロシア、イスラエルの戦後国際秩序への正面からの挑戦、保護主義の台頭と世界のブロック経済化が進んでいる。歴史を振り返ると第1次世界大戦後の世界経済恐慌の後、経済のブロック化が進み、ナチスや日本の軍部などが台頭し、第2次大戦へ突き進んだ。1930年代の再来となるのか?弱肉強食の「ジャングルの掟」の時代に戻るのか!今分岐点に立っている。
世界の軍事衝突、特に米中の軍事衝突は世界の破滅につながる。
米中の軍事衝突の可能性はあるのか?中国は「1つの中国」の原則で台湾の独立は許さない。李登輝政権の時ミサイル演習を行い激しく反発した。クリントンは空母を派遣する一方「1つの中国」を守ると述べた。その後中国は米国と対抗するため軍備を増強し空母も所有しこれに対抗できるようになった。米国は州兵レベルでは台湾の軍隊の訓練を行っている。トランプは台湾支援を強化するだろう。米国が介入すれば日米安保条約によって日本も巻き込まれる。そうならないようにすることが日本の最重要課題だ。日中は関係が悪いときほど緊密な意思疎通を図る必要がある。最近、秋葉(国家安全保障局長)・王毅(外交部長)会談が行われた。最低限、信頼関係を保ち、意思疎通を図っていくことが重要。来年はハイレベルの日中対話が復活する。李強首相の来日、日本首相の訪中などが実現するだろう。石破政権は長続きしてほしいと思う。
トランプは米国第1主義で予測不能のところがあるが、米国憲法の規定によりトランプの3選はない。、4年間国際社会はこれに耐え教訓を活かすことが必要。米国の力は落ちており世界は米国の思い通りにならず相談せざるを得ない。ヨーロッパは極右、自国第1主義の台頭がみられる。日本は、相対的に見て安定した道を歩んでいる。
<新しい時代の新しい日中関係とは>
中国はどうか。中国は国連重視、国際法と自由貿易など現行の国際秩序を守ろうという立場だ。そうすると、日本と共通点がある。日中が手を結ばなければならないことになる。すなわち「戦後国際秩序の護持と発展」これは日中の「戦略的互恵関係」の意味するところでもある。日中両国は、同じ志を持った「同志国」を糾合し「戦後国際秩序の護持と発展」のために、努めなければならない。そのためにも安定した日中の平和、友好、協力関係を構築すべきである。日中は軍事安全保障、政治外交、経済、文化民間交流の各分野において必要かつ適切な対応をすべきである。日本の民間組織は、日本社会の対中認識の改善に最大限の努力をすべきだ。
◇宮本先生を囲んでパネルディスカッション
 講演後、宮本先生を囲んで濱田州博諏訪東京理科大学長・前信州大学学長、足立正則飯山日中会長・前飯山市長をパネラーに、西堀正司・県日中会長がコーディネーター役をつとめ、パネルディスカッションが行われました。
講演後、宮本先生を囲んで濱田州博諏訪東京理科大学長・前信州大学学長、足立正則飯山日中会長・前飯山市長をパネラーに、西堀正司・県日中会長がコーディネーター役をつとめ、パネルディスカッションが行われました。
濱田氏:中国と大学間交流をしているが、中国の大学は大きく変化している。信大留学したメンバーが留学生同窓会などを通じて交流しているケースもある。
足立氏:飯山市長の時、深圳市福田区と2000年以降、教育、卓球交流などを行ってきた。交流を通じて中国社会の状況変化を感じた。
西堀会長:河北省を訪問した際、長野県に留学し帰国後、河北省の行政、医学、農業などの分野で活躍している皆さんと懇談した。活躍ぶりに感心した。先ごろ広東省から農業と観光資源調査の団が来県した。交流に積極的だった。在日中国人は108万人に上る。大学卒業後の就職困難などの問題もあり、留学生も増加傾向にある。グローカル(グローバル+ローカル)の時代になり、国際交流においても地方が活躍する時代を迎えている。
宮本先生:若い世代の失業率は高く、留学希望者も多い。日本としては中国人材の活躍を期待できる。(EV車の過剰生産問題と環境問題について)EV車は新規産業として一挙に多数が参加し、今でも100社位は残っている。激しい価格競争の事態となった。淘汰が進み、資本力の大きい企業が残っていくた。環境問題は大変難しいが、化石燃料依存から太陽光発電、風力発電、原子力発電などにシフトさせている。北京など青空が戻ってきた。(中国経済の現況、不動産バブル崩壊や失業問題について)統計だけでなく、現場感覚を大事にしている。政府の政策だけで判断するのでなく、経済人や街の人の声を聞いて判断している。不動産バブル崩壊への対処では世界の先例を研究している。政府は財政的に余力はあるがなかなか手を出さないできた。ここにきてテコ入れをしたようだ。企業家精神を尊重する方向に戻した。問題は、社会の雰囲気を変える結果を出せるかどうかだ。GDPは世界第2位、生産力製造業は第1位、人口は第2位、中国の活力は衰えていない。中国の人と物と金が日本に来る時代になった。(日中関係)90%弱が中国に好感が持てないという一方、6,7割が対中関係は重要だと考えている。このことを踏まえて、対中認識の改善に努めていくべきと思う。
第2部の祝賀パーティーは中沢保範・県日中事務局長が司会を務め、更科伸彦・県商工会議所連合会事務局長が開会あいさつ。西堀県日中会長のあいさつに続き、稲玉稔県国際担当部長、勝山秀夫県議の祝辞の後、川原一祐松本歯科大学長の音頭で乾杯し、なごやかに懇談交流しました。岡村重信前県経営者協会事務局長が締めのあいさつを行い、懇親会が終了しました。
 長野県日中学術交流委員会は8月22日長野市内のホテル犀北館において定期総会を開催し、2023年度の活動報告と決算報告、各大学・短大等の学術交流報告を承認し、2024年度の活動方針と予算などを決定しました。総会には、長野県、信州大学、長野大学、県立大学、上田女子短大、県日中友好協会、ラジオ孔子学堂など関係者18名が出席しました。
長野県日中学術交流委員会は8月22日長野市内のホテル犀北館において定期総会を開催し、2023年度の活動報告と決算報告、各大学・短大等の学術交流報告を承認し、2024年度の活動方針と予算などを決定しました。総会には、長野県、信州大学、長野大学、県立大学、上田女子短大、県日中友好協会、ラジオ孔子学堂など関係者18名が出席しました。中村宗一郎会長(信州大学学長)は「パリ五輪では米中が金メダル40個を獲得した。中国に学ぶべき点は多い。国際情勢は激動しているが、共存共栄で、世界平和を守っていきたいと多くの人は望んでいる。そのためには学術分野の交流は大変重要と思う。信州大学でも、世界につながる大学を目指して”覚悟のグローバル化”を打ち出した。留学生を1割に増やす、授業の半分は英語で行う、長野県の新たな産業を興すのに貢献するなどだ。これらを実現するためにも日中の連携は重要だと思っている」とあいさつしました。
席上、稲玉稔県国際交流課長と西堀正司県日中友好協会会長が来賓あいさつ。稲玉氏は、日ごろ日中学術交流や、留学生受入れ派遣に尽力協力いただいていることに敬意を表した後、「昨年8月知事訪中の際は信州大学や県立大学からもご参加いただき、有意義な交流が出来た。中国人学生は大変勉強熱心だ。今後とも県としても相互訪問や留学生交流等を進めていきたい。日本は人口減少の時代に入り、外国人人材の活用が課題に上っている。優秀な中国留学生人材の受け皿づくりの役割も果たしていただきたい」と述べました。
西堀会長は長年にわたり、学術交流委員会が成果を上げてきていることに敬意を表したのち、「コロナ明けで交流が再開された。日本には108万人の中国籍の皆さんが活躍している。帰化している人も20万人はいるだろう。人材としての活躍が期待される。世界が激動している中で、学術交流が平和に果たす役割は大きい。世界とアジアの平和、日中不再戦平和友好に貢献いただきたい」とあいさつしました。
夏丹女士は、中国メディア大学から派遣され、長野ラジオ孔子学堂や長野県立大学での中国語講座などで活躍していることを紹介しました。
活動報告では、各大学、県国際交流課、県日中友好協会などから中国との学術交流状況の報告、雲南省への学生訪中団派遣報告が行われ、出席者がそれぞれの立場から発言し、熱心に意見交換が行われました。また決定された活動方針では、各大学、短大の学術交流促進や第28期日中関係を考える連続市民講座、中国建国75周年記念講演会開催、留学生支援などに取り組んでいくとしています。
 第27期第6回日中関係を考える連続市民講座が4月20日、日中友好センター教室において開かれ、松本大学大学院教授で中国経済や地域中小企業の研究が専門の兼村智也先生が「新たなステージを迎える日中ビジネス」と題して講演しました。講座には約20人が出席し熱心に聴講しました。
第27期第6回日中関係を考える連続市民講座が4月20日、日中友好センター教室において開かれ、松本大学大学院教授で中国経済や地域中小企業の研究が専門の兼村智也先生が「新たなステージを迎える日中ビジネス」と題して講演しました。講座には約20人が出席し熱心に聴講しました。兼村先生は、次のように述べました。
①長野県の中国進出企業数の推移は、2022年6月で180社(香港除く)でピーク時2012年に比べ32.1%減となっている。その理由は、人件費の高騰や環境規制強化などにより「輸出基地」としての優位性が低下、国家安全に関わる戦略物資の輸出規制、データ管理の強化、ゼロコロナ政策の後遺症、生産拠点の移設・分散、取引先の動きと連動しての撤退などがある。
②今後1~2年の事業展開の方向性は、拡大が45.5%のなか、中国は27.7%で初めて3割を下回る。ASEANが中国を上回っている。八十二銀行は香港支店を廃止してシンガポールを支店に昇格。(香港情勢の変化を踏まえた動き)
③中国自動車産業のEV化の進展に伴い、日経メーカーの販売台数が伸び悩み→県内自動車部品関連メーカは中国依存を減らしている。残存者利益を求めるメーカーや、日本からの外注先として位置付けるメーカーも(信頼できる中国人幹部に経営を移管)。
④まとめ:政治的+経済的影響で長野県進出企業の業績は低下。中国でビジネスを継続する企業は経営を信頼できる中国人に任せ、かつ切り離し可能な分業体制を構築して対応している。
講演終了後、対中貿易が依然として対米貿易を上回っている現状(日中貿易は日米貿易の1.3倍)について、中国市場の魅力について、中国から見た日本などについて質問や意見が活発にだされました。
第27期講座はこれで終了し、来期は11月からスタートする予定です。ご協力ありがとうございました。
 第27期第5回日中関係を考える連続市民講座が3月23日、日中友好センター教室において開かれ、早坂俊廣信州大学人文学部教授が「中国古代の思想家・墨子の<非攻>論」と題して講演しました。講座には20人が出席し熱心に聴講しました。
第27期第5回日中関係を考える連続市民講座が3月23日、日中友好センター教室において開かれ、早坂俊廣信州大学人文学部教授が「中国古代の思想家・墨子の<非攻>論」と題して講演しました。講座には20人が出席し熱心に聴講しました。早坂先生は、世界各地で戦乱が拡大し、危惧される現代において、2400年前の春秋戦国時代に、<非攻><兼愛>を説き活躍した思想家墨子の思想に新たな光が当てられているとして、半藤一利氏の『墨子よみがえる ”非戦”への奮闘努力のために』(平凡社)、森三樹三郎訳の『墨子』(ちくま学芸文庫)、魯迅の『非攻』(光文社古典新訳文庫)、酒見賢一の『墨攻』(新潮文庫)、湯浅邦弘の『諸子百家 儒家・墨家・道家・法家・兵家』(中公新書)等を紹介しながら講義しました。
◇はじめに:半藤氏は『墨子よみがえる』の中で「平和な世界にせねばならないと悪戦苦闘した人が墨子」であり、墨子は「兼愛」という「普遍的人類愛」を説いた。愛の普遍を求めるならば当然平和を求める(国際的徹底平和主義)。兼愛の根拠として主宰者としての天を認めた等と述べている。---これらについて、原典に立ち返って検討してみたい。
◇墨子の<非攻>論:「もし1人を殺せば不義といい100人を殺せば100の死罪を犯したと非難する。しかし今、他国を責めるという大きな不義を働く者がいても、これを非難せず、かえってこれを誉めて正義という。まことに不義の何たるかを知らぬといわねばならない。」(森三樹三郎訳の『墨子』)
◇墨子の<兼愛>論:天下の害の生じる根本は互いに愛し合わぬところから生ずる。諸侯が相愛すれば野に戦うこともなく、人と人が相愛すれば害しあうこともなくなる。天下の禍難や争奪怨恨を生じさせないようにできるのは、相愛するという道があるのみである。(『墨子』)
◇墨子の<天志>論:天は義を欲し、不義を憎む。天下の万民をひきいて義に努力することが、とりもなおさず自分が天の欲することをすることである。天が義を欲し不義を憎むことを知る理由は、天下のものすべて、義あるときには生き、義なきときは死し、義あるときは富、義なきときは貧しく、義あるときは治まり義なきときは乱れるからである。天の意思に従うとは、兼ねて相愛し、交ごも相利すことであり、その結果として必ず天の賞を得るのである。大国でありながら、小国を攻めることなく、大家でありながら小家を奪うことなく、強者でありながら弱者をおびやかさず貴き身分にありながら賤人におごらず、智謀を持ちながら愚者を欺くことがなければ、必ず上は天を利し、中は鬼神を利し、下は人を利する。(『墨子』)
◇以上の墨子の原典を踏まえて半藤氏の墨子評価を検討してみたい。
◇「平和な世界にせねばならないと悪戦苦闘した人が墨子」という理解は正しいが、悪戦苦闘は平和それ自体の希求というよりは「天の志」に合致した生き方を追求した結果である。「兼愛」という「普遍的人類愛」については、「自分を愛するように他人も愛する」ことが「天下の利」をもたらすと考えただけである。「国際的徹底平和主義」については墨子の主張はあくまで、<非攻>であり、大国が小国を侵略することを「不義」だと強く非難したが、防衛能力の保持・行使は否定していない。また「天」や「神」が「兼愛の根拠」であることに間違いはないが、現代的な意味でとらえるべきではない。(魯迅の『非攻』、酒見賢一の『墨攻』)
◇「すべての人が兼愛を実践していけば結果として博愛・平等愛の世界が実現するが、それは結果であり、最初から万人を平等に愛せよとは言っていない。墨子は「倶に天をいただく」者同士の相互尊重を説いた。それは単純な理想論から発せられたものではなく、「そうすることが結果として天下全体に幸福と利益をもたらすのだ」(兼相愛、交相利)という現実的でしたたかな読みが根底にあった。(湯浅邦弘の『諸子百家 儒家・墨家・道家・法家・兵家』)
◎なぜ墨家は滅び、儒家は継続発展したのか、なぜ危機の時代に墨家はよみがえるのか、現代中国では墨家はどう受け止められているか、墨家の思想は反覇権主義といってよいか、など参加者から多くの質問や意見が出されました。
 第27期第4回日中関係を考える連続市民講座が2月18日、日中友好センター教室において開かれ、中国文学専門で長野県立大学教授の谷口真由実先生が「杜甫の自伝的長編詩を読む」と題して講演しました。講座には20人が出席し熱心に聴講しました。
第27期第4回日中関係を考える連続市民講座が2月18日、日中友好センター教室において開かれ、中国文学専門で長野県立大学教授の谷口真由実先生が「杜甫の自伝的長編詩を読む」と題して講演しました。講座には20人が出席し熱心に聴講しました。谷口先生は、中国文学に見る自伝詩の歴史を紹介したのち、杜甫の自伝的作品を取り上げ解説しました。
◇唐代の詩人杜甫は多くの自伝詩を残しており、自伝詩人といわれている。その詩は3種に分類される。①すべての作品が自身の生活、経歴を反映している。②人生の節目ごとに作られた、時事を含めて回顧した長編詩=「詠懐古五百字」、「北征」、「秋日菱府詠懐一百韻」など。③晩年に一生を総括した、純粋に自伝的な作品=「壮遊」、「昔遊」など。
◇杜甫の晩年の自伝的な一連の詩は、いずれも安史の乱に始まる激動の時代を回顧する作品であり、自伝的な詩といえる。その中でも「壮遊」の詩は、世の中の転変に重心を置くのではなく、自分の変化を描いている点、自伝詩と呼ぶにふさわしい。(今回は省く)
◇今回は、安史の乱下における杜甫の自伝的な詩「北征」を取り上げて解説された。
制作時期は、至徳2年(757年)、この時を起点に安史の乱勃発に遡って振り返り、事件や状況の刻々とした変化を回顧する場面が、作品の随所に織り込まれている。杜甫は、都での賊軍による軟禁状態からようやく脱出し、粛宗(玄宗の後継)のもとに駆け付け、その功により左拾遺の官を授けられた直後、宰相の房琯を弁護したために、皇帝の逆鱗に触れ、解職されて、帰省する。家族との再会は切望していたことであったが、このような形で暇を出されることは恥ずかしく、不満に感じてもいた。このように葛藤・煩悶の状況下で作られたのがこの「北征」詩である。この詩は五段落で構成されている。(1)旅立ちの経緯、目的が述べられる。併せて都を立ち去りがたい思いも描かれる。(2)帰省の途上目にした情景を詠じ、自然の恵みと同時に、白骨を見ては動乱の初期官軍の敗退、人々の死を回想する。(3)1年ぶりの家族との再会の喜びを描く。妻や子供たちが貧窮生活を送っていたことも詳細に表現されている。(4)現在の時局を述べる。官軍がウイグルの助けを得て禍を福に転じ賊軍を撃退してほしいと期待を述べる。(5)反乱勃発の当初を回顧し、陳将軍が、玄宗政治の過誤を正し楊家一族の処罰を要求したことへの賞賛を述べる。更に粛宗の中興により腐敗政治が刷新され唐王朝復興ができるであろうと期待を述べて結んでいる。
◎全体の構成を見て気づくのは、公的な存在としての杜甫のまなざしがとらえた、情景や思索に加えて、一人の人間としてのまなざしからとらえられた家族一人ひとりの動作の描写や情感が盛り込まれ、多元的な場面がおりなされていること。ーー更に詩文の主要な部分を紹介解説していただいた。
 第27期第3回日中関係を考える連続市民講座が1月27日、日中友好センター教室において開かれ、公社日中友好協会全国本部専務理事の西堀正司氏が「日中関係の現状と課題」と題して講演しました。
第27期第3回日中関係を考える連続市民講座が1月27日、日中友好センター教室において開かれ、公社日中友好協会全国本部専務理事の西堀正司氏が「日中関係の現状と課題」と題して講演しました。西堀氏は長野県と河北省の友好県省40周年を記念し、昨夏阿部守一知事らと訪中した際のエピソードを報告。洪水の現場対応から戻った北京市長と阿部知事の会談で「防災・減災対策の話し合いを協力してやろうとの話になった。河北省との間では40年の成果を生かして交流を継続発展させていくことで合意した」と明かしました。「1979年から続く中国とのスキー交流も1998年の長野オリンピック招致の際の中国の協力の支援につながり、2022年の北京冬季オリンピック実現に大きく貢献したと中国側から感謝された」と述べました。
参加者からの「日中の不協和音を埋めるのに何が有効か」との質問に、西堀氏は「世論が中国に対して冷めている。友好を喚起するには地方民間運動やマスコミや学校教育の役割が大きい」と強調。「県内にも9千人の中国人が暮らしている。直接あって交流するのが一番の近道」と訴えました。
2024年日中友好新春講演会・新年会を開催(1/23)2024
 長野県日中友好協会・県日中経済交流促進協議会・県日中学術交流委員会は1月23日、2024年日中友好新春講演会・新年会を長野市内のホテル犀北館で開きました。友好協会会員や各団体関係者ら100余名が出席。新年会はコロナ禍の平穏化に伴い、4年ぶりの開催となり、和気あいあいの雰囲気の中、日中の友好交流の推進を誓い合いました。
長野県日中友好協会・県日中経済交流促進協議会・県日中学術交流委員会は1月23日、2024年日中友好新春講演会・新年会を長野市内のホテル犀北館で開きました。友好協会会員や各団体関係者ら100余名が出席。新年会はコロナ禍の平穏化に伴い、4年ぶりの開催となり、和気あいあいの雰囲気の中、日中の友好交流の推進を誓い合いました。
西堀正司・県日中友好協会会長代行は、「日中友好の立場で体制の違いを乗り越え、協力してアジアや世界の平和への貢献と緊張緩和を目指していきたい。地方民間交流の推進の年としたい」とあいさつ。来賓の阿部守一知事は、県と河北省の友好提携40周年に合わせて昨年夏に同省を訪れたことに触れ「顔の見えるしっかりとした信頼関係の構築が大切なことを実感した。今後とも皆さんとともに地方交流を継続推進していきたい」と述べました。また、若林健太・篠原孝・井出庸生(代)・中川宏昌(代)の各代議士、平井利博長野大学理事長、山本格日銀松本支店長、経済界、労働界、県国際交流課長、県産業政策課長、山ノ内町・松川村・白馬村の代表、王昌勝県華僑総会会長、夏丹長野孔子学堂中国側責任者ら各界来賓が出席し日中平和友好の重要性を語り、新年の友好交流発展に期待しました。
新年会に先立って、(公財)日中友好会館中国代表理事の黄星原氏が「日中関係の歴史・現状と課題」と題して記念講演しました。国交正常化以来の日中関係の推移を振り返りながら、“日中対立と対話の併存時代”にあって、コロナ禍で途絶えた日中交流の早期再開などを訴えました。黄先生は、日本大使館勤務や中南米などの大使を歴任され、中国人民外交学会副会長兼秘書長を務められるなど、国際的視野にったって日中関係を論ずるなど活躍しています。中国の現状に理解を深め、日中両国が今後、相互信頼を深め協力提携しアジアと世界の平和と繁栄に貢献していくにはどうしたらよいかをともに考える良い機会となりました。
講演の要旨は次の通り。
|
一、 一、日中関係は3つの段階に分けて推移して来た。 ⑴ (1)第一段階は1972年から1992年「日中友好の時代」:三千人の青年大交流、「国際的なバランス感覚」を持った政治家の存在。 ◎日中共同声明や平和友好条約などの四つの政治文書は日中関係発展の異なる段階において長期的かつ安定した中日関係発展の必要性、重要性、基本原則を全面的かつ深く述べ二国間関係を発展させるための具体的かつ重要な戦略を提示していた。
⑵ 朝鮮半島が韓国政府の「一辺倒」政策により再び緊張状態になる。 ⑶ 経済貿易の発展が日中両国の「政冷経寒」を防ぐ。 ⑷ コロナ禍で途絶えた日中間の交流を早期に再開する。 ⑸ 環境づくりはどうすればいいか。 四、 日中関係の未来に向けて改善への提言 ⑴ 方向が未来を決めることを理解すること。⑵ ウィンウィンを堅持して経済協力を推進すること。 ⑶ 人的交流を深化させること。 ⑷ きちんと危機を管理すること。 |
 第27期第2日中関係を考える連続市民講座が12月17日、日中友好センター教室において開かれ、中国伝媒大学教授で長野ラジオ孔子学堂中国側代表の夏丹先生が「中国メディア事情と中国メディアスクール」と題して講演しました。講座には20人が出席し熱心に聴講しました。
第27期第2日中関係を考える連続市民講座が12月17日、日中友好センター教室において開かれ、中国伝媒大学教授で長野ラジオ孔子学堂中国側代表の夏丹先生が「中国メディア事情と中国メディアスクール」と題して講演しました。講座には20人が出席し熱心に聴講しました。
夏先生は、中国伝媒大学を卒業し、その後も大学で勤務してきた40年近い経験をもとに話しました。
①最新の統計によると、中国には1,810の新聞と定期刊行物があり、2,500以上のラジオ局とテレビ局があります。ラジオ・テレビは、通常、政府機関と密接に関連しています。多くの中国メディアの中で、最も影響力があるのは、新華社通信、人民日報、中国メディアグループで、ニュースやニュースレター、新聞、ラジオやテレビを代表する、中国で最大かつ最も重要な3つのメディアです。
②中国国内では、中国政府に関する公式情報の多くは新華社通信から得られます。 新華社通信は中国の国営通信社であるため、公式ニュースは新華社通信を通じて発表され、世界中のメディアにおける中国の政治と外交の公式ニュースも新華社通信が発行する通信を使用します。人民日報は中国共産党中央委員会の機関紙です。人民日報は1948年に創刊され、中国最大の新聞で昨年の人民日報の発行部数は250万部です。 2018年3月、中国中央テレビ局、中国国家ラジオ局、中国国際放送局は共同で中国中央広播電視台集団(CMG)を設立しました。記者と編集者が6,629人もおり、スタッフの総数は約40,000人と推定されています。
◇以下、印象に残ったことを3点紹介しますーーー。
①.テレビはかつては広告収入で潤っていましたが、近年、ネットメディアやモバイルメディアの影響により、テレビ局の広告が減少し、苦境を打開するために様々な対策を講じています。 新しいメディアへの移行は、その主な方法の1つです。WeChat、TikTok、Xiaohongshu(小紅書)などの中国で最も有名なソーシャルメディアサイトは現在活況を呈しており、ニューヨークに上場しているサイトもあります。オンラインメディアとモバイルソーシャルメディアは、徐々に従来のメディアの役割と機能に取って代わりつつあり、従来のメディアはますます影響を受けています。
②.1980年代以降、改革開放によって、中国の経済は急速に発展し、テレビを購入する人が増え、テレビ番組の制作はますますエキサイティングになりました。 同時に、多くのアメリカと日本の番組が中国のテレビ画面を占有し始めました。 当時、人々が見たいのは日本のアニメ「鉄腕アトム」、ポケモンでした。ポケモンで、ほとんどの人がピカチュウを知っており、「血の疑惑」や「マンハント」などの日本の映画やテレビシリーズを見る機会があり、その後、アニメ「名探偵コナン」、宮崎駿の「千と千尋の神隠し」をテレビで放送し、中国の視聴者は高倉健、三浦智一、山口百恵などのスターを知りました。
日本は中国の緊密な隣国でもあるため、中国のメディアは日本に注意を払っています。 国会議員選挙、岸田首相と各国首脳との会談、日本での頻発地震、さらには日本の天候の変化まで、報道があります。 特に、最近の日米合同軍事演習や、この1年間の円相場の継続的な下落や電力・ガス価格の高騰は、中国国民の注目を集めており、中国メディアでも大きく報道されています。 11月17日、岸田総理と習近平国家主席がサンフランシスコで会談し、当時の中国メディアの重要な報道にもなりました。桜の季節に日本人が桜を見に行くこと、日本の有名な相撲などについても報道しています。 これらの報道により、中国人の日本に対する理解が深まりました。多くの中国人は、東京では駐車場が難しく、駐車料金が高いことを知っていますが、東京には便利な公共交通機関、地下鉄、路面電車が四方八方にあり、日本の新幹線が特に便利で時間厳守であることも知っています。 また、日本人はとても礼儀正しく、公共の場で話したり電話で話したりしません。日本はどこもきれいで、路上にゴミがない、誰もが意識的にゴミを分別している、などです。 中国のメディアは、両国民の友情と理解を深める上で非常に重要な役割を果たしてきました。
中日両国のメディアの交流や協力は、特にテレビの分野で非常に緊密で、両国のメディアは長い間、互いに協力してきました。 CCTVは過去にNHKと緊密な連携を取り、影響力のあるテレビ番組を制作してきました。 何年も前に、彼らはテレビドキュメンタリー「シルクロード」を共同制作しました。 2005年、中国のCCTVと日本のNHKが共同で「新シルクロード」を制作しました。
現在、テレビドキュメンタリーシリーズ「世界遺産ウォーク」を共同制作し、さらなる協力関係を築いています。パンダの翔翔(シャンシャン)を紹介する番組「シャンシャン家に帰る」も共同制作しています。 この番組では、ジャイアントパンダの家族による日本での生活や、中国に帰国した翔翔の新たな生活について紹介しています。 2024年1月にCCTVとNHKで同時放送される予定です。日中記者交流も盛んに行われています。 中国メディアの記者の中には、日本のメディアで一定期間働き、研修を受ける人もいます。
③・メディア人材の育成に関しては、北京放送学院(現在は中国伝媒大学)が最も長い歴史と最強の強みを持っています。 1954年、北京に北京放送学院が設立され、当時中国で唯一のメディア専門学校となりました。
ラジオやテレビのタレントの需要が高まるにつれて、ラジオやテレビのタレントの育成に従事する学校の数も増加しています。 かつては北京放送学院がほぼ1つしかありませんでしたが、今は全く違います。 北京放送学院は伝媒大学に発展し、浙江省メディア大学、河北メディア大学、南京メディア大学など、メディア人材を育成する学校が十数校誕生しました。 中国で最も有名な北京大学と清華大学も、それぞれ2001年と2002年にジャーナリズムとコミュニケーションの学校を設立し、放送とホスティングの専攻を開設しました。
現在、中国伝媒大学には博士課程・修士課程5,000人以上を含む18,000人がおり、校舎規模は3倍に増えました。 84の学部専攻と多くの修士号と博士号があり、7つのポスドク研究ステーションがあります。 学校はジャーナリズムとコミュニケーション、情報通信工学を主な分野としており、音楽とダンス、美術、中国と中国の文学、外国の中国文学、電子科学技術、コンピューター科学技術、インターネット情報などの専攻もあります。 また、英語、フランス語、ドイツ語、ロシア語、日本語など20の外国語教育も充実しています。
学生が海外で学ぶ機会も増えています。 現在、日本では中国伝媒大学の数十人の学生が学んでいます。 日本やヨーロッパやアメリカに行く人も結構います。伝媒大学のコースの多くは4年制の大学のコースであり、伝媒大学で2年間勉強し、2年間留学するか、中国で3年、海外で1年勉強する必要があります。 このようにして、国際的な人材を育成し、新しい技術を学び、外国語のスキルを向上させることができます。また、教員は、海外の教員と交流する機会が多く、客員研究員として日本、アメリカ、ヨーロッパに行くことも多く、海外の教員との交流を通じて、常に最新の国際水準に即した専門知識を持つことができます。 アメリカ、ヨーロッパ、日本の大学で修士号や博士号を取得した先生もいます。ジャーナリズム、映画、テレビ芸術、放送、広告などに興味のある学生が、中国伝媒大学を訪問し、伝媒大学に留学することを歓迎します。
 第27期日中関係を考える連続市民講座が11月25日スタートしました。県内の大学や県日中友好協会などで作る県日中学術交流委員会主催で、毎月1回のペースで文化、歴史、経済関係などをテーマに明年4月まで計6回の講座が開かれます。
第27期日中関係を考える連続市民講座が11月25日スタートしました。県内の大学や県日中友好協会などで作る県日中学術交流委員会主催で、毎月1回のペースで文化、歴史、経済関係などをテーマに明年4月まで計6回の講座が開かれます。
第1回は長野大学の塚瀬進教授が、「3つの大日向村―佐久穂・吉林舒蘭・軽井沢」と題して講演しました。満蒙開拓団を当時の国策に沿って日本一多く送出した長野県の先鞭をきって大日向村が分村開拓団を送り出した時代背景や村を取り巻く状況などを詳しく解説しました。---財政破たんした大日向村は分村開拓団を吉林に送り出したが、そこは現地の農民が耕作していた水田地帯だった。安く買い上げ入植地とし、順調な滑り出しだったが、日本の敗戦によって多くの犠牲を出しながら帰国した人たちに残された道は、寒冷地軽井沢の山間地での開墾だったーーー。受講者は熱心に聞き入っていました。
兼村先生は、次のように述べました。
①長野県の中国進出企業数の推移は、2022年6月で180社(香港除く)でピーク時2012年に比べ32.1%減となっている。その理由は、人件費の高騰、競合する中国企業の台頭があり、中国政府も競争力のない企業の撤退は歓迎している。
②コロナ禍による中国ビジネスの懸念材料(ゼロコロナ政策による影響)として、現地駐在員の帰国困難(日本から支援者が出向けない)、操業停止命令、日本に部品・材料が届かない→中国依存リスク軽減の必要性などがある。
③人の現地化をはかるメリットとして、意思疎通が図りやすくなる、現地従業員の労働インセンティブが高まり定着も進み業績向上につながる、駐在員コストを削減できる。現地化が進まない理由として、本社との意思疎通が図りにくい、優秀な人材が給与・処遇面で優位にある非日系企業に流れてしまいその結果人材育成が進まないなどがある。
④現地化について以下4つのパターンを紹介。
(イ)完全現地化が進んだ企業として、ミクロ発條(本社諏訪)を紹介し、日本留学・就業経験をもつ中国人を登用、現地で日本社長との共働経験があり意思疎通も良好である。
(ロ)一部現地化の企業の例として、南信精機製作所(本社飯島町)、ダイヤ精機(岡谷市)を紹介。財務管理は日本人、顧客管理などは日本留学経験のある者、現場管理は中国人などとしている。
(ハ)駐在員を減員した企業として、ミスズ工業(諏訪)を紹介。新事業立ち上げ製造担当スタッフを亡くし、社長と工機担当のみを残す。
(二)不変の企業も、先行き見通しに変化がみられる。日本留学・本社就業経験をもつ中国人を現地登用する、関連中国企業に資本を一部売却し技術系を派遣するが経営は現地に移譲する、完全売却などを近日中に考えているなど。
⑤中国ビジネスの新たな懸念材料。
(イ)米中対立による影響として、デカップリングにより輸出入はリスクが大きくなり、中国での受発注を中国国内で完結させる必要性が高まり現地営業が重要となる。
(ロ)政治的リスクをどうマネジメントしていくか。
(ハ)中国が欲しがる技術(半導体、液晶パネル、などの産業チェーンの脆弱な部分を重点的に補強するとの中国政府の方針)と日本政府の経済安全保障政策との板挟みで今後について難しい判断を迫られる。該当する企業が全国で4000社ほど。
講演終了後、デカップリングなどにより経済交流がさまたげられることについて質問や意見が活発にだされました。
第26期講座はこれで終了し、来期は11月からスタートする予定です。ご協力ありがとうございました。
 第26期第5回日中関係を考える連続市民講座が3月25日、日中友好センター教室において開かれ、中国文学専門で長野県立大学教授の谷口真由実先生が「中国古典詩にみる自然へのまなざしー陶淵明、王維、李白、杜甫を中心に」と題して講演しました。講座には24人が出席し熱心に聴講しました。
第26期第5回日中関係を考える連続市民講座が3月25日、日中友好センター教室において開かれ、中国文学専門で長野県立大学教授の谷口真由実先生が「中国古典詩にみる自然へのまなざしー陶淵明、王維、李白、杜甫を中心に」と題して講演しました。講座には24人が出席し熱心に聴講しました。谷口先生は、中国六朝時代から唐に至る古典詩の代表詩人の作品を取り上げ、「自然に対するまなざしには、詩人の生きた時代により、また境遇の違いにより差違があるが、自然への憧れ、畏怖など読み取ることができる」と述べ、各時代の代表的詩人の作品を紹介解説しました。
◇詩における「自然」とは、中国最古の詩集『詩経』や戦国時代の『楚辞』にも自然は描かれているが、その自然は人間にとって有用な存在として取り上げられていて、自然そのものをテーマとして詠じることはあまりなかった。晋末、北西の異民族の侵攻により、漢民族が南下し東晋王朝(都は健康=南京)をたてた。人々は江南の美しい「風景」に出会い自然を詠じるようになった。
◇六朝時代の陶淵明と謝霊運・謝朓の「自然」詠
◎陶淵明「帰園田居(園田の居に帰る)」、「飲酒二十首」
軍閥政権下、官吏となるが自ら辞めて郷里に帰る。後半生を田園で生きた。田園詩人と呼ばれる。「桃花源」(桃源郷)のユートピアを記した文人でもある。「長い間、鳥かごの中でのような窮屈な生活をしていたが、またのびのびとした自由な境地に帰ることができた」。「山気 日夕に佳し、飛鳥 相ひともに還る、此の中に真意有り、弁ぜんと欲して已に言を忘る」と詠う。
◎謝霊運「過始寧墅」(始寧の墅=別荘を過る)
上流貴族の家に生まれたが、権力闘争に巻き込まれ左遷された。後に謀反の嫌疑を受けて流謫、処刑された。この詩は故郷の別荘に立ち寄った時の自然を詠っている。アウトドア―派で山水詩人と呼ばれる。
◎謝朓「游東田」(東田に游ぶ)
声律を重視した詩を創始し、繊細な風景描写にすぐれ、唐・李白が敬慕した南斉の詩人。自然の中に入って自分を取り戻す喜びを詠う。
◇唐詩における自然へのまなざし
◎王維「辛夷塢」(こぶしの植わっている土手)
盛唐の詩人。9歳で詩を作り、宮廷の寵児となった。自然観照に優れ、自然詩人として知られる。「こずえの芙蓉の花 山中紅萼を発く 澗戸は寂として人無し 紛々として開き且つ落つ」
◎李白「山中答俗人」(山中で俗人に答う)
盛唐の代表的詩人。西域(現在のキルギス共和国)に生まれ、5歳の時に裕福な商人であった父とともに青蓮郷(四川省)に移住した。科挙を受けた形跡がなく、遊侠を好み、道士となる修業をした。玄宗の時、翰林供奉(詩歌を作ったり詔勅を起草)となり、「詩仙」と称された。「桃花流水 窅然として去る 別に天地の人間に非ざる有り」(桃の花びらが川の水にのってはるか遠くに流れていく。世俗と異なる別世界がここにはある。)
◎杜甫「絶句二首其二」、「登高」
20歳のころから天下を周遊し、李白とも親交を結んだ。30代半ば長安に出て士官を求めたがかなわず、苦節10年玄宗に認められて官職につくも、まもなく安禄山の乱が勃発、波乱の人生を歩む。後、官を辞し成都などを旅する。当時の社会事情をリアルに描き、社会詩人と称され、またその詩は“詩によって描かれた歴史”として「詩史」と称される。
 第26期第4回日中関係を考える連続市民講座が2月18日、日中友好センター教室において開かれ、信州大学人文学部准教授の豊岡康史先生が「清朝の海賊問題」と題して講演しました。講座には17人が出席し熱心に聴講しました。
第26期第4回日中関係を考える連続市民講座が2月18日、日中友好センター教室において開かれ、信州大学人文学部准教授の豊岡康史先生が「清朝の海賊問題」と題して講演しました。講座には17人が出席し熱心に聴講しました。
豊岡先生は、「国際関係と国内問題はどちらが優先されるのか?清朝政府のホンネとタテマエ、公式発表をどこまで信じるか?」と問題提起し、「清朝と海賊問題」の事例を紹介しながら解説しました。
アヘン戦争前夜の18-19世紀の清朝、浙江・福建・広東の各沿海域や南シナ海では海賊行為が急増し、大きな被害をもたらした。
2.ベトナムから来る海賊
18-19世紀の南シナ海で海賊が横行する中で、清朝とベトナム関係における「海賊」の扱いは興味深い。
日中関係を考える連続市民講座第26期第3回は、上田女子短期大学学長の小池明先生が「米中のはざまにおける日本の立場と選択肢」と題して講演しました。20年間の商社マン勤務うち約半分を、イギリス、フランス、アメリカで過ごし、中国にも深い関心を寄せ留学生の受け入れなど行ってきた体験も踏まえ、米中対立が激化する中で両国と深いかかわりを持つ日本はどうあるべきかについて話し、26名が熱心に聴講しました。
小池先生は中国、アメリカの現状と近未来、世界の今を解説した後、日本の選択肢について語りました。
――中国は1977年文化大革命終了時点では世界的プレゼンスがわずかなものであったが、改革開放への転換以来大きく発展し世界の重要なプレイヤーとなっている。「国家資本主義」的発展を遂げ、同じチームではなく1つの極を作った。中国は高度経済成長期を過ぎ、安定成長期に入っている。世界の工場(共通のルール)、巨大市場、一帯一路、大国志向、権力集中などに国際社会から今後の行方を注視されている。多民族国家で高齢化などかかえている問題も多い。経済発展が共産党統治の正当性だったがダウンした時、民族主義を掻き立てて乗り切ろうとしないか。
一方のアメリカは格差と分断が深刻で大変な世になってきている。妥協なき分断、深刻な人種差別が存在し、産軍複合体で外国に過剰介入してきた。「遠くの戦争は蜜の味がする」。しかし、自由主義のチャンピオンとして創造エネルギーを持っている。米は、覇権国の一方の極としてあり続けるだろう。
米から見て中国の成長はいいが価値観の違う対極を作ってもらっては困る。2020年以降、米の作った世界秩序を壊そうとしているとの疑念を深め中国の体質(体制)に批判が向けられるようになった。中国から見ると、米は旧体制維持のため価値観を押し付けていると反発している。米中対立、覇権争いの激化の中で日本の立ち位置は難しくなっている。日本は、対米関係を基軸としつつも、最大の貿易相手国である中国ともうまく付き合っていくべきであり、いろいろな分野のいろいろな人々との交流を深めていくべきだ。国と国の関係は一時的な対立、緊張はあるのが当然であり、それを永続させない努力が双方に不可欠。――
講演終了後受講者からデカップリングや金融資本主義などについての質問が出されました。
 日中関係を考える連続市民講座第26期第2回は、元中学校教諭の飯島春光さんが「中国残留孤児3世がかかえる課題」と題して講演しました。学校教育の現場での経験や取り組みを踏まえ、残留孤児の歴史的背景を学ぶ大切さを訴えました。
日中関係を考える連続市民講座第26期第2回は、元中学校教諭の飯島春光さんが「中国残留孤児3世がかかえる課題」と題して講演しました。学校教育の現場での経験や取り組みを踏まえ、残留孤児の歴史的背景を学ぶ大切さを訴えました。
飯島さんは勤務先の長野市内の中学校で、中国人への偏見から帰国者3世や4世の生徒へのいじめが深刻化したことを紹介。生徒の祖父母らから、戦時中に旧満州(中国東北部)で苦労した経験を聞き取り、授業で他の生徒と共有することで帰国者への理解を深めたとしました。「周囲だけでなく、当事者の3世ですら自分のルーツを知らないのが問題だった」と話しました。
帰国者の問題が世代をまたいで続いている背景として、「学校教育で満蒙開拓の歴史が十分に教えられていない」と指摘しました。 講演終了後受講者から次々と質問や感想が出されました。
 第26期日中関係を考える連続市民講座が11月27日からスタートしました。県内の大学と県日中友好協会などで作る県日中学術交流委員会主催で、毎月1回のペースで文化、歴史、経済関係などをテーマに計6回の講座が開かれます。
第26期日中関係を考える連続市民講座が11月27日からスタートしました。県内の大学と県日中友好協会などで作る県日中学術交流委員会主催で、毎月1回のペースで文化、歴史、経済関係などをテーマに計6回の講座が開かれます。
第1回は長野大学の塚瀬進教授が「中国における満州族の歴史」と題して講演しました。当日は24名が熱心に受講しました
―中国の人口統計によると約1000万人の満族(満州族)がいるととされる。共通の宗教や言語は存在しない。マンチュリア(満州)における満州人の軌跡を見ると、①ヌルハチ・ホンタイジがジュシェン(女真)人(その後マンジュ=満州と呼ぶ)の各部族を統合し、八旗に編成して軍事力の動員を効率的にし、周辺のモンゴル人、漢人を取り込み勢力を拡大。②山海関から入関後は、漢人移住者を取り込み、旗人の人数は増加。旗人は、マンチュリア、北京、各地の駐防拠点に配置された。③20世紀以降、旗人の特権は廃止、さらには打倒の対象となる。④中華人民共和国により少数民族に指定され、民族として存在が認められる、などと―と語りました。講演終了後、出席者から活発な質問や意見が出されました。
連続市民講座の開催趣旨は次の通りです。
日中国交正常化から50年を経過しました。日中関係は新型コロナによる人的交流のストップ、米中対立の激化によって、経済、文化学術、スポーツなどの分野の交流においても困難が続いています。日中共同声明の原点に返って日中関係を破たんさせないため英知を集め、両国国民の相互信頼関係を醸成していくことが望まれます。歴史的に深いかかわりを持ち、日本の最大 の貿易相手国である中国はGDP第2位の経済大国となり巨大な変化を遂げています。14億人が住む隣国中国に対する理解を深めることは日本にとって一層重要となっています。長野県日中学術交流委員会では、中国を多面的に理解するために県内で活躍している大学・短大等の先生を講師に迎え、第26期連続市民講座を計画しました。多数ご参加ください。

 長野県日中友好協会・県日中経済交流促進協議会・県日中学術交流委員会は10月18日、日中国交正常化50周年記念講演会を長野市内のホテル犀北館で開きました。講演会には、各界来賓や県内各地から120名が出席。西園寺一晃先生(元朝日新聞総合研究センター主任研究員)を講師に迎え「米中対立激化の中での日中関係・その現状と展望」と題して記念講演が行われました。終了後、先生を囲んでパネルディスカッションがおこなわれました。中国研究、日中関係の第一線で活躍されている先生ならではのお話で、グローバルな視点から日中関係のおかれている現状と課題を考える有意義な機会となりました。
長野県日中友好協会・県日中経済交流促進協議会・県日中学術交流委員会は10月18日、日中国交正常化50周年記念講演会を長野市内のホテル犀北館で開きました。講演会には、各界来賓や県内各地から120名が出席。西園寺一晃先生(元朝日新聞総合研究センター主任研究員)を講師に迎え「米中対立激化の中での日中関係・その現状と展望」と題して記念講演が行われました。終了後、先生を囲んでパネルディスカッションがおこなわれました。中国研究、日中関係の第一線で活躍されている先生ならではのお話で、グローバルな視点から日中関係のおかれている現状と課題を考える有意義な機会となりました。
布施正幸・県日中友好協会副会長が主催者を代表して、「日中国交正常化50周年を迎えたが、日中関係は経済交流が史上最高を記録している一方、コロナ禍や、尖閣問題、米中対立の激化など多くの困難にぶつかっている。とりわけ米中対立の激化の波に巻き込まれて両国関係が破たんするようなことの無いよう英知を集めて進んで行くことが大切と思う。先生を講師に迎え、グローバルな視点から日中関係のおかれている現状と課題を考えていきたい」とあいさつしました。
阿部守一県知事の祝賀メッセージが小林一洋県国際交流課長から披露されました。知事は「日本と中国は一衣帯水の隣国同士であり、文化的、歴史的ばかりでなく、経済的にもお互いなくてはならない深い関係にある。来年は長野県と河北省との友好提携40周年の節目を迎える。これまで積み重ねてきた両県省の交流の更なる深化を図っていきたい。講演会が日中関係の理解を深める場となることを期待申し上げます」と述べています。
西園寺先生は、米中対立の現状を分かりやすく解説し、今後もこの対立は長く続くが米中戦争は起こらないと述べました。また1972年の日中国交正常化に至った経過を振り返り、他の国とは違って民間交流の積み重ねがありLT貿易など経済界の期待が大きかったと指摘しました。米中対立が激化する中、「日本は米中のはざまでどのようなスタンスをとるか。双方とバランスの取れた、いい関係を構築しないといけない」と述べました。
講演後、西園寺先生を囲んで西堀正司・県日中副会長がコーディネーター役をつとめ、土屋龍一郎氏(元日本青年会議所会頭)と大月良則氏(県日中理事長・元県国際担当部長)をパネラーに、パネルディスカッションが行われました。(概略下記参照)
≪西園寺先生の講演「米中対立激化の中での日中関係・その現状と展望」 ≫
この数年世界はコロナ禍と米中対立に翻弄されてきた。コロナ禍は終息しつつあるが、米中対立は長く続くだろう。しかし核の時代にあって大国同士の大きな戦争は核戦争となり、人類の滅亡につながる。ウクライナを見ても米ロ戦争にはならない。ポストコロナは米中対立で回っていく。対立は続いても、米中戦争は起こらないだろう。人類史上ローマ帝国など大国強国が表れたが永遠に続くことはない。近代に入って世界の覇権を握っていた大英帝国も2度の大戦を経てアメリカにとってかわられた。米国の覇権もいつまでも続くわけではない。
世界はポスト冷戦の大変革期にある。米ソ冷戦がおわり世界はかえって無秩序になって紛争が多発している。米中対立を軸に動いている。対立は主として経済、貿易、ハイテク分野で激化している。トランプ時代は一国主義で貿易赤字問題が中心だった。バイデン時代になると、親米国家をまとめて中国に対抗しようとしている。仲間を作って中国を封じ込める戦略。「自由と民主主義」の価値観を同じくする国、「自由で開かれたインド太平洋」を標榜しアメリカを中心とした旧秩序を守る。一方どの国も経済グローバル化が進む中で、GDPの1位と2位の国が争ってもなんの益もなく、「三方一両損」の状態。日中貿易ばかりでなく、米中貿易、EUの対中貿易はどんなに制限しようとしても昨年史上最高を記録している。グローバル化した世界経済では部品も国境を越えている。産業のコメと言われる半導体6割は中国が買っていた。中国産は1割。組み立て分業。米のデカップリング政策でハーウェイやテンセントなどが攻撃されたが、半導体の原料のリン酸は中国が世界の70%を産出している。またレアアースも中国が90%を産出しており、これがなければハイテク産業も成り立たないし、兵器も作れない。半導体が外部からの輸入がストップしたら中国は自国で開発する。短期的に見れば中国は困るが、長期的に見れば自国で作り米国からの輸入が減ることになる。かつての、日米経済摩擦を振り返ってみると、紡績から車そしてコンピューター、半導体へと分野は変化していったが、アメリカを追い越すことは許さない。三菱が国産の次期戦闘機を開発することも許さなかった。
米中対立は貿易摩擦からハイテク分野の競争に移行してきている。米が中国を意識し始めたのは、中国製造2025戦略を打ち出したとき。産業のハイテク化(ハイテク化は軍事とも連動している)建国100周年の2049年には世界の先頭に立つとの目標をかかげた。「一帯一路」巨大経済圏構想、中国の宇宙開発計画(月面着陸)、中国版GPS(米のGPS覇権がくずれる)等々。イギリスの研究所の見込みでは2030年~33年に中国はアメリカを追い抜くと予測している。
日本の報道を見ると中国は孤立していると思われがちだが、アフリカ、中南米、アジア諸国など幅広い関係を持っている。これからは、日本はアメリカ一辺倒でなく頭を柔らかくして付き合っていく必要がある。国力は貿易だけで推し量れないが、世界の主要国は中国との貿易がトップを占めている国が多い。オーストラリアを見ても輸出の35%が中国向けで、対米輸出は6.3%というのが現実だ。
では中国は世界覇権を握ることができるのか?できないと思う。特定の強国が世界を牛耳ることはできない。核戦争に勝者はいない。露6.2千発、米5.5千発、中3.5百発--の核を持っているがこれを使ったら世界は破滅する。人類滅亡の可能性は、①核戦争、②強力なウイルス、③極端な気候変動、④環境と生態系の破壊の4つしかないだろう。
日中関係発展の上でODAによる対中借款は3兆円を超え、これは日本のODAの69%を占めるが、中国の発展に貢献した。主として円借款で中国はこれで日本の製品を購入した。中国の発展に伴い日中貿易も増えた。50年間で350倍になった。米中が仲良くしてもらうのが日本にとって最も好ましい。日本は国益を考えれば米中対立は望まない。
日本の戦後の対中政策を見ると岸内閣は経済交流を露骨に妨害した。池田内閣は経済民生重視政策で有名だが、対中政策も政経分離政策をとり、LT貿易など民間取り決めが結ばれ、民間の経済交流は盛んになった。佐藤内閣はこの流れを抑えるために日中貿易に輸出入銀行の融資を使わせない措置をとった。(吉田書簡)安倍内閣の政策は新政経分離政策と言われ、外交安保は日米同盟強化を基礎に価値観を同じくする国と連合し、中国封じ込めをおこない、経済的には対中協力を促進するというものだ。
「台湾有事」問題。安倍氏は「台湾有事は日本有事」と言った。台湾を巡る歴史を振り返ってみると、第2次大戦終了→米ソ冷戦スタート→国共内戦が始まるがこの時の国民党は430万の軍隊と米国の支援する豊富で優秀な武器を有し、一方の共産党は130万の粟を食べぼろをまとった軍隊で、ゲリラ戦を展開。米国は蒋介石を支援したが敗れた。朝鮮戦争をきっかけに対ソ防波堤としての役割を日本に求め、日本の民主化政策を反転させ、再軍備化に進んで行った。
台湾で戦争は起きるのか?台湾が独立宣言をすれば戦争になる。あるいは偶発的な衝突が引き金になる可能性はあるが、中国はアメリカと戦争をしたくない。米中台いずれも戦争を望まない。ウクライナになぜ米は直接介入しないのか。核戦争になることを恐れている。日本は米中のはざまでどのようなスタンスをとるべきか。中国包囲網の先頭に立つのではなく、外交的努力を傾けるべきと思う。双方とバランスの取れた、いい関係を構築しないといけない。
(文責編集部)
≪西園寺先生を囲むパネルディスカッション≫
 ◎西堀正司コーディネーター:それぞれの立場から中国との関わり、友好の思いなどを語っていただきたい。
◎西堀正司コーディネーター:それぞれの立場から中国との関わり、友好の思いなどを語っていただきたい。
◎土屋龍一郎氏は日本青年会議所会頭を務めていた時の経験を振り返り、「教科書問題の最中に訪中したが、街頭で中国の人々と心通う交流ができた。政治的なギクシャクがあっても国民同士交流を深めていくことが大切と思う」と語りました。
◎大月良則氏は「“飲水思源”の言葉を大切に、友好の先達の思いを継いで県日中友好協会理事長の役割を果たしていきたい。2010年の阿部知事の訪中に秘書課長として同行したが、当時尖閣問題直後で難しい時期であったが、全国の知事に先駆けて訪中したことは、良かったと思っている」と語りました。
◎西堀氏は「官民挙げての日中交流が大切と思う。コロナ禍や様々な障害があるが、平和友好の継続は、政府の意志の問題でもあり、民間の意志の問題でもある」と述べました。
◎西園寺先生は、「日中関係は世界的に見ても特異なものがある。民間交流が先行し、その後、国交正常化が実現した。ニクソン大統領の訪中前後の動き、中国の国連復帰など外的要因も大きかったが、国交正常化には、内的要因があった。石橋湛山、松村謙三、高碕達之助氏ら多くの先達が民間交流の積み上げ方式で努力してきた。また財界の期待も大変大きかった。当時と現在の困難をと比べると当時の方がもっと厳しかった」と述べました。
◎土屋:両国関係発展のためには、地方民間交流の柱になるものが必要と思う。
◎大月:交流の柱の一つとして、長野県は中国と40年にわたるスキー交流をおこなってきた。本年2月の北京冬季五輪のスキー競技は河北省の張家口市で開催された。新華社が40年間の交流を詳しく紹介した。今後も交流を続けていきたいし、インバウンド事業にもつながっていくと思う。
◎西堀:明治維新から敗戦まで77年、敗戦から本年まで77年になる。未来に向けての77年は2099年で21世紀末となる。日本と中国の付き合いの過去・現在・未来を顧みて、今を生きる我々は日中両国の平和友好のために努力していきたい。(文責編集部)
 長野県日中学術交流委員会は9月29日長野市内のホテル犀北館において定期総会を開催し、2021年度の活動報告と決算報告、各大学・短大等の学術交流報告を承認し、2022年度の活動方針と予算などを決定しました。総会には、信州大学、長野大学、県立大学、上田女子短大、県日中友好協会、ラジオ孔子学堂など関係者が出席しました。
長野県日中学術交流委員会は9月29日長野市内のホテル犀北館において定期総会を開催し、2021年度の活動報告と決算報告、各大学・短大等の学術交流報告を承認し、2022年度の活動方針と予算などを決定しました。総会には、信州大学、長野大学、県立大学、上田女子短大、県日中友好協会、ラジオ孔子学堂など関係者が出席しました。中村宗一郎会長(信州大学学長)は「本日は日中国交正常化50周年の記念日にあたる。この50年の間に中国は目覚ましい発展を遂げた。アカデミー分野でも学術論文数はアメリカに次いで2位となり日本は12位で追い抜かれてしまった。中国に学ぶべき点は多い。国際情勢は激動しているが、共存共栄で、世界平和を守っていきたいと多くの人は望んでいる。そのためには交流、特に学術分野の交流は大変重要と思う。コロナ禍のため困難が多いがオンラインなど工夫して交流を継続し進めていきたい」とあいさつしました。
席上、丹羽博彦県国際交流課主事と小池明上田女子短大学長、夏丹長野孔子学堂中国側責任者よりあいさつをいただきました。丹羽氏は、日ごろ日中学術交流や、留学生受入れに尽力していることに敬意を表した後、「コロナ禍で日中間の人的交流が制限されているが若い世代の交流・学生の交流は重要なので工夫して取り組んできた。昨年の東京五輪に際しては中国を相手国とするホストタウン事業としてオンラインで応援イベントを実施した。その際学生サポート登録を呼びかけ5大学の学生37名が研修講座や応援イベントに参加した。明年は長野県と河北省との友好提携40周年に当たるので、アフターコロナを見据えてトップの相互訪問や留学生交流等検討していきたい」と述べました。
小池学長は「コロナ禍やウクライナ等世界は激動している。米中の2極対立とともに世界は多極化しており、様々なプレーヤーがいる。偶発的な衝突を避けるために、草の根レベルの交流が必要で学術交流や民間交流が果たす潤滑油的なソフトパワーは貴重。特に学術交流の果たす役割は大きいので皆で努力していきたい」とあいさつしました。
夏丹女士は長野県日中友好協会ラジオ孔子学堂中国側責任者として来県したことを紹介するとともに、中国メディア大学と長野県立大学が縁あって今春交流協定を結び客員研究員としても活躍していきたいと述べました。また中国メディア大学の状況を紹介しました。
決定された活動方針では、コロナ禍で制約はあるが、各大学、短大の学術交流促進や連続市民講座、記念講演会、留学生支援などに取り組んでいくとしています。
総会議事終了後の意見交換では、出席者がそれぞれの立場から発言しました。布施正幸県日中友好協会副会長は、「コロナ禍や米中対立の激化によって、日中関係は困難な状況におかれているが、14億人の住む中国と安定した友好協力関係を維持発展させていくことは日本にとって重要な課題。それぞれの国にはそれぞれバイオリズムがあると言われる。日中国交正常化50周年を迎えたが、日中関係を破たんさせないために日中共同声明の原則を守り、交流を通じて理解と友好を深め、平和に貢献していきたい」と述べました。谷口眞由実県立大学教授は、古典文学を専門としている立場から、「中国から歴史的に文化的影響を受け深いかかわりがある。相互理解を深めていきたい」と述べました。米倉真一信州大学副学長は「近隣諸国との交流は大切。科学技術発展のために手を携えていきたい」と述べました。大月良則県日中理事長は「国同士はぎくしゃくしていても民間同士は仲良くしていきたい。明年は長野県と河北省との友好提携40周年を迎える。知事訪中などが計画されているので協力していきたい」と述べました。
 第25期日中関係を考える連続市民講座が11月27日からスタートしました。県内の大学と県日中友好協会などで作る県日中学術交流委員会主催で、毎月1回のペースで文化、歴史、経済関係などをテーマに計6回の講座が開かれます。
第25期日中関係を考える連続市民講座が11月27日からスタートしました。県内の大学と県日中友好協会などで作る県日中学術交流委員会主催で、毎月1回のペースで文化、歴史、経済関係などをテーマに計6回の講座が開かれます。
第1回は長野大学の塚瀬進教授が「辛亥革命110周年を迎えて―通説が見直される近年の研究動向―」と題して講演しました。当日は29名が熱心に受講しました
―清朝の改革や孫文の革命運動の実際の状況、西洋の影響(社会進化論の影響が強かった)、科挙廃止による影響、共和制の樹立と失敗・袁世凱の独裁などを紹介しながら、近代国家が持つ「領土・主権・国民」の3要素を創出する過程であったとし、かつては「革命」と「反革命」の2分法的な発想で辛亥革命を考察していたが、社会現象は2分法で割り切れない部分が大きく、皇帝専制政治体制が近代国民国家体制に変化するという、根本的かつ巨大な政治変動、社会変動の中で辛亥革命の意義を考察する研究が進められている―と語りました。講演終了後、出席者から活発な質問や意見が出されました。
連続市民講座の開催趣旨は次の通りです。
日中国交正常化から明年は50周年を迎えます。日中関係は新型コロナによる人的交流のストップ、米中対立の激化によって、経済、文化学術、スポーツなどの分野の交流においても困難が続いています。コロナ禍後を見据えて、日中共同声明の原点に返って両国国民の相互信頼関係を醸成していくことが望まれます。
詳細はこちら――>第25期日中関係を考える連続市民講座「中国の歴史・文化と日本」
 長野県日中学術交流委員会は8月3日長野市内のホテル犀北館において定期総会を開催し、2020年度の活動報告と決算報告、各大学・短大等の学術交流報告を承認し、2021年度の活動方針と予算などを決定しました。コロナ禍で制約はありますが、各大学、短大の学術交流促進や連続市民講座、記念講演会、留学生支援などに取り組んでいくとしています。総会には、信州大学、長野大学、県立大学、上田女子短大、県日中友好協会、ラジオ孔子学堂など関係者が出席しました。
長野県日中学術交流委員会は8月3日長野市内のホテル犀北館において定期総会を開催し、2020年度の活動報告と決算報告、各大学・短大等の学術交流報告を承認し、2021年度の活動方針と予算などを決定しました。コロナ禍で制約はありますが、各大学、短大の学術交流促進や連続市民講座、記念講演会、留学生支援などに取り組んでいくとしています。総会には、信州大学、長野大学、県立大学、上田女子短大、県日中友好協会、ラジオ孔子学堂など関係者が出席しました。濱田州博会長(信州大学学長)は「コロナ禍にあって、訪中も中断し日中間の交流がストップしていることは大変残念だ。相互に訪問して対面交流することは当面むずかしと思うが、オンラインでの交流等工夫していきたい。信州大では河北医科大学とオンライン会議を実施した。模索しながら交流再開に備えていきたい」とあいさつしました。
席上、小林一洋県国際交流課長と小池明上田女子短大学長よりあいさつをいただきました。小林課長は、日ごろ日中学術交流や、留学生受入れに尽力していることに敬意を表した後、「県としても河北省への留学生派遣事業や中国を相手国とする東京五輪ホストタウン事業に取り組んできた。大学生サポーターを募集したところ37人が登録し5回の講座を行い、8月2日にはオンラインで中国卓球選手の応援イベントを行った。多文化共生に取り組み、アフターコロナを見据えて留学生交流等再開していきたい」と述べました。
小池学長は「コロナ禍によって今までの価値観(の限界)があらわになってきている。中国のプレゼンスが大きくなっており米中対立が激化している中で中国の台頭に対する反発があるが、世論が一色になってしまうのはまずい。自己主張が無いといわれる日本人だが潤滑油的なソフトパワーは貴重。特に学術交流の果たす役割は大きいので皆で努力していきたい」とあいさつしました。
総会議事終了後の意見交換では、出席者がそれぞれの立場から発言しました。布施正幸県日中友好協会理事長は、「コロナ禍や米中対立の激化によって、日中関係は困難な状況におかれているが、14億人の住む中国と安定した友好協力関係を維持発展させていくことは日本にとって重要な課題。それぞれの国にはそれぞれバイオリズムがあると言われる。中国は巨大な変化を遂げているが、交流を通じて理解と友好を深め、平和に貢献していきたい」と述べました。

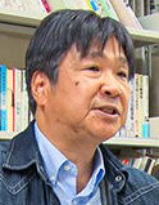 第24期第6回日中関係を考える連続市民講座が4月24日、日中友好センター教室において開かれ、松本大学教授で中国経済が専門の兼村智也先生が「コロナ禍によって変わる日中ビジネス」と題してオンラインで講演しました。コロナ禍の中でしたが、講座には12人が出席し熱心に聴講しました。
第24期第6回日中関係を考える連続市民講座が4月24日、日中友好センター教室において開かれ、松本大学教授で中国経済が専門の兼村智也先生が「コロナ禍によって変わる日中ビジネス」と題してオンラインで講演しました。コロナ禍の中でしたが、講座には12人が出席し熱心に聴講しました。兼村先生は、「コロナ禍の中で、マスクや防護服など医療関連物資の調達が滞るなどサプライチェーン(供給網)の寸断でモノの移動が止まる等中国依存度の高さが明かとなり、国同士の付き合い方を再検証する必要が指摘されている。また米中対立が激化している中で、アメリカのデカップリング政策に沿う形での開発や生産の”脱中国化”の動きが生まれており、二重に問題が提起されている。
中でも半導体メーカーを中国から引きはがす政策に力を入れているアメリカは台湾さらに日本を巻き込んでこの政策を進めようとしている。一方中国は14億の巨大市場をバックに、内需拡大で対抗しようとしている。このような中で、日系企業の対中ビジネス行動はどう変化しているか?
中国進出日系企業は”現状維持”の姿勢で、競争力のある日系企業にとって中国市場は依然として大きな魅力と考えられている。求められているのは中国拠点の自立化で、日本の本社と切り離した中国子会社内での資材・資金の運用の現地化が最大の経営課題となっている。
現地化がむずかしい理由としては人の入れ替わりが激しく定着しない、人材育成が難しいこと、日本企業はマニュアルでなく人を通じてノウハウや仕組みを移転していく体質があり現地に任せる覚悟が不足していること等があげられる。一方コロナ禍で日系企業の評価は雇用を守る等評価が高まっていて、良質な人材が集まる可能性も生まれている。人の現地化に成功した企業に見られる特徴としては、日本での就学・就業経験があり、日本の本社のことを知っていて本社社長との信頼関係があり、旺盛な企業家精神を持っていることなどがあげられる。
自立した拠点としての可能性を持っているのは、アジアの中でも中国・ベトナムのみ。日系企業が経営の現地化をはかるうえで適当な地域。日本国内企業は、一方で中国と一線を画したアメリカやアセアンとなどとのサプライチェーンを形成しつつ、もう一方で中国でのサプライチェーンにも足場を築くこと、両にらみの体制構築が有益ではないかと考える。」と指摘しました。
アセアンと中国との経済的結びつきやアセアン諸国の人件費の比較、ベトナムは人件費も上がり飽和状態に近づいていてサプライチェーンの上でも楽ではないこと、アジア最後のフロンティアミャンマーの事情などにも話が及び有意義な講座となりました。
第24期講座はこれで終了し、来期は11月からスタートする予定です。ご協力ありがとうございました。
 第24期第5回日中関係を考える連続市民講座が3月13日、日中友好センター教室において開かれ、信州大学人文学部准教授の豊岡康史先生が「清朝中期の対外政策:「独裁」の実態・歴史の亡霊」と題して講演しました。コロナ禍の中でしたが、講座には21人が出席し熱心に聴講しました。
第24期第5回日中関係を考える連続市民講座が3月13日、日中友好センター教室において開かれ、信州大学人文学部准教授の豊岡康史先生が「清朝中期の対外政策:「独裁」の実態・歴史の亡霊」と題して講演しました。コロナ禍の中でしたが、講座には21人が出席し熱心に聴講しました。豊岡先生は、「ここ数年、中国(あるいはロシア・トルコなどの旧近世帝国の後継国家)に関して、元首による「独裁」、いわば歴史の逆行を問題視する言説が見受けられる。その当否はさておき、実際に前近代帝国において「独裁」はいかに行われていたのだろうか?清朝中期(18世紀~19世紀前半)の政策決定のあり方について、制度・具体的ケースを取り上げて話したい。」と述べ、清朝漢地の政策決定機構について解説し、更に1808年のイギリス軍のマカオ上陸事件がどのように処理されたかを紹介しました。
「結論的に言えば、清朝における「独裁」とは、重要な書類は皇帝が決裁しているけれども、政策策定は皇帝を補佐する少数の上級官僚が行っていた。その政策内容は、マジョリティである漢地・漢人(大多数を占める漢民族)に配慮したパフォーマンスに満ちたものになっていた。その意味では、皇帝が好き勝手に権力を振るう、というイメージとはかけ離れていたと言える。さらに、その政策内容は、ときに外国からは超時代的で自己中心的な「中華思想」そのものとされてきたが(「中華思想」は実際には1936年和田清らが日本の中国侵略の理由づけのために作り上げた虚像であった)、実際には柔軟な(あるいは”弱腰”な)判断を下すこともあり、むしろ諸外国の認識は表面的なパフォーマンスにとらわれてしまっているともいえる。」と指摘しました。
現代中国との比較の角度からも興味深いお話でした。
次回の第6回講座は、4月24日(土)、兼村智也・松本大学教授が「コロナ禍によって変わる日中ビジネス」をテーマに講演します。
 第24期第4回日中関係を考える連続市民講座が2月20日、日中友好センター教室において開かれ、中国文学専門で長野県立大学教授の谷口真由実先生が「漢詩のユーモア 杜甫・李白・白居易・蘇軾を中心に」と題して講演しました。コロナ禍の中でしたが、講座には39人が出席し熱心に聴講しました。
第24期第4回日中関係を考える連続市民講座が2月20日、日中友好センター教室において開かれ、中国文学専門で長野県立大学教授の谷口真由実先生が「漢詩のユーモア 杜甫・李白・白居易・蘇軾を中心に」と題して講演しました。コロナ禍の中でしたが、講座には39人が出席し熱心に聴講しました。谷口先生は、「風刺は対象を見下す視点に立つが、ユーモア(諧謔)は自身を含めて対等に見る親しみ深い視線を特徴とする」とし、後漢末期から唐・宋に至る著名な詩人(ほとんど官吏・政治家でもあった)を取り上げ、その生きた時代背景も紹介しながら、現実の不条理や人間共通の弱点をおおらかに面白がり現代の人々をも共鳴させる作品が生まれたことをわかりやすく話しました。―
◎「竹林の七賢」は激動の血に彩られた時代に、限りある自己の生をより十全に生き抜こうとし、世間的価値観の呪縛を脱して私の流儀で固有な運命を選びとろうとした。厳しいい言論統制の中を生き抜いていく知恵とユーモアが見て取れる。彼らは誰よりもよく笑い、また目が眩むほど憤り得た。陶淵明は下級官吏を辞し、酒をこよなく愛し、自然を楽しみ、詩を作り悠々自適な生活を送った。
◎盛唐の詩人、杜甫は安史の乱や朝廷内部の政争など政情不安の時代を生き、社会詩人と評される。政治・社会の矛盾を鋭いまなざしでとらえ直截に表現した社会批判詩を多数作っている。一方で、「飲中八仙歌」などでは戯れに自身や友の姿を滑稽に描いた詩もみられる。曲江の酒家に立ち寄り、憂さを晴らす詩も作っている。人の世は乱で荒れ果てても自然は悠然としているとうたう。また杜甫には珍しくデカダンの詩もある。成都の草堂にあっては秋の暴風で吹き飛ばされた粗末な家にあって千万間の広い部屋に貧しい人々がつどい笑いあうことを夢想する詩もみられる・・・
◎李白は盛唐の代表的な詩人で杜甫より11歳上。その詩は天衣無縫、自由闊達で「詩仙」と称された。「月下独酌」では名月を迎え影に対して3人となる、行楽すべからく春に及ぶべし・・言葉遊びや擬人法が見られる。杜甫は李白を一斗詩百編と評した。李白の多くの詩文は酒にちなむものが多く、ユーモアや比喩にあふれたものが多い。
◎白居易は中唐の代表的詩人、地方官吏の家に生まれたが優秀な成績で進士に合格、中央政界で活躍するも、左遷などを体験した。平易な用語でわかりやすい詩を意識的に制作した。風諭詩(婉曲な政治批判の詩)、閑適詩(静かに自然を楽しむ詩)、感傷詩(男女の愛情を描く詩)に分類し、『白氏文集』を編集し、平安文学に大きな影響を与えた。「白鷺」は罪を得て流されていく道中の詩であるが笑いで包んでいる。「重題」では廬山こそはうるさい名誉心からの逃避場所であり、司馬というつまらぬ官職も隠居役としてはなかなかいい、とうたう。
◎蘇軾は北宋の詩人、進士に合格したが新法・旧法の争いに巻き込まれ、海南島に流されたこともある。「海内に知己あれば天涯も比隣の如し」は有名な句。比喩表現や比較(なぞらえる)、典故(古典からの出典)、詩語(畳韻語)の面白さがある。―
まとめとして、「ユーモアは遊びの精神に基づくが、単なる笑いではなく、政治の世界でのつまずきに遭遇した作者の苦しみの中から生み出された。自己の内省を経て、自身の弱さやダメぶりを認め、それを、滑稽・諧謔的な言葉で表現している。作者は、ユーモアを表現することによって、逆境の苦しみを打破する起爆剤としている。それゆえ、読者に困難な現実に向き合う力を与えてくれるのではないか」先生の結びの言葉に、共感の拍手が送られました。
次回の第5回講座は、3月13日(土)、豊岡康史・信州大学人文学部准教授が「清朝の対外政策の決定方法と現代中国」をテーマに講演します。
 第24期第3回日中関係を考える連続市民講座が1月23日、日中友好センター教室において開催され、米国の社会経済事情に詳しい上田女子短期大学の小池明学長(経済学、金融論)が「米大統領選と米中対立に想う」と題してオンラインで講演しました。コロナ禍の中でしたが、講座には19人が出席し熱心に聴講しました。
第24期第3回日中関係を考える連続市民講座が1月23日、日中友好センター教室において開催され、米国の社会経済事情に詳しい上田女子短期大学の小池明学長(経済学、金融論)が「米大統領選と米中対立に想う」と題してオンラインで講演しました。コロナ禍の中でしたが、講座には19人が出席し熱心に聴講しました。小池先生は、過去10年間の米国と中国の主な出来事を振り返った後、米国事情、米中関係、日本の取るべき道などについて話しました。(概略下記参照)
―米ソ冷戦時代には米国には中国を引き寄せるべきだとの思いがあり、WTOなどへの加盟によって世界標準に近づいて民主化も進むだろうとの思いがあった。もちろん14億の人口・市場に対する関心もあった。中国はこの10年間成長を続け現在世界のビッグプレーヤーとして存在感を増している。米国は中国を次第に警戒し対抗する政策をとるようになった。
トランプ前大統領の任期中に米国社会の分断が広がった。南北戦争でも同じだが今後、分断解消に相応の時間がかかるだろう。バイデン新大統領は対話を重要視した政治を進めていくとみられる。
一方、対中政策についてはバイデンはトランプとは違って中国寄りとの見方もあるが、米国の世論が強硬論を支持しており、トランプとの対抗上強硬なことを言った。急激に融和策へとかじを切り直すことはないだろう。競争対立関係は変わらないが、妥協できることは建設的にやっていこうとするだろう。
日本は、米国寄りの立ち位置だが、中国との歴史的、経済的関係の大きさを考えれば安定的な関係を築く努力が求められている。正当なことを主張しつつ見返りも用意し交渉の材料を持つことが必要だ。―
興味深い内容でメモを取りながら真剣に聞き入りました。オンラインによる講演は初めての試みでしたが、今後より改善して、交流機会を作っていきたいと思います。次回は2月20日(土)谷口眞由実・県立大学教授が「漢詩のユーモア--李白・杜甫・白居易・蘇軾を中心に」をテーマに講演します。
主語と動詞をはっきりさせる中国語と主語と動詞があいまいな日本語の特徴に触れた後、日常のあいさつと配偶者の呼称、漢字から見た古代女性の社会的地位、老子・孔子・荘子・孟子など古代思想家が中国語と中国文化に与えた影響、詩詞が中国語と中国文化を豊かにしたこと、中国の4大名作と4大奇書(「三国志演義」「西遊記」「水滸伝」「金瓶梅」が4大奇書と言われていたが、「金瓶梅」の代わりに「紅楼夢」を加えたものが4大名作と呼ばれるようになった)へと話が進みました。
更に、『漢委奴国王』(紀元1世紀、後漢の光武帝が日本の奴国王に与えたと「後漢書」に記されている「漢の倭奴国王」)金印と漢字の日本伝来、明代にイタリア人宣教師マテオ・リッチが漢字をローマ字表記することをはじめ、これが、現代中国で広く使われている「漢語ピンイン法案」へとつながっていったこと等興味深い話が続きました。また、明治期には革命、科学、共和、哲学、自由など多くの社会科学用語などが日本から中国に逆輸入されたこと、峠や辻、切符、切手などは和製漢字単語であることも紹介されました。玉や紅が好きな中国人、気の毒な犬、四君子と尊ばれる「梅・蘭・竹・菊」など話は中国文化に幅広く及び講義時間もあっという間に過ぎました。
第24期日中関係を考える連続市民講座が11月21日から始まりました。県内の大学と県日中友好協会などで作る県日中学術交流委員会主催で、毎月1回のペースで文化、歴史、経済関係などをテーマに計6回の講座が開かれます。
第1回は長野大学の塚瀬進教授が「中国における歴史教育の特徴と問題点」と題して講演しました。自身が中国近現代史を研究している立場から、中国人がどのような歴史認識の中にいるのか知ることなしには中国人研究者の研究論文を深く理解することができないとの問題意識に立って、①中国の歴史教育の特徴、②歴史教科書の制度的変遷、③一般的な中国人の近代以降の歴史観、④日中戦争についての記述、⑤歴史認識の相違などについて語りました。講演終了後、出席者から活発な質問や意見が出されました。
主催者はコロナ禍の平穏化を願いつつ、皆さんの協力を得ながら講座を進めていきたいと述べていました。第2回は12月19日、王秋菊・清泉女学院短大中国語講師が「中国語と日本語-日中文化比較」とのテーマで講演します。
-戦後75年、日中国交正常化から48年を経過し、日中関係の改善加速が期待された中でしたが、新型コロナの世界的感染拡大によって、人的交流がストップし、経済、文化学術、スポーツなどの分野の交流においても困難が続いています。早期の平穏化を願いつつ、コロナ禍後を見据えて、両国国民の相互信頼関係を醸成していくことが望まれます。 歴史的に深いかかわりを持ち、日本の最大の貿易相手国である中国はGDP第2位の経済大国となり巨大な変化を遂げています。14億人が住む隣国中国に対する理解を深めることは日本にとって一層重要となっています。中国を多面的に理解するため県内で活躍している大学・短大などの先生を講師に迎え第24期講座を計画しました。お誘いあってご参加ください。
詳細はこちら――>第24期日中関係を考える連続市民講座「中国の歴史・文化と日本」
第2回は12月19日(土)王秋菊・清泉女学院短大中国語講師が中国語と日本語・文化比較について話します。
第3回は1月23日(土)小池明・上田女子短大学長が米大統領選と米中対立について話します。
第4回は2月20日(土)谷口眞由実・県立大学教授が漢詩のユーモアについて話します。
第5回は3月13日(土)豊岡康史・信州大学准教授が清朝の対外政策決定方と現代中国について話します。
第6回は4月24日(土)兼村智也・松本大学教授がコロナ禍で変わる日中ビジネスについて話します。
濱田州博会長(信州大学学長)は「コロナ禍にあって5月の日中学長会議が延期となるなど、日中間の交流がストップしていることは大変残念だ。信州大では留学生が大勢いるが実験実習などができず困っている。一方協定を結んでいる大学からマスクの寄贈があった。相互に訪問して対面交流することは当面むずかしと思うが、オンラインでの交流等工夫していきたい。再開に備えて準備していきましょう」とあいさつしました。
席上、宮原茂県国際担当部長と西堀正司県日中友好協会副会長よりあいさつをいただきました。宮原部長は「長野県として上海駐在員に加えて新たに北京駐在員を増やす方向で準備している。昨年は中国要人の来県や知事訪中も実現した。国同士の関係は難しい面もあるが、地方民間交流をしっかり進めていきたい。中国を相手国とする東京五輪ホストタウン事業には大学生の皆さんにも参加いただきたい」と述べました。西堀副会長は「コロナ禍で諸交流がストップして、友好協会70周年記念活動も延期となっている。習近平主席の4月訪日も延期となったが、友好協会は引き続き国賓としての来日を歓迎することを決めた。中米対立の激化は人々の憂うるところだが、日本はバランスをとって役割を発揮してもらいたい」とあいさつしました。
 長野県日中学術交流委員会の主催で、11月23日長野県日中友好センター教室において第23期第1回講座が開かれました。講師は長野県立大学の谷口眞由実教授、演題は「”令和”と『文選』-万葉歌人と漢文学-」でした。
長野県日中学術交流委員会の主催で、11月23日長野県日中友好センター教室において第23期第1回講座が開かれました。講師は長野県立大学の谷口眞由実教授、演題は「”令和”と『文選』-万葉歌人と漢文学-」でした。
谷口先生は唐詩が専門だそうですが、大宰府のトップ(大宰帥)の座にあった大伴旅人(おおとものたびと)の邸宅で観梅の宴が催され、そのとき読まれた和歌を収めた万葉集巻5梅花の歌32首の序が原典となっていることやそれに影響を与えた王義之などについて詳細に解説しました。旅人は漢文学の造詣が深く、九州の地(体のよい追放)にあって、世俗を超越する心境から東晋の書家(将軍)王義之に心を寄せ、その『蘭亭集序』(曲水の宴での41人の詩集の序)や『文選』巻15・後漢の張衡『帰田賦』などを深く会得していたこと等を説明いただきました。万葉歌人と漢文学の深いつながりの中から「令和」が生まれたことを知り、悠久な日本と中国の文化交流の歴史を改めて理解することができました。
なお、この日中関係を考える連続市民講座は中国を多面的に理解するために県内で活躍している大学・短大等の先生を講師に迎え開催されてきました。歴史的に深いかかわりを持ち、日本の最大の貿易相手国である中国は巨大な変化を遂げ、GDP第2位の経済大国となりました。14億人が住む隣国中国に対する関心を持ち理解を深めることは日本にとって一層重要となっています。
高波謙二・県日中友好協会会長が主催者を代表して、「本年、中華人民共和国建国70周年を迎えた。中国は急速な変化と発展を遂げ、国際社会における比重を高めており、日中の貿易額も対米貿易を大きく引き離して、往復33兆円を記録した。日中関係は21世紀に入って歴史認識問題、尖閣問題によって困難な状況が続いてきたが、昨年の両国首脳の相互訪問、首脳会談によって好転し、正常な軌道に戻った。このチャンスを活かし、長期的視点で安定した日中関係を築いていきたい。宮本雄二先生を講師に迎え、平和で安定した日中関係を築くためにはどうしたらよいかをともに考えたい」とあいさつしました。
宮本先生は冒頭、長野県が(開拓団送出日本一の)歴史を踏まえ中国との関係を大切にし草の根から友好関係が出来上がってきたことにかねがね敬意を抱いてきたと述べ、大使在任中に方正の日本人公募を参拝したこと等も紹介したうえで、これから中国とどう付き合うかについてわかりやすく、深い洞察に富むお話をしていただきました。(概略下記参照)
――将来の日中関係を考える上で、なぜ日本が中国侵略に始まる対米戦争という過ちを犯したのか総括する必要がある。かつて日本は中国のナショナリズムを過少評価し、対中侵略を進め更に全く展望のない対米戦争まで突き進んでしまった。第1次世界大戦後の平和構築に向けた世界の大きな流れを見ることに失敗した。これから中国とどう付き合うかを考える上で、このことをしっかり押さえておく必要がある。
中国の発展は目覚ましくGDPで今や日本の約3倍規模になっておりやがて米国を追い抜くだろうが、中国がダントツの1位になることはないだろう。世界は多極化の時代に入っており、中国は経済では自由貿易を、国際政治では常任理事国として国連憲章に基づく国際的なルールを支持している。その点で、大きな方向で中国と日本は一致している。そこを突破口に政治、経済の国際的枠組みを日中がともに支え、強化することを全面的に打ち出すべきだ。中国は変わり続けており、中国共産党の統治力や変わる力に注目すべきだ。今までこうだったという固定観念は捨てたほうが良い。日中は共通の言葉を持つに到った。
日中関係を考える上で、中国人の対日観が急速に変わってきている。訪日観光客の増加やスマホなどを通じて日本に対する好感度がアップしてきている。両国の歴史認識問題については以前は大きな障害だったが世代交代が進み脇における時代になった。閣僚らによる靖国参拝など日本がきっかけを作らなければ問題は起こらないと思う。過去の歴史より、改革開放の実績と今後の中国の発展を自信をもって進んでいける状況が生まれ、対日観も客観性を持つようになった。
米中関係が激化している。アメリカは自分に追いつき追い越そうとする国が出現するのは面白くない。かつてソ連、次に日本がバッシングの対象になった。経済、軍事・安全保障面で、アメリカは中国の台頭を押さえつけようとしている。軍事・安全保障面では軍人は最悪を想定して相手を過大評価し軍拡→戦争と進んでいってしまう傾向がある。中国人は考えている最中だが、冷静に考えれば中国を攻める国はない。軍事力に頼ることなく、自由貿易、国連強化などソフトパワーをもって、安全と尊厳を守ることが賢明であることは言うまでもない。日本は米中を衝突させない役割があり、貢献できるのではないか。
日中関係は国民の信頼関係が低下していると言われるが、一番関係が悪化したときでも10%すなわち1200万人の日本人が中国が好きとの世論調査結果だった。国民同士の交流を通じて等身大の中国を理解することによって両国関係は安定する。号令一下右向け右という中国人はいない。中国人は「義」の価値観が一番強いように思う。中国人は道理が無ければ従わない。留学生に温かく接し、日中関係を大切にしたい。今後の日中関係を考えるとき、一番心配なのは日本の若い世代が中国との関係にあまり関心を持っていないこと。日本にとって中国の重要性は年々増している。中国とどう付き合うか、自分たちの問題として考えてほしい。――
講演後、宮本先生を囲んで濱田州博信州大学学長をパネラーに、西堀正司・県日中理事長がコーディネーター役をつとめ、パネルディスカッションが行われました。参加者は熱心に耳を傾けました。
第2部の祝賀パーティーでは、高波県日中会長、濱田県日中学術交流委員会会長のあいさつに続き、花岡徹県国際担当部長、太田昌孝(代)・井出庸生(代)衆議院議員、小松裕(県卓球連盟会長)・若林健太前国会議員の祝辞の後、犛山典生県経営者協会事務局長の音頭で乾杯しなごやかに懇談交流しました。また高橋要長野市商工観光部長、大月良則県健康福祉部長、樋代章平八十二銀行常務執行役員、根橋幸夫県国際課長、岡村重信県プロフェッショナル人材戦略拠点事務局長、埋橋茂人県議(代)、李妮県国際交流員、娜日蘇長野市国際交流員、石家庄市研修員の魏薇・王瑶さんらからも祝辞をいただきました。また長野ラジオ孔子学堂のフルス教室のメンバーが日ごろの練習成果を発表し、研修生や女性会員らが「北国の春」や「ふるさと」などを披露し拍手を浴びました。王昌勝県華僑総会会長が締めのあいさつを行い、盛り上がりの中懇親会が終了しました。
 長野県日中学術交流委員会は8月8日、長野市内のホテル信濃路において2016年度総会を開きました。引き続き日中学術交流を促進していくことを決めた他、信州大学や長野大学、県短期大学、上田女子短大など中国との学術協定や学術交流、留学生受け入れなどの現状なども報告されました。また、第20期日中関係を考える連続市民講座や長野県日中友好協会創立60周年記念事業に協力していくことが決定されました。
長野県日中学術交流委員会は8月8日、長野市内のホテル信濃路において2016年度総会を開きました。引き続き日中学術交流を促進していくことを決めた他、信州大学や長野大学、県短期大学、上田女子短大など中国との学術協定や学術交流、留学生受け入れなどの現状なども報告されました。また、第20期日中関係を考える連続市民講座や長野県日中友好協会創立60周年記念事業に協力していくことが決定されました。濱田州博会長は、「日中関係は難しい問題を抱えているが、長野県は、民間レベルで中国と深い結びつきがあり交流も盛んだ。(出身の)信州大学繊維学部でも留学生受け入れなど交流が行われている。引き続き、民間学術交流に力を入れ中国との積極的な学術交流を継続していきたい。」と述べました。
来賓として高波謙二県日中友好協会会長が日ごろの協力に対し感謝た後、日中関係の重要性と長野県と河北省の交流状況などに触れ、本年が県協会創立60周年にあたり引き続き平和友好に努めていきたいとのべ、「文化学術交流は両国の平和友好関係を持続発展させていく大切な役割を果たしてきた。一層のご活躍を祈ります」とあいさつしました。
山本晋司県国際課長は、長野県が河北省はじめとした中国との交流に力を入れている様子を紹介し、学術交流は地味ではあるが日中関係を支える大切な役割を果たしていると述べ今後の活躍を期待しました。上條宏之県短期大学学長は「中国国際放送局や河北大学と友好関係があり、学生が訪問して交流する機会も増えている。いろいろな交流を重ねていきたい」とあいさつしました。
総会では2015年度の事業報告・決算報告を承認した後、2016年度の事業方針・予算を採択しました。
終了後、立石昌広県短期大学教授が、「中国の”新常態”」と題して講演しました。
第19期日中関係を考える連続市民講座スタート(11/28)
第19期日中関係を考える連続市民講座が11月28日から始まりました。県内の大学と県日中友好協会などで作る県日中学術交流 委員会主催で、毎月1回のペースで文化、歴史、経済関係などをテーマに計6回の講座が開かれます。第1回は長野大学の塚瀬進教授が「溥儀の生涯とその時代」と題してラストエンペラーの生きた激動の時代とその人を紹介しました。第2回は立石昌弘・県短期大学教授(中国経済)が「1930年代の中国と日本」と題して講演しました。
委員会主催で、毎月1回のペースで文化、歴史、経済関係などをテーマに計6回の講座が開かれます。第1回は長野大学の塚瀬進教授が「溥儀の生涯とその時代」と題してラストエンペラーの生きた激動の時代とその人を紹介しました。第2回は立石昌弘・県短期大学教授(中国経済)が「1930年代の中国と日本」と題して講演しました。
--日中両国は2000年の友好往来に裏打ちされた文化の共通性があります。一方、近代不幸な戦争を体験しています。国交正常化以来40数年を経過し、最大の貿易相手国となっています。ここ数年、政治的ギクシャクが続いてきましたが、日中関係は徐々に明るさを取り戻しつつあります。英知をかたむけ、平和と友好協力の道を歩む方途を探すことは両国国民にとって大切な課題です。中国を多面的に理解するため県内で活躍している大学・短大などの先生を講師に迎え第19期講座を計画しました。お誘いあってご参加ください。
詳細はこちら――>第19期日中関係を考える連続市民講座「中国の歴史・文化と日本」
11/28(土)「溥儀(ラストエンペラー)の生涯とその時代」、塚瀬進・長野大学教授
12/19(土)「1930年代の中国と日本」、立石昌弘・県短期大学教授(中国経済)
1/23(土)「中国茶あれこれ」、王秀閣・中国国際放送局日本語部アナウンサー・長野孔子学堂責任者
2/27(土)「中国近世小説の世界『杜騙新書』の話」、氏岡真士・信州大学人文学部准教授
3/19(土)「中国進出県内企業の現状」、兼村智也・松本大学教授
4/23(土)「宋代中国の都城と文化」、久保田和夫・長野高専教授
丹羽宇一郎・前中国大使招き、日中友好協会創立65周年記念の講演会を開催(10/9)2015

 長野県日中友好協会・県日中経済交流促進協議会・県日中学術交流委員会は10月9日、戦後70年、日中友好協会創立65周年にあたり講演と記念のつどいを長野市内のホテル犀北館で開きました。講演会には、180名が出席。尖閣問題のさなか中国大使として厳しい日中関係の最前線にあって両国関係の破滅を避けるため全力を傾注された、丹羽宇一郎先生(日中友好協会全国会長)が、「戦後70年、中国の行方と日中関係の今後」と題して記念講演しました。その後、先生を囲んでパネルディスカッションがおこなわれました。「厳しい日中関係を打開し新たな扉を開くために」、ともに考え前向きに民間交流を進めていこうとする熱意あふれる有意義な1日となりました。
長野県日中友好協会・県日中経済交流促進協議会・県日中学術交流委員会は10月9日、戦後70年、日中友好協会創立65周年にあたり講演と記念のつどいを長野市内のホテル犀北館で開きました。講演会には、180名が出席。尖閣問題のさなか中国大使として厳しい日中関係の最前線にあって両国関係の破滅を避けるため全力を傾注された、丹羽宇一郎先生(日中友好協会全国会長)が、「戦後70年、中国の行方と日中関係の今後」と題して記念講演しました。その後、先生を囲んでパネルディスカッションがおこなわれました。「厳しい日中関係を打開し新たな扉を開くために」、ともに考え前向きに民間交流を進めていこうとする熱意あふれる有意義な1日となりました。
夏目潔・県日中経済交流促進協議会会長の開会のあいさつに続き、高波謙二・県日中友好協会会長が主催者を代表して「日中友好協会は65年前、日中戦争の深い反省の上に、両国の不再戦、平和友好を誓って国民の期待を担って誕生した。全国でもっとも多くの満蒙開拓団を送り出した長野県は負の歴史を肝に銘じ教訓として友好関係を築く決意をした。粘り強く民間・地方の交流を続け、友好に資していきたい。大使在任中、中国全土を自分の目で視察され、政府高官はもとより、庶民の方とも交流を深め現場主義を貫かれた丹羽先生から得がたい体験に裏打ちされた貴重なお話をお聞きし、今後の糧としていきたい」とあいさつしました。
丹羽先生は冒頭、習近平主席とも大使在任中9回あったことがあり習氏が「日中は引越しのできない間柄で、仲良く付き合っていく以外に道はない」と言っていたことを紹介しました。「日中双方の世論調査では、嫌中や日本人が怖いなどの数字が8割を超えるなど、政府間だけでなく民間でも厳しい。交流の機会を増やし誤解を解いていく必要がある。同じ人間としてお互いに信頼しあったら日中間でも過去の歴史を乗り越えて偏見をなくしていくことができる」と強調し、日中間の全ての紛争を平和的手段で解決し、武力や武力による威嚇に訴えないと定めた1972年の日中共同声明に触れ、「声明の精神を両国が遵守するよう努力するべきだ」と訴えました。
また9月の米中首脳会談に触れ日本人が大きくなった中国を理解すべきだと述べました。日本で余り報道されていないが、米中首脳会談では安全保障や経済連携などが広範に議論され、両国は2016年を「米中観光年」にすることで合意したことを紹介。さらに「オバマ大統領は2020年までに米国人学生100万人強に中国語を学ばせると宣言した。日本が尖閣問題でごちゃごちゃやっている間に、中国は日本を必要とせず米国と関係を深めるようになってしまう」と指摘しました。
先生は、日本の戦争責任や、日中国交正常化のために先人が払った努力が忘れ去られつつあるとも懸念。「国交正常化移行の40年余りで10億ドルだった日中の貿易額が3300億ドルまでになったのは両国が平和だったからだ。戦争に近づくようなことはやるべきでない」と強調しました。
最後に中国の習近平体制に触れ、「習氏は自信を持って国政にあたっており中国経済は崩壊しない。当面中国共産党の1党独裁体制以外ありえないが、21世紀半ばの建国100周年に向けた長期構想を持ちさまざまな課題を解決しようとしている。ちなみに2017年は習体制2期目になるが、日中国交正常化45周年にもなる。大使のとき40周年記念行事600件もが、中止になり本当に悔しかった。45周年は是非成功させたい」と講演を締めくくりました。
講演後、丹羽先生を囲んで上條宏之・県日中学術交流委員会副会長(県短期大学学長)、山根敏郎・長野市日中友好協会会長をパネラーに、西堀正司・県日中理事長がコーディネーター役をつとめ、パネルディスカッションが行われました。
県内各地から集まった聴衆は熱心に耳をかたむけ、時代の変化や国際環境の変化を踏まえ日中が真剣に向かい合い相手を理解し、両国関係を改善し、関係を深めていく必要性を心に刻みました。「まず一歩踏み出すこと」を信条とする先生の情熱に大いに刺激を受けたと感想を語っていました。
第2部の祝賀パーティーでは、相澤孝夫・副会長(松本日中会長)の開会あいさつに続き、高波会長が「”隣人同士仲良く付き合っていきたい。その為にもてる力を発揮したい”との丹羽先生の信念に貫かれた講演に感動した。日中関係が徐々に明るさを取り戻しつつある中で、集いの成果を踏まえて民間交流を進めていきたい」と語りました。中島恵理県副知事、井出庸生代議士、若林健太参議院議員からの祝辞に続いて、村石正郎・県議会日中友好促進議員連盟会長の乾杯の音頭で懇親会に入りました。小松裕・代議士(代)、小坂憲次・参議院議員(代)、今井正子・高島陽子県会議員、朱丹陽・王秀閣・中国国際放送局長野孔子学堂担当、董彤・県国際交流員、王昌勝・県華僑総会会長、塚田佐・元長野市長らから祝辞をいただきました。また、小林勝人・飯田日中理事長から満蒙開拓平和記念館の現状報告がされました。また女性委員会メンバーなどから日本と中国の歌が披露され、和やかな交流がおこなわれました。
岡本宜樹・日本銀行松本支店長、滝沢英一・県国際課課長補佐、銭坂丈夫・上田市秘書課、柳澤直・樹山ノ内町副町長、岡村重信・県経営者協会事務局長、西村昌二・県中小企業団体中央会参事、中村英雄・県商工会連合会専務理事、荒井英彦・県信用保証協会会長、奥村明子・ジェトロ長野所長、高木幸一郎・JA全農県本部長、北村智JA長野中央会地域農政部部長、後藤正幸・信濃教育会会長、嶋田力夫・長野学園理事長、手塚久雄・信州大学国際交流課長、井口弥寿彦・信濃毎日新聞社総務局長、小沢吉則・長野経済研究所調査部長、桜井啓司・県武術太極拳連盟会長、など各界来賓が出席しました。
山沢清人会長は、「日中関係は政治的ギクシャクが続いたがだんだんと明るさが見えてきた。長野県は、民間レベルで中国と深い結びつきがある。引き続き、民間学術交流に力を入れることが大切と思う。中国との積極的な学術交流を継続していきたい」と述べました。
来賓として高波謙二県日中友好協会会長が「文化学術交流は政治的ギクシャクがあっても両国の平和友好関係を持続発展させていく大切な役割を果たしてきた。一層のご活躍を祈ります」とあいさつしました。
上條宏之県短期大学学長は「中国国際放送局や河北大学と友好関係があり、学生が訪問して交流する機会も増えている。いろいろな交流を重ねていきたい」とあいさつ。小池明上田女子短大学長は「日中間には政治レベルのギクシャクがあるが、いろいろな民間レベルの交流もある。草の根レベルの交流が大切。大切な隣国中国とはいろいろなネットワークを生かして付き合って行きたい」と述べました。
総会では2014年度の事業報告・決算報告を承認した後、2015年度の事業方針・予算を採択しました。
終了後、西堀正司県日中友好協会理事長(日中友好協会全国専務理事)が、「戦後70年・日中友好協会創立65周年、日中関係の現状と課題」と題して講演しました。
 県日中学術交流委員会主催の第18期日中関係を考える連続市民講座で2月21日中国国際放送局・長野ラジオ孔子学堂の朱丹陽さんが講演しました。
県日中学術交流委員会主催の第18期日中関係を考える連続市民講座で2月21日中国国際放送局・長野ラジオ孔子学堂の朱丹陽さんが講演しました。演題は「言葉でつながる日本と中国・ひつじ年と現代中国事情」。春節を迎えて、旧年を追い払う爆竹の由来や赤が魔よけの意味を持つこと、春節の慣わしなど中国の伝統文化を理解するのに役立ちました。また日本でもおなじみのひつじにちなんだ四文字熟語など興味深いお話をしていただきました。昨年の中国十大ニュースの画像を交えての紹介もわかりやすく好評でした。
さすが文字の国、歴史伝統の国と思われる話を、いくつか取り上げてみましょう。
①未年ににぴったりの新年のあいさつは「三陽開泰」(未年には「三羊開泰」とも言う)。
・「三陽」は三つの陽気。「易経」によると、旧暦11月の冬至から昼がだんだん長くなることから、「冬至」は初の「陽気」、続きの12月は二番目の「陽気」、お正月は三番目の「陽気」なことから、「三陽」。「泰」は「平穏、安定」の意味。「陽」が三つ目まで来たら、厳しい冬も乗り越え、待ち遠しい春が訪れます。
②春節の慣わしもしっかり決まっているのです。
初一(元旦):元は1年の初日、春の初日。
鶏の日 鶏の絵や切り紙などを飾る。早朝に爆竹を鳴らす。年始回りをする。黄色と白のお餅を食べる(黄色は黄金、白は白銀)。箒(ほうき)の誕生日。お年玉(押歳銭)。
初二 犬の日特に店はえびす、福の神(趙公明 関羽)祭る。
初三 羊の日玄関に飾った門松と門神紙を焼いて、人々各自平常の暮らしに戻る。口げんかになりやすい日とされ、年始回り禁止。
初四 豚の日 かまどの神をはじめ神々が天から戻る日。・爆竹を鳴らしたり、美味しいものを飾ったりする。解雇を知らせる日でもある。
初五 牛の日 財神・えびすの誕生日。 ・初四までのタブーを解禁する日で、破五とも言う。 ・初一からのゴミを全部出さなくてはならない。 ・早朝零時から、窓やドアを開け、爆竹を鳴らして、財の神様を迎える。 ・羊頭と鯉を祭る。
初六 馬の日 トイレの神様の日。・仕事や商売を本格的に始まる日。・大掃除をする。・トイレを綺麗に掃除する。・農家は春の耕作を始める。
初七 人の日 火の誕生日。・美味しいものを作って、満喫する日。 ・七草粥 状元粥を食べる。
初八 穀物の日。
初九 玉皇大帝の誕生日。 ・天を祭る。
初十 石の誕生日 ・道具を含めて石でできた全てを使ってはいけない。
この後は正月11、正月12・・・・と続いていくそうです。
フーさすがに歴史伝統の国ですねェー!!!
現代中国事情では、改革全面深化、法治国家建設、経済発展の「新常態化」、腐敗取締り、戸籍制度改革、2人子の条件付実施などが取り上げられました。「新常態化」耳慣れない言葉ですが、「安定成長」の中で構造改革、イノベーションにとりくむのだそうです。都市と農村の格差是正、第三次産業の発展等を追求していくことになるそうです。腐敗取締りは、「虎も蝿もたたく」方針でかなり徹底して行われているそうです。都市戸籍と農村戸籍に分かれていた戸籍制度を一元化する改革が本格的に進められました。経済発展に伴って出稼ぎ労働者の都市定住激増で現れたさまざまな問題をこれによって解決していこうということのようです。1人子政策を長らく続けてきた中国も人口バランス・超高齢化社会の到来を予感して2人子を条件付で認めていくことになりました。
また、日中関係の話題では、日中首脳会談、中国人訪日観光客激増、高倉健さん逝去などが取り上げられました。四つの原則合意に基づいて首脳会談が実現したのは喜ばしいことです。両国が時代の変動期をうまく乗り切って和して協力し共に繁栄していける道を両国指導者も国民も真剣に考えていきたいものです。中国人観光客は昨年250万人を突破しました。この春節の大型連休中にも大勢訪日しました。日本の魅力も体験していただく良い機会になればと思います。高倉健さんは「君よ憤怒の川を渉れ」(追補)などで1980年代中国の人々の心を惹きつけ、彼の死は深い悲しみをもって受け止められたそうです。日中友好にも貢献した健さんに改めて感謝したいと思います。
聴講者からは、具体的な中国事情が理解できてよかったと大変好評でした。
 第18期日中関係を考える連続市民講座が11月22日から始まりました。長野県内の大学と県日中友好協会などで作る「県日中学術交流委員会」主催で以降、毎月一回のペースで文化・情報事情、歴史、経済関係などをテーマに計6回の講座が開かれます。
第18期日中関係を考える連続市民講座が11月22日から始まりました。長野県内の大学と県日中友好協会などで作る「県日中学術交流委員会」主催で以降、毎月一回のペースで文化・情報事情、歴史、経済関係などをテーマに計6回の講座が開かれます。
開催趣旨には次のように述べられています。--日中両国は引越しのできない間柄にあり、悠久の往来の歴史と不幸な戦争を体験しています。また最大の貿易相手国でもあります。日中関係が雪解けを迎えかつての友好的な機運が回復するか大事な分かれ道に差し掛かっています。英知をかたむけ、困難を克服し、平和と友好協力の道を歩む方途を探すことは両国民にとって大切な課題です。現在、日本も中国も、アジア・世界も大きな変革期を迎えています。隣国中国に対する関心を喚起し理解を深めることは一層重要となっています。--
第1回講座は長野大学の塚瀬進教授が「現代中国を理解するポイント」と題して話しました。中国は巨大かつ多様な国であることを踏まえ、経済・政治・歴史のトピックの中から、現代中国を理解することにつながるものを選んでわかりやすく解説しました。講演のあと質問や意見がたくさん出され、有意義な講座となりました。
中華人民共和国65周年記念の講演会とパーティーを開催(10/2)2014
 長野県日中友好協会・県日中経済交流促進協議会・県日中学術交流委員会は10月2日、中華人民共和国建国65周年にあたり講演と記念のつどいを長野市内のホテル犀北館で開きました。講演会には、150名余が出席。中国研究の第一人者として活躍している朱建榮・東洋学園大学教授が、「建国65周年を迎えた中国と日中関係の今後」と題して記念講演しました。講演終了後、先生を囲んでパネルディスカッションと記念パーティーがおこなわれました。「建国以来の中国の歩みを振り返り中国理解を深めながら、いかに日中関係の危機を打開し、新たな友好関係を築いていくか」をともに考え危機を打開しようとする熱意あふれる有意義な1日となりました。
長野県日中友好協会・県日中経済交流促進協議会・県日中学術交流委員会は10月2日、中華人民共和国建国65周年にあたり講演と記念のつどいを長野市内のホテル犀北館で開きました。講演会には、150名余が出席。中国研究の第一人者として活躍している朱建榮・東洋学園大学教授が、「建国65周年を迎えた中国と日中関係の今後」と題して記念講演しました。講演終了後、先生を囲んでパネルディスカッションと記念パーティーがおこなわれました。「建国以来の中国の歩みを振り返り中国理解を深めながら、いかに日中関係の危機を打開し、新たな友好関係を築いていくか」をともに考え危機を打開しようとする熱意あふれる有意義な1日となりました。
夏目潔・県日中経済交流促進協議会会長の開会のあいさつに続き、井出正一・県日中友好協会会長が主催者を代表して「日中両国はアジアと世界の平和と繁栄に責任を持っている。両国関係は困難な状況が続いているが、切っても切れない間柄だ。粘り強く民間・地方の交流を続け、友好に資していきたい。朱先生から得がたい体験を踏まえて貴重なお話をお聞きし、改めて日中関係の重要性を認識する機会としたい」とあいさつしました。
朱先生は、冒頭自身の体験に触れ、個人が政治の波に飲み込まれることはあるが、研究者として動じないで専門分野を極めていきたいと述べた後、マクロ的に中国の歩みを振り返り表層より深層を見ていく必要性を強調しました。また日中関係については「近年の日中関係の冷え込みに、変化が見えてきた」と分析。理由として「中国では汚職撲滅など国内対策の取り組みに一定のめどが立ち、外交課題に取り組む余裕が出てきた。日本も、集団的自衛権の行使容認を閣議決定するまでは中国脅威論が必要だった」ことをあげました。更に「11月北京で開かれるアジア太平洋経済協力会議(APEC)での日中首脳会談が実現すれば、中国国内での対日交流がかなり変わる」と展望しました。
講演の要旨は以下のとおりです。
―(新中国誕生の意義と歩みに触れ)19世紀から20世紀にかけて中国を取り巻く世界の状況が大きく変化し、西洋列強による衝撃が、確立されていた中国の文明・体制に衝撃を与えた。列強の侵略に対応するため、ゆっくりとした民主主義近代化の道ではなく共産主義の道を選んだ。しかし、さまざまな要素の積み重ねの上に中国革命の成功はあった。現在、蒋介石の再評価や20~30年代の民族資本や新文化運動の果たした役割などが見直されてきており、また孔子など中国の歴史・文化・伝統を学んでもっと活用していこうとしている。毛沢東の時代と鄧小平の経済建設主体の時代も連続性あるものと捉え欠陥は改善していこうとしている。総括しながら、長期戦略を練り、科学技術開発の連続性等も重視しようとしている。習近平体制が何を目指そうとしているのか冷静に見ていく必要があろう。
2050年に向けた中国の「新しい長征」が始まっている。鄧小平の3段階戦略と習近平の「中国の夢」は同じ目標と言える。2021年(建党100周年)に「全面的な小康社会(まずまずの生活ができる社会)実現」、2049年(建国100周年)に「富強・民主・文明・和諧」の社会主義現代化国家の実現を掲げている。東アジアの発展の道筋を見ると、まず①経済の民主化(市場ルール導入)、②社会の民主化、③政治体制の民主化の道をたどっている。現在は社会の民主化の時期であり、社会問題が集中的に表れる社会的大転換の時期にあたっている。中国はこの30年間に大きく変わった。85点以上でないと不合格という日本の基準から見ると落第に見えるかもしれないが、55点以上とったことは十分評価されて良い。
日中関係の現状と展望―①APEC首脳会談は実現するか、②靖国神社参拝問題と島の問題この2つの阻害要因の克服は可能か、③今後の展望と経済交流の新しい可能性について。①についてはすでに触れた。②島問題の合意は難しいが事実上の棚上げは可能、周辺海域での不測事態の防止・行動ルールの構築が急務。「歴史」と「領土問題」は「出口論」で解決すべきで、「小異を残して大同を求める」原点に立つことが必要。③本格的改善を決める諸要素としては、中国国内の改革の要素、米中関係、国民同士の相互理解、「戦略的互恵関係」の再確認などがある。日中関係は「政冷」でも「経熱」は冷めていない。チャイナ+1は良いが、インドや東南アジアは中国に替わる受け皿にはならない。環境・農業・高齢化対策など中国の社会問題は逆に日本のチャンス。内陸部への進出と「安心・安全の保障」体制の構築が期待される。中国による対日投資の新しい可能性も出てきている。
講演後、朱先生を囲んで上條宏之・県日中学術交流委員会副会長(県短期大学学長)、森田恒雄・飯田日中友好協会会長をパネラーに、西堀正司・県日中理事長がコーディネーター役をつとめ、パネルディスカッションが行われました。
上條氏は「辛亥革命以前からの歴史は連続していると見る観点は啓発された。日本も戦前戦後の連続性をにも目をむけ、日清戦争以降の日中の近代史のかみ合わせをはかるべきだ」と述べました。森田氏は満蒙開拓平和記念館の建設運営に拘わっていることを紹介した上で開拓団の悲劇に触れ、「体験を風化させることなく、侵略への反省を忘れてはいけない」と述べました。
朱先生は「中国が首相の靖国参拝に反対しているのは、国交正常化に際し戦争賠償を放棄したが、周恩来総理は中国人民を説得するとき日本人民と軍国主義者を区別し、A級戦犯に戦争の責任を押し付け、日本人民も日本軍国主義の被害者とした。歴史にとらわれないで進む政治的解決の知恵と言える。日本はこのとき日中戦争で中国人民に多大の損害を与えたことを深く反省すると表明した。8月方正の日本人公墓をたずねたが、この公墓は周総理の許可を得て建立されたもので、開拓団の人々も日本軍国主義の犠牲者だとしたものだ。一方中国としては国交正常化以降日本が中国の現代化のために多くの支援をしたことを忘れてはならない。1978年鄧小平は訪日の際、日本に学び中国現代化に前向きに努力するとした」などと述べ日中が和して協力していく必要性を強調しました。
西堀理事長は最後に宇都宮徳馬先生の「日中友好は最大の安全保障」との言葉を紹介して日中友好のため一層努力しましょうと締めくくりました。
県内各地から集まった聴衆は熱心に耳をかたむけ、歴史を踏まえ両国関係の改善、民間交流の継続と深化の必要性を心に刻みました。
第2部の祝賀パーティーでは、井出会長のあいさつに続き、塚田佐・元長野市長、王昌勝・県華僑総会会長からの祝辞に続いて、鷲沢正一・前長野市長の乾杯の音頭で懇親会に入りました。国会議員(代理)、白建飛・県国際交流員らから祝辞をいただきました。また、この夏スキー・軽井沢・須坂・上田友好訪中団などで中国を訪問した様子を代表から報告しました。会場では友好の大切さを思い激励しあう姿が見受けられ、和やかな交流がおこなわれました。
井出庸生・衆議院議員、小松裕・衆議院議員(代)、若林健太・参議院議員(代)、土屋孝夫・県国際課担当係長、小山富男・県国際化協会事務局長、住吉廣行・松本大学学長、浅川祐司・県経営者協会事務局、西村昌二・県中小企業団体中央会参事、細野邦俊・県商工会連合会専務理事(代)、荒井英彦・県信用保証協会会長、高木幸一郎・JA全農県本部長、中村重一・信濃毎日新聞社専務、酒井康成・松本歯科大学法人室留学生課係長補佐など各界来賓が出席しました。
山沢会長は、「日中の協力、アジアとの協力が必要で、民間学術交流に力を入れることが大切と思う。各大学での教授間交流など、壁を少なくして交流を進めていきたい。信州大学としても、北京や上海に留学生による学友会が誕生した。中国との積極的な学術交流を継続していきたい」と述べました。
来賓として土屋孝夫県国際課係長は「友好提携先の河北省から2名の研修員を受入れ、県からは3名の研修員を河北大学に派遣している。民間学術交流の特色を生かして日中間の交流を積極的にを進めていただきたい」とあいさつしました。 西堀正司県日中友好協会理事長は、「日中関係は尖閣問題や靖国参拝問題で大変厳しい状況が続いているが、11月の北京APECにむけて首脳会談の可能性が取りざたされるようになった。関係改善を期待したい。青少年交流や学術をはじめとした文化の交流を通じて、相互信頼関係を大切にしていくことは長い目で見て重要な意味を持つ。大学間交流など一層の発展を期待したい」と述べました。
上條宏之県短期大学学長は「両国政府が困難を打開していくことを望む。国際放送局の朱丹陽先生に中国語の指導をお願いしているが、当学での中国語学習者は結構多く、河北大学への留学実績も増えている。若者をサポートして、交流を進めていきたい」とあいさつ。小池明上田女子短大学長は「政治家はバックグランドを背負っているので振り上げたこぶしをおろせないところがあるだろうが、市井の我々は違う。この人と関係を持たなければやっていけないとなれば、チャンネルを切らさないことが大事だ。大切な隣国中国とはいろいろなネットワークを生かして付き合って行きたい」と述べました。
総会では2013年度の事業報告・決算報告を承認した後、2014年度の事業方針・予算を採択しました。
終了後、朱丹陽さん(中国国際放送局長野孔子学堂中国側責任者)が「中国の大学事情」を講演しました。全国統一試験に900万人以上の受験生が受験したことなど新中国誕生から文革を経て現在に至る大学入試の変遷などをわかりやすく紹介いただきました。
 日中関係を考える連続市民講座(第4回)が2月22日県日中友好センターで開かれ、上田女子短大学長の小池明氏が「日本・中国・アメリカ-体験的付き合い方」と題して講演しました。小池氏は20年間の商社マン生活の中でアメリカ・ヨーロッパ・中国などの駐在経験があり、それぞれの国の国民性を学ぶ機会があったとしてその体験を生かした付き合い方・見方を話しました。また上田女子短大として、長野放送と北京電視台との協定により毎年2人ずつ北京から受け入れている様子も紹介しました。
日中関係を考える連続市民講座(第4回)が2月22日県日中友好センターで開かれ、上田女子短大学長の小池明氏が「日本・中国・アメリカ-体験的付き合い方」と題して講演しました。小池氏は20年間の商社マン生活の中でアメリカ・ヨーロッパ・中国などの駐在経験があり、それぞれの国の国民性を学ぶ機会があったとしてその体験を生かした付き合い方・見方を話しました。また上田女子短大として、長野放送と北京電視台との協定により毎年2人ずつ北京から受け入れている様子も紹介しました。(以下中国・日中関係部分を中心に概略を紹介します。)
日中関係が難しいとき専門家ではない素人の立場でどう見るか、アマチュアの考え方が意外と事態を動かしているのではないかと思い日ごろ考えていることをお話したい。マルチの国の付き合いの中で二国間関係を読み解くことが必要ではないかと思う。
中国は共産党が統治しているが経済発展に伴い格差が拡大し、貧しくとも平等だった時代と大きく変わった。コントロールを強めるのか、民主化を進めるかの選択が迫られるだろうが、党の力量の強さから言えばそんなに急速な変化はないだろうと思う。
団塊世代として日本の戦後復興・高度経済成長・安定成長の時代を生きてきたが、日本の歩んだ道を若い世代にどう伝えていくか大きな課題と思う。1970年代中ごろの中国の存在感は政治的な面が主で経済的に語られることはほとんどなかった。現在は、中国はGDP世界第2位の経済大国となった。中国のプレゼンスは世界の工場から世界の市場へと比重を高めている。日本人はリスクを避ける傾向が強いが、中国人はリスクに挑み世界的な投資を進めている。穀物やエネルギーを買いあさっており世界に与える影響は大きい。1兆3千億ドルの外貨を保有しており、これは脅しにも使えるが自分にも返ってくる。WTOの一員として秩序ある成熟したプレーヤーであることが期待されている。
我々が中国との関係を良くしていくヒントは、お互いに相手の実情を知ること。中国の人々に日本社会を知ってもらうこと。そのためには政治・経済・文化・観光・若者など多様な付き合いが必要だ。
日本は明治維新以降、脱亜論的考え方にたって中国やアジアに侵略進出していった。一方で中国に対し4000年の歴史・文明的先輩への敬意という両面があった。今、日中の逆転現象が起き、また戦勝国としての意識もある。マスメディアがそれぞれ民族主義を煽ることは危険でそうならないよう気をつける必要がある。自制を働かして冷静に付き合っていく、大人の知恵を持って対していくべきだ。冷戦時代にもLT貿易などいろいろな努力が払われていた。日本も「一党独裁」的な傾向が出てきていて心配の面があるが、日本の多様性が中国からも見えるようにしていく必要がある。尖閣問題や靖国問題を見ると、「匹夫の勇」ではなくて「やらざる勇気」が重要だと思う。
日米同盟は中国と仲良くしていく上でも必要と思うが、日本に対するアメリカでの評判は歴史認識など厳しいものがある。中国はアメリカに多くの留学生を送り、高官の子弟も大勢行っている。日本も留学生やインターンシップ受入れなどもっと努力すべきだ。また日中関係を改善するには、環境面での協力はじめ共同の事業に取り組み双方が技術や知恵を出し合っていくことが大切と思う。
 県日中学術交流委員会主催の第17期日中関係を考える連続市民講座で中国国際放送局・長野ラジオ孔子学堂の朱丹陽さんが12月14日講演しました。演題は「中国語と現代中国事情」、ここ2、3年中国でよく使われ、世相を反映する13のキーワードを紹介しながら中国人のくらしや国内事情について解説しました。
県日中学術交流委員会主催の第17期日中関係を考える連続市民講座で中国国際放送局・長野ラジオ孔子学堂の朱丹陽さんが12月14日講演しました。演題は「中国語と現代中国事情」、ここ2、3年中国でよく使われ、世相を反映する13のキーワードを紹介しながら中国人のくらしや国内事情について解説しました。本来、地方で勢力のある富豪をさす「土豪」は、身の回りのものに金をかけ、見せびらかす人を皮肉る言葉として流行している-と説明。金色に塗装された車や携帯電話の画像もスライドで示し、「物価高や就職難などに悩んでいる人もいれば、金銭的に有り余る人もいるという格差への不満が表されている」と話しました。
「延遅退休」(退職年齢を延ばす)が話題になっているのは日本と同じような高齢化が急ピッチで進んでいる事情があるとのこと。
「戸籍制度改革」については、都市部と農村部に区別され他戸籍制度の下で、都市部に働きに出ても基本的な行政サービスが受けられない問題なども説明、改革の新しい動きが出るたびに高い関心が寄せられていると述べました。
聴講者からは、庶民感覚が現れるキーワードを取り上げて解説してもらったので具体的な中国事情が理解できてよかったと大変好評でした。
第17期日中関係を考える連続市民講座が11月23日から始まりました。長野県内の大学と県日中友好協会などで作る「県日中学術交流委員会」主催で以降、毎月一回のペースで文化・情報事情、歴史、経済関係などをテーマに計6回の講座が開かれます。
開催趣旨には次のように述べられています。--日中関係は尖閣問題を解決し得ないまま1年余りを経過しています。両国は引越しのできない間柄にあり、悠久の往来の歴史と不幸な戦争を体験しています。また最大の貿易相手国でもあります。英知をかたむけ、困難を克服し、平和と友好協力の道を歩む方途を探すべきです。現在、日本も中国も、アジア・世界も大きな変革期を迎えています。隣国中国に対する関心を喚起し理解を深めることは一層重要となっています。--
第一回講座は長野大学の塚瀬進教授が「歴史的観点から見た日本人の考え方、中国人の考え方」と題して話しました。大陸国家、多民族国家中国と島国日本との状況は大きな違いがあることを、清朝を事例に取り上げました。国家と社会の関係、徴税システムの特徴、経済活動の面から両国の国家構造、社会構造の違いを解説しましたが、中国を深く理解して行く上で注目されるところです。講演のあと質問や意見がたくさん出され、有意義な講座となりました。
村山元総理長野で講演、両国関係の危機打開を訴える(11/12)2013
長野県日中友好協会・県日中経済交流促進協議会・県日中学術交流委員会は11月12日、日中平和友好条約35周年にあたり講演と記念のつどいを長野市内のホテル犀北館で開きました。講演会には、200名余が出席。村山富市元総理が「村山談話を語る-日中関係の危機を打開し新たな友好関係を築くために」と題して記念講演しました。講演終了後、先生を囲んでパネルディスカッションと記念パーティーがおこなわれました。村山談話の歴史的意義を再認識し、尖閣問題で厳しい試練にさらされている日中関係の現状を冷静に見つめ、危機を打開しようとする熱意あふれる有意義な1日となりました。
夏目潔・県日中経済交流促進協議会会長の開会のあいさつに続き、井出正一・県日中友好協会会長が主催者を代表して「日中関係はまだもろいものがあるが、切っても切れない間柄であり、粘り強く民間の交流を進めていきたい。日中は好き嫌いでなく正面から付き合っていかなくてはならない。村山談話の当事者である先生から貴重なお話をお聞きし、改めて日中関係の重要性を認識する機会としたい」とあいさつしました。阿部守一・県知事が先の訪中で河北省長と率直に今後の交流協力について話し合いができたことを紹介し、日中の民間交流、地方政府同士の交流の重要性を訴えました。
村山元総理は、アジアへの植民地支配と侵略を認め反省と謝罪を発表した「村山談話」(1995年)について、「戦後50周年の年に自分しかできない歴史的な役割だった」と当時の心情を明かし、アジアの一員として日本がアジアから信頼される国になる、そのためには戦争の反省、歴史を教訓として未来に向かって手を携えて進んで行く必要性を強調しました。その後の歴代内閣が村山談話を踏襲し、2008年の福田・胡錦濤会談では戦後の日本の平和的発展を中国側が初めて評価し「戦略的互恵関係」を築いて行く約束をしたことを振り返りました。
尖閣問題については、両国政府間で実質的に棚上げにしていた領土問題が「国有化」によって両国関係に大きな困難をもたらした経緯を紹介した後、「無人島をめぐって第2第3の経済大国が争うべき愚はやめ、冷静に対応し話し合いにより平和的に解決すべきだ」と述べました。また最近の村山談話や河野談話を否定するかのような動きや憲法改正の動きに対して危惧を表明し、政治家は、ナショナリズムを刺激しあうのではなく、周辺諸国と仲良くして行くこと、アジア全体の平和と繁栄を考えるべきであり、そのためには日中が手を携え軸となって行くべきだと述べました。
 講演後、村山元総理を囲んで井出正一・県日中友好協会会長、上條宏之・県日中学術交流委員会副会長、山根敏郎・県日中経済交流促進協議会副会長をパネラーに、西堀正司・県日中理事長がコーディネーター役をつとめ、パネルディスカッションが行われました。
講演後、村山元総理を囲んで井出正一・県日中友好協会会長、上條宏之・県日中学術交流委員会副会長、山根敏郎・県日中経済交流促進協議会副会長をパネラーに、西堀正司・県日中理事長がコーディネーター役をつとめ、パネルディスカッションが行われました。
村山内閣で厚相を務めた井出会長は両国関係の打開を目指して「村山談話の精神を今こそ大事にしなければならない」と強調しました。上條氏は村山談話の意義を再確認した上で、未来志向の関係は歴史を踏まえて初めて出てくる。日中関係は厳しいが民間・若者・経済界・学術などいろいろな分野で交流を進め東アジア共同体の基礎を作って行くことが大事だと述べました。山根氏は中国は日本にとって大切な国であり、友好活動は困難があっても粘り強く進めたい、健康長寿の源でもあると述べました。
村山元総理は総理在任中の心構えや、辞意を固めたときの心境、クリントン米大統領との会談ではアメリカの重圧を感じつつも主権国家の代表として意見を述べた体験などを紹介しました。また「杖るは信に如くは莫し」(よるはしんにしくはなし=信義に勝るものはない)との信条や長寿の健康法を語っていただきました。
県内各地から集まった聴衆は熱心に耳をかたむけ、両国関係の改善、民間交流の継続と深化の必要性を心に刻みました。
第2部の祝賀パーティーでは、立石昌広・県学術交流委員会事務局長の開会と井出会長のあいさつに続き、倉田竜彦・県日中友好促進議員連盟会長、村石正郎・県議会前議長、塚田佐・元長野市長、朱丹陽・中国国際放送局日本語部・長野ラジオ孔子学堂中国側責任者、張金霞・県国際交流員、王昌勝・県華僑総会会長、穂苅甲子男・信州葫蘆島友の会会長らから祝辞をいただきました。会場では友好の大切さを思い激励しあう姿が見受けられ、和やかな交流がおこなわれました。最後に小池明・上田女子短大学長の音頭で日中友好万歳で締めくくりました。
吉田博美・参議院議員(代)、若林健太・参議院議員(代)、白鳥博昭・県国際課長、岡村重信・県経営者協会事務局長、木藤暢夫・県商工会議所常務理事、井出康弘・県中小企業団体中央会事務局長、細野邦俊・県商工会連合会専務理事、白井千尋・県信用保証協会会長、浦野邦衛・JA長野中央会地域農政部長、中山千弘・連合長野会長、古川幸雄・部落解放同盟県連書記長、安田政寛・県針灸師会会長、桜井啓司・県武術太極拳連盟会長、手塚久盛・信州大学国際交流課長、藤原一二・松商学園理事長、福沢務・松本短期大学学生部長、酒井康成・松本歯科大学法人室留学生課主任など各界来賓が出席しました。
山沢会長は、「政府間のギクシャクがあっても民間同士の交流が大事で、長い目で見て付き合って行くことが必要だ。留学生を取り巻く環境などにも関心をはらい、中国との積極的な学術交流を継続していきたい」と述べました。井出正一県日中友好協会会長は昨年国交正常化40周年に際し、北京で中学生卓球交歓大会が盛大にに開催されたことを紹介し、「日中関係は尖閣問題で大変厳しい状況が続いているが、青少年交流や学術をはじめとした文化の交流を通じて、相互信頼関係を大切にしていくことは長い目で見て極めて重要な意味を持つ。大学間交流など一層の発展を期待したい」と述べました。
総会終了後、立石昌広・県短期大学教授が「中国社会の変容」と題して記念講演し大きく変化している中国の現状に対する理解を深めました。ました。
 日本と中国のみならず、アジアと世界は大きな変革期を迎えています。中国はじめ、アジアの人々との付き合いは年々重みを増しています。日本がアジアの一員として地歩を築いていくためにも、隣国中国に対する理解を一層深めていくことが必要と思います。
日本と中国のみならず、アジアと世界は大きな変革期を迎えています。中国はじめ、アジアの人々との付き合いは年々重みを増しています。日本がアジアの一員として地歩を築いていくためにも、隣国中国に対する理解を一層深めていくことが必要と思います。
長野県日中学術交流委員会では、中国に関する様々な面を学ぶために県内で活躍している大学・短大等の先生を講師に迎え、第15期の連続市民講座を計画しました。講座内容は、それぞれのテーマでおわかりのように、多義にわたっています。多くの方のご参加をお待ちしております。
◎資料代 1回200円(6回分一括納入の場合は800円)
◎申込み 県日中学術交流委員会/長野市中御所岡田町166-1県日中友好協会内 TEL026-224-6517・6518(FAX)
◎講義日程(予定) *時間 午後1:30~3:30
*場所 日中友好センター教室(TEL026-224-6517長野市岡田町166-1バスターミナル斜向かい)
|
回 |
月日(曜) |
テ ー マ (予定) |
講 師 |
|
|
1 |
11/27(日) |
満洲国における経済統制と在来社会 |
塚瀬進・長野大学教授 |
|
|
2 |
12/17(土) |
中国の教育と若者たち |
ビラール・イリアス・長野大学教授 |
|
|
3 |
1/28(土) |
毛細血管の生長から見る生物の巧み―日中学術交流の一隅 | 白倫・信州大学繊維学部教授 | |
|
4 |
2/25(土) |
中国発展戦略の転換 |
立石昌広・長野県短期大学教授・長野県短期大学教授 |
|
|
5 |
3/24(土) |
成長する中国市場と長野県企業 | 兼村智也・松本大学教授 | |
|
6 |
4/21(土) |
儒教・孔子・『論語』 | 早坂俊廣・信州大学人文学部准教授 | |
 長野県日中友好協会・県日中経済交流促進協議会・県日中学術交流委員会は10月24日、辛亥革命100周年にあたり講演と記念のつどいを長野市内のホテル犀北館で開きました。講演会には、180名が出席。前駐中国大使の宮本雄二先生が「これから、中国とどう付き合うか」と題して記念講演しました。講演終了後、先生を囲んでのパネルディスカッションと記念パーティーがおこなわれました。日中関係の未来を展望し友好の意義を再確認できた有意義な1日となりました。
長野県日中友好協会・県日中経済交流促進協議会・県日中学術交流委員会は10月24日、辛亥革命100周年にあたり講演と記念のつどいを長野市内のホテル犀北館で開きました。講演会には、180名が出席。前駐中国大使の宮本雄二先生が「これから、中国とどう付き合うか」と題して記念講演しました。講演終了後、先生を囲んでのパネルディスカッションと記念パーティーがおこなわれました。日中関係の未来を展望し友好の意義を再確認できた有意義な1日となりました。上条宏之・県日中学術交流委員会副会長の開会のあいさつに続き、井出正一・県日中友好協会会長が主催者を代表して「日中両国は、アジアと世界の平和と繁栄に責任を負っている。互いに多くの解決しなければならない課題を抱えており、互いに争ってはいられない。相互補完の関係にあることを自覚し、共存共栄、、共進が必要であり、そうできる。戦略的互恵関係をうたった共同声明は日中両国の進むべき道を示している。尖閣問題等を見ると両国関係はまだもろい面もある。民間交流の大切さを実感した。みんなで力を合わせて友好発展のために尽力したい。宮本前大使の貴重な体験をお話いただきこれから中国とどう付き合うかを考えていきたい」とあいさつしました。
先生は「これから中国とどう付き合うか」に話を進め、①世界の基本的趨勢と日中関係、②中国の現状をどう見るか、③日中戦略的互恵関係の世界、を具体的事例を交え分かりやすく明快に語りました。
①世界の基本的趨勢と日中関係
中国共産党の文献を読むと、必ず大きなところから入って細部にいたるという思考方法を貫いている。この思考方法を取り入れてまず世界の基本的趨勢を押さえておきたい。現在世界は曲がり角に来ている。アメリカ式資本主義がリーマンショックにより行き詰まり、市場の巨大化で活路を見出そうとしたEUも危機を迎えている。新興国もチャレンジを受けているが、世界経済の中の比重が高まった。中国・インド・ブラジルも経済のグローバル化・開かれた経済から利益を得た。従ってこれら新興国はこの仕組みを壊すことはしないだろう。修正は必要だが現在の仕組みから利益を得ているのでこれを尊重して行くだろう。技術革新・グローバル化・相互依存は益々進むだろう。一方、軍事安全保障面から見ると、相手に対する猜疑心、最悪の事態に備えるという基本的位置づけは変わらない。日中間に横たわるこの2つの矛盾を政治的にどう調整するか。隣国同士は仲が悪い。独仏は500年間戦争を続けようやく仲直りした。日中間は近いから仔細が分かってしまう。両国が仲悪くなったり対立したりする事例は事欠かない。不安定要因はあるが、大きな視点で日中関係を前進させていく必要がある。
②中国の現状をどう見るか
中国は、中国共産党の(国民党の弾圧下で育まれた)秘密主義と社会の急速な変化、多様化によって分かりにくいところがある。改革開放政策は大きな成功を収めた。成功は新たな問題を生み出している。1つの踊り場に来ている。中国社会は大きく変質し、経済活動の飛躍的拡大、生活空間の拡大が進んだ。2008年には23%が大学に進み、インターネット人口は5億人に達し、市民が自分で判断できる状況となった。価値観が多様化し、幸福感が1人1人違ってきた。全員を満足させることはむずかしい。格差と腐敗の問題も深刻だ。科挙制度の伝統があった中国では地方知事を務めれば3代の富ができるといわれていた。鄧小平が江沢民に3つの提起をしたといわれている。1つは軍の掌握、2つは党の分裂を避ける、3つは腐敗・汚職は民の心が去る。これから分かるように腐敗の問題はかなり重視されている。
中国はたくさんの問題を抱えているが中国は倒れない。次々と問題は起こるが問題の60~70%は解決してきた。中国共産党の統治能力が高いことを示している。たとえば不動産バブルに対しては今年だけで低所得者向けに1000万戸の公団住宅を作っている。更に3000万戸を計画している。中国に経済発展をもたらし、良くここまでやった、中国共産党を評価すべきと思う。しかし、問題は深刻化している。今社会の安定が強調されている。100人以上のデモが年間8万件おきているとの中国の公式発表がある。日本だったらたとえ10分の1であっても大変なことだ。判断基準が日本とは違う。
③日中戦略的互恵関係の世界
日中がともに世界の中で大国となり影響力の強い国となった。歴史的に見ると、かつて中国は長く世界の大国であった。明治以降日本が勃興し、中国が没落した。現在、地球規模で見て、日中は世界のなかでGDP第2位と第3位の国となり、世界に対する責任は大変大きくなった。戦略的互恵関係にありけんかばかりしていることは許されない立場にある。毛沢東時代は世界に対して敵対的だった。改革開放の時代は世界の中に組み込んで行くことこそ必要だ。かつて天安門事件が起こったとき欧米は中国を非難したが、日本は改革開放勢力を支援した。日中両国は相互補完の関係にあり、よい経済協力関係をつくるのは日本の国益でもある。
中国の発展に伴い中国は大国になったのだから、もっと自分の主張をしてもよいのではないかと思う人が増えている。アメリカはイラクに戦争を仕掛けた、アメリカに包囲されているという猜疑心がある。また歴史的な屈辱を忘れないという愛国主義教育は現在の指導部に跳ね返ってきて、柔軟な外交のかせになることもある。改革開放の道筋を指し示した鄧小平理論も腐敗に対処する具体的処方は残していない。時代の要請にあった中国独自の価値観を打ち立て世界に表明しなければならない。
日中関係は経済分野における戦略的互恵関係と一方における軍事安全保障問題これをどのようにバランスをとりうまく処理して行くかが課題となっている。日本は平和国家として生まれ変わった。より多くの国民同士が接触して相互信頼を育むことが最も大切だと思う。交流を強化して、相互不信の状況を突破していかねばならない。軍事安全保障の専門家の観点から見ると米中はいずれ衝突するといい、経済の専門家は協力以外に道はないという。この両者のバランスが大切だ。安定した状況を作ること。軍事交流が大切で、軍事的透明性を高めることが必要だ。軍事安全保障の観点すなわち最悪の状況に備えるという、この世界に引き込まれている。軍人同士が相互訪問し率直に言い合うことが必要だ。
 ◎講演後に、宮本先生を囲んで西堀正司・県日中友好協会理事長の司会でパネルディスカッションが行われました。
◎講演後に、宮本先生を囲んで西堀正司・県日中友好協会理事長の司会でパネルディスカッションが行われました。県日中学術交流委員会会長の山沢清人・信州大学学長は「信州大学に留学した人たちが中国へ帰国してから同窓会を作って北京で40人、上海でも30人が集まったといった話も聞く。日本の学生も中国に派遣していきたい。中国留学生の意識や意欲は高い。中国から学んでくることはたくさんある」と述べました。
宮本先生も、「地方交流が日中関係を底ざさえしている。信大医学部の留学生が河北医科大学をリードしているという話を聞いた。これからの交流は科学技術重視だ。中国では大学の統合を数年前に行って巨大化している。地域連合を組んで地方交流をすすめていただきたい。留学生の相互交流は大変大切。留学生は国を代表することになる。留学生を大事にして返すこと。彼らは日中の架け橋になる。日本政府ももっと留学生交換事業を支援すべきだ。
桜井佐七・県日中経済交流促進協議会理事は「中国が好きで、文革中から中国を訪問している。万博中国館の清明上河之図のコンピューターグラフィックも見に行った。大変素晴らしかった。新幹線に乗って西湖も訪問してかえったところで温州の高速鉄道事故処理問題が起こった。中国の軍事大国化や人権軽視の事故処理についてどう考えたらよいか」と語りました。
宮本先生は「中国で基本となる価値観が揺らいでいる。根本的なところを打ち立てられていないところに欧米の物質主義的な新しいものがどんどん入ってきている。中国の人権・民主主義を考える場合、易姓革命の伝統がある国なので天命すなわち民の声に従ってやることだと思う。社会の格差については熾烈な論争があり左右から批判が起こっている。民衆の意識も高まっている。人民の人民による人民のための政治ということに尽きると思う。
軍事大国化についていうと航空母艦を大国は大国として持つべきという庶民の声もある。何のための軍事大国化か、まだ我々に明らかにしていない。この辺が問題と思う」と語りました。
会場からも原発、アジア経済の一体化、アニメなどの日本文化などに対する中国での受けとめ方などの質問が出されました。「中国ではエネルギー効率がまだまだ悪い。経済成長が共産党の統治の正当性を保障している中で、原発は電力確保の上で必要としている。アジアの経済一体化については50%はアジア域内の貿易が占めている現実があり、今後もその傾向を強めて行くことになるだろう。外来文化への対応としては党が全てを手のひらの上でやらせようとするがこれはだんだん難しくなっている。知的財産権の保護の問題もある」などと答えました。
第2部の祝賀パーティーでは、井出会長のあいさつに続き、村石正郎・県会議長、王昌勝・県華僑総会会から祝辞をいただいた後、若林健太・参議院議員の音頭で乾杯しました。また、今井正子・県議、劉非・北京放送局日本語部副部長らからスピーチをいただきました。会場では和やかな交流が行なわれました。最後に佐々木治夫・県医師会副会長の音頭で日中友好万歳で締めくくりました。小坂憲次・吉田博美・参議院議員(代)、塚田剛義・県信用保証協会常勤理事、和田明・県中小企業団体中央会総務部長、竹之内健次・部落解放同盟県連委員長、三浦義正・信州大学理事、鈴木隆・同、酒井康成・松本歯科大学法人室主任など各界来賓が出席されました。講演会には、浅井秋彦・県国際課長、小松正俊・JA長野中央会専務、埋橋茂人・JA全農県本部長、木藤暢夫・県商工会議所常務理事、高橋博久・県平和人権環境労組会議議長、小沢明・県国際交流推進協会事務局長らも出席されました。
*宮本先生の発言についての文責は編集部にあります。
 長野県日中学術交流委員会(山沢清人会長)は8月10日、長野市のホテル・サンパルテ山王において2011年度総会を開きました。信州大学や長野大学、県短期大学、上田女子短大など中国との学術協定や学術交流、留学生受け入れなどの現状なども報告され、引き続き日中学術交流を促進していくことを決めました。また、第15期を迎える日中関係を考える連続市民講座や辛亥革命百周年記念日中関係を考えるシンポジウムなどに取り組むことが決定されました。
長野県日中学術交流委員会(山沢清人会長)は8月10日、長野市のホテル・サンパルテ山王において2011年度総会を開きました。信州大学や長野大学、県短期大学、上田女子短大など中国との学術協定や学術交流、留学生受け入れなどの現状なども報告され、引き続き日中学術交流を促進していくことを決めました。また、第15期を迎える日中関係を考える連続市民講座や辛亥革命百周年記念日中関係を考えるシンポジウムなどに取り組むことが決定されました。山沢会長は、「3.11以降日本は国難を迎えている。労働力の減少などの現実にも向き合っていかなければならない。中国との連携協力は重要で、国家経営の視点など学ぶべき点も多い。留学生を引き受けるだけでなくこちらからも派遣し学ぶ必要性を感じている」と述べ、若い世代の人材の養成を日中学術交流の中で積極的にすすめていきたいとの意向を示しました。上条裕之県短大学長も「日本は歴史的な転換期を迎えている。中国は日本の前途にとって避けて通れない重要な隣人、中国との学生交流・研究者の交流などすすめていきたい」と述べました。
総会終了後、長野滞在中の中国国際放送局日本語部副部長の劉非さんが「辛亥革命100周年-孫文と日本」と題して記念講演しました。孫文の活躍を支えた宮崎 滔天(みとうてん)や梅屋庄吉の事跡を詳しく紹介し出席者に感銘を与えました。
 長野県日中友好協会・県日中経済交流促進協議会・県日中学術交流委員会は12月3日、日中友好協会創立60周年を記念し講演と祝賀のつどいを長野市内のホテル犀北館で開きました。講演会には、200名が出席。朝日新聞中国総局長や編集委員、ニュースステーションのコメンテーターとして活躍された加藤千洋(ちひろ)・同志社大学大学院グローバル・スタディーズ研究科教授が「激動する世界の中の日本と中国」と題して記念講演しました。講演終了後、先生を囲んでのパネルディスカッションと祝賀パーティーがおこなわれました。友好の意義を再確認し共有できた有意義な1日となりました。
長野県日中友好協会・県日中経済交流促進協議会・県日中学術交流委員会は12月3日、日中友好協会創立60周年を記念し講演と祝賀のつどいを長野市内のホテル犀北館で開きました。講演会には、200名が出席。朝日新聞中国総局長や編集委員、ニュースステーションのコメンテーターとして活躍された加藤千洋(ちひろ)・同志社大学大学院グローバル・スタディーズ研究科教授が「激動する世界の中の日本と中国」と題して記念講演しました。講演終了後、先生を囲んでのパネルディスカッションと祝賀パーティーがおこなわれました。友好の意義を再確認し共有できた有意義な1日となりました。激動する世界の中の日本と中国―3つの逆転と中国の行方そして日中関係--加藤千洋・同志社大学大学院教授
内藤武男・県日中経済交流促進協議会会長の開会のあいさつに続き、井出正一・県日中友好協会会長が主催者を代表して「日中友好協会創立60周年にあたり、10月には北京の人民大会堂で日本から1200人、中国から宋健中日友好協会会長ら100人の友人も参加して祝賀会が行われた。席上加藤紘一日中全国会長に代わり代表してあいさつした。尖閣沖の漁船衝突事件以来一挙に日中関係が厳しくなり崩れそうになり、そんな中での祝賀会だったので一抹の不安もあったが、こんなときだからこそ民間友好団体のわれわれが頑張らねばとの思いをもった。新中国誕生の翌年友好協会はスタートし、多くの先達が数々の困難を乗り越えて国交回復や友好発展のために尽力してきた。戦略的互恵関係が言われているが、まだもろい面もあり、より確かなものに構築することが重要と思う。国情の違いを理解し、国民感情の改善に努めること、そのためには民間の努力が重要だ。日中両国の良好な関係はアジアと世界の平和と繁栄にとって必要不可欠。中国・アジア・世界の事情に詳しい加藤千洋先生を迎えて講演をお聞きし友好協会として何をなすべきか考えていきたい」とあいさつしました。
加藤先生はまず、世界の何がどう激動しているかに触れ、激動の世界について3つの逆転現象を上げました。①米中の逆転(昨年の自動車販売台数の米中の逆転)②日中の逆転(GDP第2位の座の逆転)③東西の逆転(歴史的に見て1820年ごろまでGDPの33%を占めていた中国が産業革命やアヘン戦争を機に没落し世界経済の中心が西に移ったが、今再び東に移ってきた)3つの逆転の主役はいずれも中国であると述べました。
この中国と付き合って行く上で①中国の台頭、経済発展はいつまで続くか②経済が豊かになった中国の民主化はあるのか③不透明ではあるがますます重要となっている中国とどうやって向き合えばよいかと話を進めました。
①特派員として中国に7年間滞在した経験から言うと少なくとも後10年は高度成長を続けるだろう。さらにアメリカに追いつき追い越すだろうとの予測もある。沿海部の経済発展地域、内陸の後発地域など中国は島国の均一な日本と違って3~4の経済モデルが同居しており奥行きが深い。中国共産党は統治能力をもっており、また財政にゆとりがある。(バブル崩壊の対応も可能。)目標として20年までに4倍増を打ち出し、全面的小康社会の実現を掲げているが、控えめに考えても7%成長を10年続けるとGDPは倍になる。さらに10年続けると4倍になる。現在5兆ドルだから2020年には10兆ドル、30年には20兆ドル、アメリカは現在15兆ドルほどなのでこちらも一定の成長を見込んで20兆ドルとすれば計算上並ぶことになる。歴史を見ると中国の台頭は100年スパンで続いて行くものといえる。
マクロで見ると飛ぶ鳥を落とす勢いの中国だが、問題は山積みしている。先送りしてきた問題、急ぎすぎた結果発生している問題としてエネルギー効率の悪さ、環境破壊の問題、少子高齢化問題、少数民族問題、役人の汚職の問題、中でも格差問題がある。対策として西部大開発などのような内陸部への開発投資、三農問題の解決、徴税システムの強化などに取り組んでいこうとしている。
②一人当たりのGDPが3700ドルから4000ドルとなると中産階級も政治的主張を始める。中国も民主化する時期ではないかと世界から見られている。56の多民族国家である中国は複雑な国情で、同列には論じられないが中国式の政治的変革が進むだろう。
③超高齢化社会の日本と高齢化社会になりつつある中国とどのように向かい合っていったらよいか。 1人あたりのGDPが1万ドルを超えるところが上海、広州、北京、青島と広がり、それが日本と同じ規模となっており、自動車だけでなく高級消費財が爆発的に売れる状況にある。一方、尖閣問題での反日デモ、小泉時代の反日デモ、SARSなどがありチャイナプラスワン(中国が主だが安全弁として別に1つ持つ)がいわれている。リスクがあるからといって避けるわけにはいかない。魅力ある中国を有効に使って、向き合って行くべきだろう。
中国の友人と話しているとGDPは2位になったといっても人口は10倍、日本には10年いや20年、25年は追いつきませんと言う。それは日本のソフトパワー、完備された水道・鉄道の正確さ・トイレの清潔さ・治安の良さ・きれいな街・社会の中にある何気ない人間関係と次々と日本の良さをあげる。中国やインドに対して量的拡大競争を挑んでも太刀打ちできない。日本のソフトパワー、省エネ、環境保全などを活かし質の高い国を目指し、それを活かして中国と友好的な協力関係をつくって行くべきだろうと結びました。
尖閣問題、北朝鮮問題、日米中正三角形論、中国の民主化と情報統制などについての質問に対して加藤先生から、率直な見解が示され、聴衆はうなずきながら耳を傾けました。
尖閣問題への対応では両者とも失敗したなと思う。日本の失敗は船長をあとのことを考えず逮捕したこと、釈放タイミングの悪さ、ビデオ流失への対応など、脈絡のなさが目立った。一方中国の失敗も大きかった。問題を民間交流や経済の領域にまで広げてしまったこと、南西諸島への自衛隊配備強化などの状況を作り出してしまったこと、このような情景は中国側も見たくなかっただろう。中国のネット上にはこのような姿勢に批判的意見も見られることは救いだ。北朝鮮問題への中国の対応を考える場合、中国は複雑な国で、見る角度によって違う要素を持っていることをおさえておく必要がある。外交部は厳しく当たれと考えているが、国内の安定と経済の発展が至上命題の中国にとって隣国の不安定化を望まないと言うのが本音だ。中国の民主化については現政権の置き土産となるかはちょっと疑問で次期政権でも具体像は見えてこない。情報統制システムも一方でネット空間の広がりがあり、また知識人の言論自由の幅も広がってきている。三歩前進二歩後退、すり足のような変化ではあるが、「長江の流れは、よどみ・逆流はあるが、一貫して西から東へ流れている」(江沢民)ことも事実だろう。
西堀理事長は、中国では毛沢東・周恩来・鄧小平時代と比べて指導者のカリスマ性がなくなっている中で日中関係・対外関係の処理も大胆で柔軟な決断を下すことが難しいかもしれない。正三角形理論は理想だが、国民感情もありアメリカ一辺倒的な日本政府の対中政策となっている。しかし政治は細っているが経済関係は太い。尖閣問題も小異を残して大同の精神で処理してほしい。民間交流を拡大して尖閣問題が小異になるくらいの関係を目指すべきと述べました。
最後に加藤先生が青少年交流の大切さに触れ留学生など一人ひとり大切にして付き合って行くことが相互信頼・友好協力の基礎になると述べ締めくくっていただきました。
第2部の祝賀パーティーでは、島田力夫・長野大学学長、王昌勝・県華僑総会会、阿部守一県知事から祝辞をいただいた後、塚田佐・前長野市長の音頭で乾杯しました。また篠原孝・衆院議員(代)、北沢俊美・参院議員(代)、小坂憲次・参院議員(代)、佐々木治夫・県医師会副会長、劉非・北京放送局日本語部副部長、岡田荘士・長野市日中議連会長、田中正治・松本歯科大学理事、穂苅甲子男・信州葫蘆島の会会長、小林佑一郎・前帰国者定着促進センター所長らからスピーチをいただきました。県会開会中のため寺島義幸・県会議長からは祝電をいただきました。女性委員会メンバーが加藤先生を囲んでふるさとを合唱。会場では和やかな交流が行なわれました。最後に窪田徳右衛門・白馬村副村長の音頭で万歳で締めくくりました。塚田剛義・県信用保証協会常勤理事、星沢重幸・部落解放同盟県連副委員長、三浦義正・信州大学副学長、高橋進・長野大学学部長など各界来賓が出席されました。
