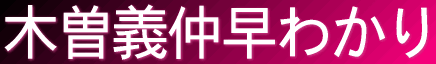 |
||||||||
 |
||||||||
| お知りになりたいこと | ご 説 明 | 出典の分類 | ||||||
笠原平五頼直 (かさはらへいごよりなお) |
(?〜?) 源平時代の武将。平家方。信州笠原牧(長野県中野市)の人物。 笠原牧は古代律令制の頃からの馬の生産地。当然、騎馬戦に優れる。 源頼政が反平家の挙兵をしたとき(宇治川の合戦) 平家方武将として参戦(1180/4/26)。 以仁王・頼政・仲家(義仲の兄で頼政の養子)が死亡。 その功により勘解由判官に任命される。 木曽で義仲が挙兵するとその前に立ち塞がる。 市原の戦い(1180/9/7) 横田河原の戦い(1181/6/13)において激突。 敗北して逃亡。消息不明。 頼直も義仲も信州育ちの騎馬戦の専門家。 その決戦はどんなに豪快だったでしょうか? |
1 人物 | ||||||
神仏に起請し,願を立てる時などにその趣旨を述べた文書。祈願文。願文。 木曽義仲が真盛の甲等を願状を添えて多田神社に奉った。 7日匿ってもらったお礼と戦勝祈願して涙を流したという。 |
2 図書文献 随行日記 木曾義仲副書 |
|||||||
(きそよしなか)  徳音寺所蔵 |
『吹く風を勿来の関と 思えども 道も背に散る 山桜かな』 とは源義家(みなもとのよしいえ)が残した歌です。 義家の曾孫(ひこまご)で,頼朝や義経とは義兄弟。 父は,源義賢(みなもとのよしかた) 母は,小枝御前(遊女との説もある) (1153〜1184) 源氏(げんじ)の血筋をひき武蔵の国(嵐山町)に生まれ,幼名を駒王丸(こまおうまる)と呼ばれた。 武将の最高位征夷大将軍(せいいたいしょうぐん)に上り詰めたが,31歳の若さで従兄弟の源義経(みなもとのよしつね)に討たれ波乱の生涯を閉じた英雄である。 駒王丸2歳の時に,父義賢が義平(よしひら)に討(う)たれたため,母小枝御前(さえごぜん)と共に,乳母の嫁ぎ先である木曽の土豪(どごう)木曽中三権守(きそちゅうさんごんのかみ)中原兼遠(なかはらかねとお)のもとに逃れた。 元服(12歳)して義仲を名乗り,木曽日義の里の地宮之原で平家追討に旗挙げを目指した。 日義の里では今でも,この木曽義仲の旗挙げに因んだ「ラッポショ」(火祭りの呼び名)の伝統が引き継がれている。 後の「朝日将軍木曽義仲公」(あさひしょうぐんきそよしなかこう)である。 菩提は長野県木曽郡日義の里「徳音寺」で,高台に一族と共に眠る。 木曽義仲と日義の里 |
1 人物 |
||||||
| (きそちゅうさんごんのかみかねとお) | (?〜?)生没未詳 信濃の国木曽の豪族。 「中三」とは,中原氏の三男の意 義仲の乳人。今井四郎兼平,樋口次郎金光の父。 義仲(駒王丸)を匿い,文武に長けた武将に養育した人物。 「義仲を捕らえて差し出すように」との平家の厳命に従わず,旗挙げには信濃の軍勢を援軍に招聘した恩人。 |
2 図書文献 | ||||||
| は木曾義仲に限りない愛情を抱き、死んだら義仲の傍らに葬ってほしいと遺言した。二人の墓は今も大津市の義仲寺に並んでいる。 |
4 縁の地 | |||||||
| (ぎょくよう) | 九條兼実(くじょうかねざね)の書いた日記。 日記の中に木曽義仲が書かれている。 九條兼実は,後白河法皇の側近にあった右大臣で英才博学の人物として知られる。 「玉葉」は,藤原定家の「名月記」と並んで,時代の趨勢を慧眼を以て直視し,後世に残した貴重な記録として高く評価したい。 この中で,木曽義仲の動静についてもよく観察して記録している。その内容は「平家物語」に語られる嘲笑蔑視(とうしょうべっし)ではなく, 木曽義仲を描写する九條兼実(くじょうかねみ)の人物像から玉葉の内容に”実像”が有るのではないかと推量される。 |
2 図書文献 | ||||||
| (きみょうちょうらい) | 仏の教えを信じて頭を地につけて拝すること。 |
4 ご参考 | ||||||
(くじょうかねざね) |
(〜) 「玉葉」世の中の動静を日記にして残した人物。 中に木曽義仲の動静が書かれている。
|
1 人物 | ||||||
鎌倉時代前期の歴史書。 慈円が書いたもので承久二年の成立とされる。 、 和漢の年代記や、神武天皇から順徳天皇までの歴史及び慈円の史論が仮名文で書かれて著書全7巻。 木曽義仲挙兵から上洛の間の記録がある。 【慈円(じえん)】(1155〜12125) 平安末〜鎌倉初期の天台宗の僧。諡は慈鎮。吉水の僧正とも通称する。関白藤原忠通の子。九条兼実の弟。天台座主を四度つとめた著書に,歌集「拾玉集」などもある。 |
2 図書文献 | |||||||
  |
||||||||