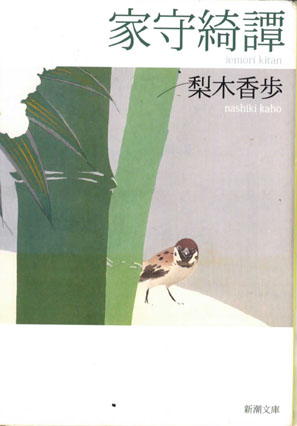
毎月1日発行[発行責任者:守 一雄]
(kaz-mori[at-mark]cc.tuat.ac.jp)
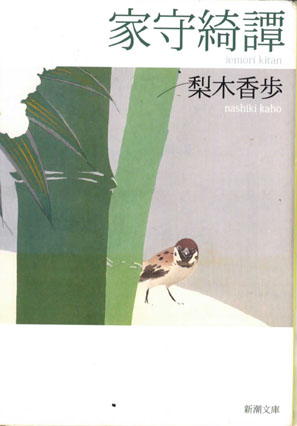
|
|
(c)新潮社 |
本を開いてすぐの目次には「サルスベリ」「ヒツジグサ」「ドクダミ」など植物の名前が並ぶだけ、さらにページを繰ると「家守綺譚」という扉の裏には、「左は、学士綿貫征四郎の著述せしもの。」とある。「あれ、確か著者は女の人だったはずでは」と表紙を確認して、すぐに「そうか明治時代くらいの男になりきって書いたものか」と気づく。
その綿貫征四郎(わたぬきせいしろう)というのは、まだ大学生が同年齢集団の1%にも満たなかったであろう時代に大学を卒業した売れない物書きで、今で言えば、文系の博士課程満期退学者(高学歴ワーキングプア)だ。貧しいこともあり、誰も住む人がいなくなった大学時代の友だちの実家にただで住まさせてもらっている。家は空き家にして誰も住まない状態にしておくと、かえって痛むというので、「家守」として庭付きの一戸建ての空き家の管理をしているというわけだ。(巻末の吉田伸子さんの解説にもあるように、本文中には時代も場所も特定はされていないが、明治三十年代後半くらいの京都と滋賀の境目くらいの話と想像できる。)
さあいよいよ嘘の始まりである。まずは、その家の床の間の掛け軸に描かれた絵の中から、若くして死んだ高堂というこの家の持ち主である友だちがボートを漕いでやってくる。そして、「庭のサルスベリがおまえに懸想をしている(恋心を抱いている)」と忠告するのである。綿貫はそれをさも当然のように受け入れて、「木に惚れられたのは初めてだ」と述べる。で、高堂に木に惚れられたらどうすればいいのかを尋ねると、そばに座って本を読んでやれと言われる。そこで、さっそくそうしてみる。そして、「私の作品を読み聞かせたら、幹全体を震わせるようにして喜ぶ。かわいいと思う。」というのだ。ここまでとんでもない嘘をつかれると、わけもなく気持ちがいいから不思議だ。
その後も、庭の植物に関わる奇妙な話が、ちっとも奇妙という感じを示さないまま、さも当たり前のように語られていく。タヌキやキツネ、河童が登場してきても、雷が落ちたせいで、モクレンの木がタツノオトシゴを孕んでしまっても、もう何も驚くこともない。綿貫は、それらの奇妙なできごとをさも当然のように淡々と書き綴るのである。その不思議を不思議としない話の展開が心地好い。それぞれのエピソードに植物のタイトルがついているのだが、必ずしもその植物が中心となっているわけでもなく、また、それぞれが独立しているようでいて、互いに関連しつつ、これもまた淡々と語られて行くのである。
どう見ても嘘の話なのだが、どれもこんな世界があってもいいなと思えるような味のある「いい話」なのだ。綿貫のような生活をしてみたいものだと思えてくる。これは面白い。