|
|
■超音波骨密度測定法
音が伝わる際の減衰率や速さは物質の緻密性により差が生じるという
原理を応用して、かかと(腫骨)に超音波を当てて骨量を計測する方法。
放射線を用いないので子供や青壮年のスクリーニング検査に適しています。
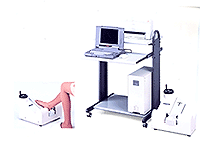 骨密度測定装置 骨密度測定装置 |
■骨粗鬆症
わが国では骨粗鬆症患者は1,000万人(1996年)と推定され、
原発性骨粗鬆症は男性にくらべ女性に圧倒的に多く発症します。
寝たきり老人の大きな原因となっている大腿骨頚部骨折患者は1987年の
全国調査では年間5万人、1992年の全国調査では、年間8万人と急速に
増加しています。大腿骨頚部骨折は一度発症すると40%は退院できず、
この骨折が原因で骨折後1年以内に10〜20%が死亡するという統計が出ています。
今まさに高齢化社会をむかえつつある時期にあるわけですから、
将来のQOL(quality of life=質のよい生活)のため、骨粗鬆症の
健診・診断・治療はその重用性を増しています。

年齢別にみた骨粗鬆症の発生頻度 |
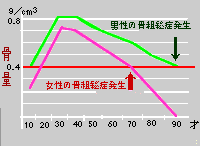
加齢による骨量の変化 |
■なぜ女性に多いのでしょう?
1.女性はもともと骨の量が少ない。
2.閉経があること(女性ホルモンの減少により、骨密度が急速に低下する)。
若い女性でも無理なダイエットや、神経食思不振症などにより、
卵巣機能低下から生じる無月経やカルシウム摂取の不足によって、
骨量減少が顕著になります。
3.男性よりも長寿であるため(平均寿命が83歳近いわけですから、30年間位)
女性ホルモン(エストロゲン)が低下した時期を過ごすことになります。
■治療にはどんな方法が?
その人のライフスタイルから長年にわたって低下した、また、一旦低下
してしまった骨量を日常生活指導(食事・運動・日光浴など)のみで
回復させることは、予防のレベルとしては良いのですが、治療としては
実際にはかなり困難です。
従って、薬物療法(カルシウム剤や骨の形成を促進し、破壊吸収を
抑制する薬剤を用いる)が必要となります。
A.骨吸収抑制剤:カルシトニン、エストロゲン、イプリフラボンなど)
B.骨活性化剤:ビタミンD3
C.骨形成促進剤:ビタミンK
当院では上記の薬剤を状況に応じて使用していますが、特に婦人科の立場から、
HRT(hormone replazament therapy:ホルモン補充療法)を有用と考えています。
■ホルモン補充療法は副作用が心配?
もちろん、使用していけない場合(例えば、エストロゲン依存性悪性腫瘍、
重症肝機能障害、血栓症など)がありますが、対象女性を十分に考慮して
選択すれば、女性にとってのメリットは非常に多いのです。
適応例を示すと、
A.更年期障害の予防および治療
B.泌尿器症状(萎縮性腟炎、性交障害、尿失禁)
C.骨粗鬆症の予防と治療
D.高コレステロール血症の予防
E.痴呆の予防
また、よく発ガン性の心配を聞かれることが多いのですが、
HRTを正しく行えば、子宮体ガンの発生はむしろ減少するのです。
もちろん、定期的な子宮・乳房検診が大切であることは言うまでもありません。
|
|
|