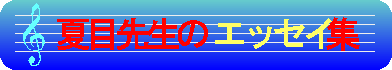
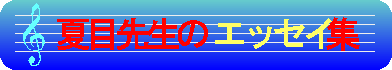
【第5回】
The English translation of this essay is here.
集団指向の強い日本人は、自分だけ人と違った行動を取ることを、極端に嫌う傾向があります。内心では「それは違うんじゃない」と思っていても、回りの皆がやっていることに従ってしまいがちです。先日も東京の音楽大学へ通い始めた私の生徒から、こんな電話がかかってきました。「大学の学生のほとんどの人が白い楽譜を持っているけど、あの楽譜でなければいけないんですか?」
「白い楽譜」とは、日本のピアノ界の重鎮であった井口基成という人が編纂した、春秋社から出版されている一連のピアノの楽譜のことです。この楽譜は普通によく使われている楽譜と違って、真っ白な表紙なものだから、すぐそれと分かるのですね。その白い楽譜を、どの学生もどの学生も小脇に抱えて歩いて行くというのです。まだ楽譜の違いについて何の知識もない新米の音楽学生にしてみれば、自分の持っている楽譜はもしかしたらいけないのかもしれない、などと心配になるのはよく分かります。しかし、実際には同じ曲集の楽譜でも、幾つかの違った版が出版されているのです。このように白い井口版ばかりがやたらに目立つとすれば、いかにも日本的な風景で悲しくなります。
私はかねがねこの井口版のバッハの曲集の編集内容には、大きな疑問を持ってきました。簡単な例としてインベンションの第一番を取り上げてみましょう。井口氏はこの曲の冒頭に「強く」を意味する「フォルテ」を書いています。この指定は幾つかの点で、大変に疑問があります。
- この冒頭部分は、次に一段高くなったところで繰り返され、更に高い頂点に達します。始めから強いフォルテで音楽を始めたのではので、音楽の作りようがありません。
- このインベンションの教育的目的について、バッハ自身が「中でもカンタービレ(歌う)奏法を学ばせ」と書いています。もちろんこの曲の主題も、十分に歌うことができるメロディーです。もしこれをフォルテでひいたら、とても歌うようにひくことはできないでしょう。フォルテという記号を見ただけで、演奏者はこの主題は柔らかく歌うメロディーではなく、力強い性格の主題だと受けとってしまうと思います。
- この曲はたった2ページからなるかわいい小品です。そのことを考えても、クライマックスが後から出てくるというのに、いきなりフォルテから始めるということは、あまりに乱暴な開始といえるでしょう。
ちょっと考えれば分かりそうなこんなことでさえ、この版にはこのように問題があるのです。それなのに何故井口版が、こんなにもピアノ教師や音楽学生の間で使われるのでしょうか。それは、おそらく井口基成という先生が、戦後日本のクラシック音楽界が急速に発展を遂げつつあった時、ピアノ教育界の重鎮として重きをなしていたからでしょう。権威に弱い日本人の間では、いつの間にか井口版が一番だという、暗黙の了解が出来上がってしまったのだろうと思います。
私のような一介の地方のピアノ教師が、いくらこの版には問題がありますよといったところで、日本の体勢には何の影響もありませんが、実は、この井口版には思い出があります。全日本ピアノ指導者協会が催したあるピアノの公開講座の折りでした。講師は世界的に有名なジュリアード音楽院のマーティン・キャニン教授、受講生は東京芸術大学の学生でした。バッハのイギリス組曲のアルマンドをレッスンしていたのですが、その学生があまりに強い音でひくものですから、先生が楽譜をのぞき込むと、その楽譜には「フォルテ」と印刷されていたのです。それを見て先生は「一体どの楽譜を使っているのですか?」と聞かれました。果たせるかなそれは井口版だったのですね。キャニン先生は「アルマンドは、荘重で優美な曲ですよ。どうしてこれがフォルテでひき始めることができるでしょうか。」といった意味のことをおっしゃると、白い井口版を高く掲げて、「この版にはとても問題があります。バッハを勉強するときは、この版を使うのはよした方がいいですよ。」と会場に向かって話されたのです。
私がその時思ったことは、「結局このような偉い先生が言ってくれないことには、日本人は納得してくれないんだなあ。」ということです。何の先入観もなしに自分の感性を柔らかくもって、そのアルマンドが最も自然にその美しさを発揮するようにひいてみれば、自然とこれがフォルテでないことくらい分かろうと思うのですが。
と言っても、この学生ばかりを責められないでしょう。その学生はおそらく自分の先生にその楽譜を買うように言われたのでしょうから。結局、この問題の根源は、日本の文化のあり方そのものにある、と言えるかも知れません。そこでは、「学ぶことは目上の者の言う通りにすること」ですから、教師も自分自身の感性を喚起しようとする気が、あまり起きないのかも知れません。半ば盲目的に井口版を与え、井口版に従って教えますから、生徒自身の自然で柔軟な感性が育たないというわけです。もしかしたら、その先生は井口先生直系の生徒かも知れませんね。日本では、トヨタの社員は全員トヨタの車に乗っているように、そうするのが日本の習わしですから。とろが、所変わってアメリカのオートバイメーカー、ハーレイ社に努める社員だと、自社のオートバイに乗ろうが、ホンダのバイクに乗ろうが社員の勝手だそうです。文化の違いが、こんなところにも現れているのですね。
しかし、考えてみれば、彼らが教えている西洋音楽というのは、他でもない「自分自身の感性」というものを、一番大切な基本理念とした芸術なのですね。その意味からすると、このようなクラシック音楽の指導のあり方というのは、最もその精神から遠いと言わなければなりません。
数年前地元で行われた子どものためのあるピアノコンクールで、モーツァルトのソナチネが課題曲として出されました。2楽章からなるソナチネの最初の楽章は「アダージョ(大変に遅く)」と指定されていました。ところが、参加したほとんどの子ども達は、この曲をかなり早めのテンポでひいたのです。実はその楽譜には、編集者のハンス・カン氏が書き込んだと思われるメトロノームの指示が書かれていました。それに従うと、とてもアダージョとは思えないほど速いテンポになるのです。こここでも多くの先生方は、自分の感性に問いかけることなく、このメトロノームの早さに従ったようです。
しかし、私はその速さでは、とてもその曲の持っている息づかいや美しさを、表現することができないと感じました。そこで、素直に自分の感じ方にしたがって、そのメトロノームの指示より遅い速さで私の生徒を教えました。悲しいことに、その生徒がいただいた講評には、案の定このテンポのことが書かれていて、「もう少し早めにひくように」と注意されていました。
実は、当時クヴァンツという高名な音楽家が、音楽の拍子と早さの関係を詳しく論じた本を表していますが、これに従えばこの曲のように2分の2拍子で書かれたアダージョの曲は、カン氏のメトロノームの指示よりかなりゆっくりしたものになります。後日ジュリアード音楽院のステッセン教授にお会いする折りがあったので、このことをお話したら、カン氏のテンポを評して「リディキュラス(馬鹿げている)」と言っていました。
もしかしたら、井口版の正当性を主張して、私に反論を試みる人があるかも知れません。あるいはハンス・カン氏のテンポの正当性を主張する人もいるかも知れません。しかし、それにしてもどうしてみんながみんな、それだけに従ってしまうのかということです。これは、西洋音楽の拠って立つ理念からすれば、異常としかいうことができないでしょう。西洋音楽が日本に入ってきて百年を過ぎた今、技術としてだけマスターする時代はもう終わりにしなければならないと思います。たとえ地方の町の一介の教師であっても、自分の感性や自分の判断を足場にして、音楽に立ち向かう姿勢が何より求められるのではないかと考えます。
[ホームページ][コース案内][音階の曲集]」[夏目先生のエッセイ][テキスト研究]
Copyright(c) 1997 Yoshinori Natsume, All rights reserved.