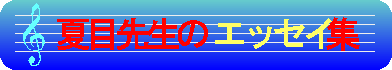
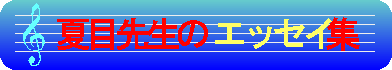
【第3回】
今回は、教室の新聞「おたまじゃくし第86号」(平成3年3月)に掲載したエッセイを載せることにしました。ここで取り上げた問題の多くは、この記事が書かれた時から何年もたった現在でも、相変わらず私たちの問題として残っているのではないでしょうか。もちろん、時がたって改めて読み直してみますと、現在ではやや違った視点を持っているものもあります。それだけに、古いエッセイも再度取り上げることで、自分の生き方の軌跡を見る思いがします。
自分の足で立てるように
先日ある民間放送のモーニングショーで「アメリカ人が嫌がる日本人の言動。日本人の言葉、しぐさ。ここがイヤ!」というタイトルの番組を放送していました。みなさんはこのタイトルを見て、どんな感じをお持ちになりますか。日本人はまだまだ沢山のことで、アメリカ人に嫌に思われているのかと、恥ずかしさや劣等感を覚えた方もあろうかと思います。放送界という、国際化の認識についてはもっとも進んでいると思われる人たちまでが、このような視点から番組を作るくらいですから、それも無理ないことかも知れません。
私はといいますと、私はこの番組を見て、たいへん腹立たしくなりました。アメリカで日本人の動作が、時に奇妙に見えることがあるというのなら、分らないでもありません。しかし、この番組は日本での出来事を問題にしているのです。「郷に入っては郷に従え」ということわざがありますが、アメリカ人には、自分達は日本にいるんだということを、まず心に止めておいてもらいたいものです。本当の国際理解は、相手の文化を理解し尊重するところから始まるのだという極めて基本的なことを、改めて彼らに気が付いて欲しいと思いました。
とはいっても、そんな彼らの批判をそのまま受け入れたような番組を作ってしまう日本人にも、大いに問題があるといえるでしょう。司会者が、出席している数人のアメリカ人に「日本人の言葉やしぐさを変に思ったことあるか。」と聞いていましたが、「ここは日本だ。私たちがどんな風しようと、いい気なお世話だ。」と突き返せない日本人は、それが日本人の性格だといってしまえばそれまでですが、とてもさみしいと思いました。
残念なことですが、日本はここまで経済発展してきても、心の底では未だに劣等意識を、抜けきれないでいるのだと思います。あるカナダの青年からこんな話を聞きました。ある時、通りをこれ見よがしに歩いていたパンクルック(ロック歌手の真似をして派手な色に髪を染めた)のお兄さんに「Hello! Do you have a light?(タバコの火を貸して下さい)」と尋ねたそうです。こんな時カナダを始め西洋諸国の若者なら「バッカヤロー。うせろ。」ぐらいのことを言って威圧するところだそうですが、こそこそとその場を逃げ出してしまったそうです。威勢のいい彼らですら、このちょっとしたハプニングに動揺してしまったようです。
こんな話もしていました。ある民間放送局で、英語で書かれた木島平(大きなスキー場のあるところ)の宣伝文を読む仕事をしたそうです。木島平に行く人は日本人だけなのに、何で英語でやらなければいけないのか、英語で喋った本人が随分不思議がっていました。
カナダの青年四人とスキーに行ったときのことです。四人が四人とも日本の若い女性を見て、「日本の女の子はみんなきれいだ。」と感嘆の声を上げるのです。まるで自分の国の女性はブスばかりだといわんばかりです。それなのに日本のファッション雑誌の表紙の多くは、今でも外国の女性を使っています。そのファッション誌を読んで洋服を購入する読者は皆日本人なのだから、外国の女性が着た洋服を見ても、体型や肌の色の違いを考えると、それほど参考にはならないと思うのですが。これなどもまだまだ自分達の真価に自信が持てないでいる、日本人の一面を見る思いがします。
私はこれまで西洋音楽を教える仕事をして来ました。その意味では、西洋の文化を高く評価してきたということができます。しかし、その事を通して私が学んだ一番大きなことは、自分自身の価値観や判断を大事にするということでした。これは決して西洋のものにこそ価値がある、といったことではありません。何故なら、私自身が日本人であるということ抜きにしては、何事も始まらないのですから。
例えば、私は一流の演奏家のレコードやCDを参考に聞くことがあります。しかし、自分がその演奏を気に入らなければ(結構そのような場合が多いのですが)、いくらその演奏家が西洋の大家であっても、私にとっては価値のないものです。そして自分の信じるところを、自信を持って出すことにしています。そのような私の考え方や指導を通して、生徒の皆さんも自分の手で自分の価値を作り上げていくことの大切さを、学び取ってくれることを、いつも願っています。
[ホームページ][コース案内][音階の曲集]」[夏目先生のエッセイ][テキスト研究]
Copyright(c) 1997 Yoshinori Natsume, All rights reserved.