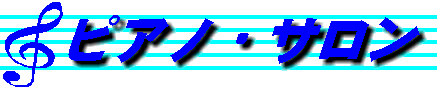
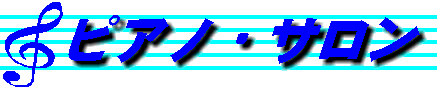
| と き | : | 平成11年4月11日(日)2:00p.m. |
| ところ | : | 長野県民文化会館小ホール |
| 出 演 | : | 夏目芳徳生徒20名(小1〜高3) |
| 入場料 | : | 無料 |
| 《 プ ロ グ ラ ム 》 | |
| ◆ピアノソロ◆ | |
| バッハ | パルティータ第1番 変ロ長調より |
| リスト | 演奏会用練習曲第1番〈森のささやき〉 |
| フォーレ | バルカローレ イ短調 作品26の1 |
| メンデルスゾーン | 練習曲 ヘ長調 作品104の2 |
| ブラームス | ラプソディ 作品79の1、2 |
| ラヴェル | ピアノのためのソナチネ 第3楽章 |
| 湯山 昭 | 風変わりなマズルカ、エコセーズ |
| その他 | |
| ◆バイオリンとピアノのアンサンブル◆ | |
| モーツァルト | バイオリンソナタ 変ロ長調 K378 |
| ベートーヴェン | バイオリンソナタ ニ長調 作品12の1 |
| その他 | |
- ◆賛助出演:加藤 晃(バイオリン)
- 愛知県立芸術大学音楽学部卒業後、1991年ドイツ国立アーヘン音楽大学に留学。1996年バイオリンとビオラでDIPLOM(国家演奏家資格)を取得し、同大学を卒業、帰国する。バイオリンを中澤きみ子、新藤義武、綿谷恵子の各氏に、バイオリン・ビオラ・室内楽をシャルル・アンドレ・リナーレ氏(オルフェウス弦楽四重奏団)、ビオラをマッシモ・パリス(イ・ムジチ合奏団)に師事。現在、名古屋弦楽ゾリステンの音楽監督等を努める傍ら、長野ではSBCアンサンブルのトレーナー、小諸高校音楽科の講師、また長野のプロフェッショナルな演奏団体、アンサンブル・ノーヴァの代表として多方面に活躍している。
| 当日に向けて練習中のみさきちゃん(小4)の演奏をお楽しみください | ||
| バッハ : パルティータ第1番 変ロ長調 | アルマンド | |
| コレンテ | ||
| ジーグ | ||
| 慣れないクラビノーバを使っての演奏で、ふだん通りの演奏でないのがちょっと残念。でも、残された1ヶ月あまりの練習で、当日は素晴らしい演奏をしてくれるものと期待しています。 | 上のボタンを操作し てお聞きください |
|
今回も新しいプログラムでお楽しみ下さい
ピアノ・サロンは、私、夏目芳徳の指導を受けている生徒たちが演奏するコンサートです。このコンサートにはいくつかの特徴がありますが、その一つは、毎回たくさんの新しい曲目を取り上げていることです。それにより指導者も生徒も、またコンサートにお出でになったお客様も、そのたびに新しい創造に立ち向かい、新鮮な発見と感動に出会うことができる、と考えています。
また、出演生徒の多くは、「ピティナ・ピアノコンペティション」で優秀な成績を修めた生徒たちです。しかし、彼らはコンクールの虫のようなタイプでは、決してありません。彼らの多くはピアノ以外の学校生活や部活動にも興味を持って、一生懸命活躍している子どもたちです。
ある小学生の子どもはドッチボールに夢中だったり、別の中学生は剣道の部活に忙しい中で、ピアノの練習を続けています。高校では陸上の長距離の選手で、毎日練習を終えて家に帰ると夜の8時頃。それでも、こつこつとピアノを続けた生徒もいました。でも、そんな事情がとても信じられないくらい、子どもたちは皆ステキなピアノを演奏します。今回も、そんな子どもたちの素晴らしい演奏を、どうぞお楽しみ下さい。
バイオリンとピアノのアンサンブル
これまでの「ピアノ・サロン」では、ピアノのソロの間に連弾を入れて、プログラムに変化を持たせてきました。子どもたちはこの連弾の勉強を通して、アンサンブルの楽しさを知り、また合わせる技術も身につけることができた思います。そこで、そろそろ他の楽器とのアンサンブルを経験してもいい頃かな、と考えていました。
ところで、アンサンブルといえば、最近では子どもたちのコンクールを初めとして、小さな子どもにオーケストラとの競演をさせることが、一部には流行っているようです。しかし、費用的にも大きな負担のかかるこのような催し物は、ちょっとバブル経済時の影を見るような感じがしないでもありません。私は、子どもたちのアンサンブルは、むしろ少人数の室内楽から始める方が、より親密性があって緻密で内容の濃いアンサンブルを体験できるのではないかと思います。
このような考えを前回のピアノサロンの時に、地元のバイオリニスト・加藤晃さんにお話ししたところ、大いに賛成していただき、快く子どもたちとの共演を引き受けて下さいました。お陰様で、昨年のバイオリンとのアンサンブルは大成功でした。今年もアンサンブルについては、昨年の経験をより深めるという考えから、再度加藤さんにお願いして、バイオリンアンサンブルを演奏することになりました。最近行った第1回の練習の時から、加藤さんには「昨年の経験が生きていて、1回目からずいぶん楽に合わせることができた。」とのコメントをいただきました。今から当日が楽しみです。
演奏する生徒たちには、緊張することなく、いつものリラックスした演奏を聴かせてほしいものと願っています。また、お聴きになる皆様には、そんな生徒たちの努力を、大きな拍手で迎えて上げていただければ、たいへんありがたく思います。