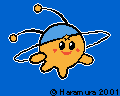 |
スライディングルーフの観測室を作るぞ! 2001年7月1日〜8月2日 |
| 最終更新日:2001年8月2日 |
2001年7月1日
ゴールデンウィーク、中学生さんの修学旅行や自然教室と本業が忙しく、6月初旬まで殆ど手付かずだったのですが、気合いを入れ直して観測室の製作を開始。
天体観測というとドームを連想するが、皆で天を眺めるには不便だし、作るのも大変そう、という事でスライディングルーフを作ることにする。雑誌の広告を眺めて大体の構造は決定、いつも大工仕事をお願いしている棟梁に依頼しようとしたが、忙しいらしく一向に連絡がとれない。え〜い、望遠鏡も自作しているのだから、この際、観測室も自分で作ってしまえ!となりました。
6月中旬から設計しながら作業開始。7月1日には、やっと木組みがほぼ終了。

 主に2×4材で組んでいます。
主に2×4材で組んでいます。
2×4材は柔らかく、強度の面では不満がありますが、なんと言っても安い!
部分的にコンパネを張り付けてセミモノコック(?)的な構造になる予定。
 裏側から見るとこんな感じ。
裏側から見るとこんな感じ。
食堂の増築部分の上に乗っています。写真で見えている屋根の下に、もうひとつ古い屋根があり、柱は上の屋根を貫通して古い屋根の上に取り付けています。
材木やルーフに使うカーポート等買って、これまでの出費:334、410円也
(望遠鏡:228、001円、観測室:106、409円)
2001年7月12日
スライディングルーフで一番問題になると思われるレールとルーフの製作を開始。
ルーフは市販品には2分割の物が多いが、作るのが大変そうだし、中央部の雨漏りの心配もあるので、カーポートを改造して一枚物のルーフとする。望遠鏡の死角を少なくするのにはルーフを棟方向にスライドさせたい所だが(望遠鏡を高い位置に設置出来るので。)、積雪の関係でそうもいかない。
レールをへの字形にして望遠鏡の位置を少しでも高くする事にした。
 レールは75mm×45mmの鉄のCチャン。
レールは75mm×45mmの鉄のCチャン。
上部に荷重を支えるタイヤ(キャスター)、レールの中にガイド用のタイヤを入れてあります。
ルーフは写真右方向にスライドします。
材木やレールに使う鋼材等買って、これまでの出費:397、128円也
(望遠鏡:228、001円、観測室:169、127円)
2001年8月2日
小中学校はもう夏休みに入っているというのに、観測室は木組みがむき出しのまま。
お客様を迎えつつ、少々焦り出していたが、7月25、26、29〜31日を休業にしてトップシーズン前のラストスパートをかける事にしました。
スライディングルーフの屋根はポリカーボネイトの波板、側面はカラートタンの平板、後面はカラートタンの角波板を張り付ける。
屋根はさほど問題なく張れたものの、側面のカラートタンは構造がやや複雑だったせいもあって、かなりデコボコになってしまった。この辺は素人の悲しい所だが、近くで見る人もいないので、と割り切ってしまった。
作業の都合で、ルーフ後面を張る前にレールを取り付ける。
3メートル近いCチャンを3本仮組みして屋根の上で一人で立ち上げるのは、かなり緊張したが思いのほかスムーズに作業は進行、どぉって事ないじゃん、と思ったのも束の間、どう見てもレールが水平になっていない!どうやら柱の寸法を間違えたようだが、他のステーも組み付けてしまったので、後戻り出来ない。やむなく空中でレールの取付け穴を開け直すハメとなってしまった。(斜めの屋根の上に立てた脚立の上で、12mmの穴を鉄のCチャンに開ける、と言ったら結構恐い作業です、本当に)
 なんとかレールを付け直して、いよいよスライドテスト!
なんとかレールを付け直して、いよいよスライドテスト!
さすがにレールをへの字形にしてあるので、上る時にはかなり重いものの、レールの継ぎ目以外では抵抗感も殆ど無く、スムーズに動くではありませんか!嬉しくて何回も動かしてしまいました。
さて今度は床を張って、と作業を進めていたところに、持病の腰痛が!
その後の三日間は歩くのが、やっとの状態で、結局8月までの作業は木組みがむき出しのままで終了となってしまいました。続きは9月まで、おあずけです。