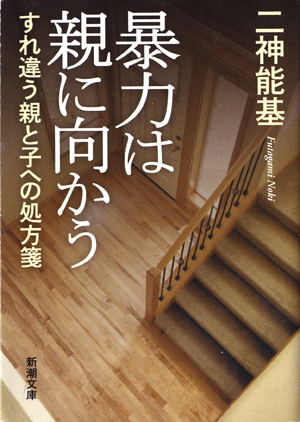
毎月1日発行[発行責任者:守 一雄]
(kaz-mori[at-mark]cc.tuat.ac.jp)
http://www.avis.ne.jp/~uriuri/kaz/dohc/dohchp-j.html
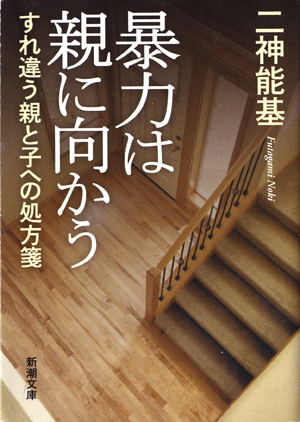
|
|
(c)新潮社 |
ところが、新たにいい本が見つかる一方で、定番を占めていた本が品切れになって使えなくなることも起こってきます。ディベートの本も、当初は岡本明人『授業ディベート入門』(教育新書)でしたが、品切れで手に入らなくなり、茂木さんの本になりました。一方、城山三郎『素直な戦士たち』(新潮文庫)・清水義範『虚構市立不条理中学校』(講談社文庫)も定番でしたが品切れになり、代わりが見つからないままきています。『虚構・・』の時は、アマゾンのマーケットプレイスに出品されていたものを買い占めて学生に転売するという荒技を使ったこともありました。(そのため、この本の古書価格相場が一時急激に上昇しました。)別の年には、山岸俊男『社会的ジレンマ』(PHP新書)が「品切れ」ということがわかり、これは授業の中核となる本で代わりが見つからないものだったので、著者の山岸先生に連絡して、重版されることを確認し、お手元にあったものを譲りうけて急場をしのいだこともありました。
東京農工大学に移ってからも、教職課程でこうしたスタイルの授業を5種類担当してきているので、30冊分のリストの管理をしなければなりません。30冊分もあると、品切れ以外にも、内容的に古くなったものの更新も必要で、普段からの目配りが結構大変です。今回紹介する本は、10年以上課題図書のレギュラーを張ってきた斎藤環『社会的ひきこもり』(PHP新書)の後継候補となる絶対おススメの本です。 (守 一雄)
「事務局」のユニークな取り組みの一つが、「レンタルお姉さん」というひきこもり支援の方法だ。ひきこもりの親の依頼を受けて「お姉さん」がひきこもりの若者を訪問し、外に引き出す働きかけをする。ひきこもりの解決にはこうした外からの「お節介」が必要なのである。NPO法人ではあるが、もちろん有料のサービスである。長い間ひきこもっていると、本人が外に出る気になっても、すぐに外で何かができるわけではない。そこで「事務局」では、次のステップとして、そうした若者が共同生活をするための寮を用意している。この寮で、社会的技能を学び、職場体験や学校に入り直すための準備をするのである。
そんな活動を通して、二神氏が見いだしたひきこもり問題の根本要因は「教育熱心な親」だ。良い学校に行って、人生の「勝ち組」になる。そんな目標を親子で共有していた、小さい頃は「素直ないい子」だった子どもが、ある日突然ひきこもりになる。親はなんとかして子どもをもう一度「目標へのレール」に乗せようとするが、その目標を捨てて、「勝ち組」にこだわる考えを変えないかぎり、ひきこもり問題は解決しない。だから、ひきこもりの子どもの「暴力は親に向かう」というのである。(守 一雄)