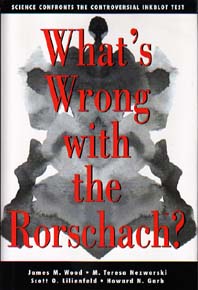
毎月1日発行[発行責任者:守 一雄]
(kazmori@gipnc.shinshu-u.ac.jp)
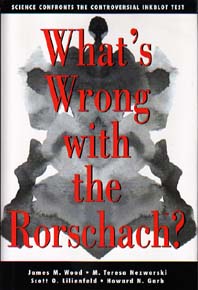
|
|---|
|
表紙にあるインクのシミは実際のテスト図版ではない。 |
今月はあえて英語の本を紹介することにした。洋書なのに和書並みの値段だし、夏休みにちょっと張り切っていつもは読めないような本に挑戦するというのもいいかな、と思ったからである。それになにより、「絶対面白い」本なのである。私も英語の本をこれほど一気に読んだのは久しぶりである。それほど面白い。
実は、この本は今年の4月号で紹介した『「心理テスト」はウソでした。』の中で紹介されていたものである。そこでは「ロールシャッハ・テストを容赦なく批判した書物が大量に売れている。それなのに、日本の臨床心理学の専門家は知らぬ振りである。都合が悪すぎるということだ。」とあったが、確かにハードカバーのこれだけ立派な装丁の本をこの値段で売ることができるということは、「数万部は売れる」という「読み」があったからだろう。そして、臨床心理学者ではない私でさえ手にして読んだくらいだから、実際にも多くの人が読んだと思う。臨床心理学者はこの本を読まないとホントに大変だよ。
内容を章を追って紹介しよう。全部で12章からなる。第1章は全体の概観であり、ロールシャッハ・テストが信頼性も妥当性もないテストであるにもかかわらず、なぜ広く使われているのかの謎解きの始まりである。第2章ではスイスの精神科医ロールシャッハがインクのシミによるテストを考案した経緯が紹介され、第3章ではそれがどうアメリカに渡ってきたのか、そして、第4章第5章では、1940年代にはアメリカ心理学界をロールシャッハ・テストが制覇する様子が描かれる。ここまでが第1幕である。
第2幕は、科学的心理学者たちの批判で始まる。1950年代にはいろいろな科学的心理学者がロールシャッハ・テストの問題点を指摘し始め(第6章)、ついには当初は擁護派であった心理測定分野の第1人者クロンバックに徹底的に批判され、ロールシャッハ・テストは1960年代にはほとんど絶滅寸前に追い込まれてしまう(第7章)。
青息吐息のロールシャッハ・テストを1970年代に見事によみがえらせたのがエクスナーである(第8章)。エクスナーの包括的システム(the Comprehensive System)は、科学的なデータ収集によってロールシャッハ・テストを標準化することで、問題点を解決し、ベック法やクロッパー法などアメリカへの紹介者ごとに違っていた得点化手続きの統一にも成功した。1980年代から90年代までには、エクスナー法はアメリカ心理学会(American Psychological Association)から「学会としてのお墨付き」まで得てしまうのである。
ここで終わればハッピーエンドなのだが、そうはいかない。第9章では、エクスナー法の内実が暴かれる。エクスナーの「科学的データ」というのは、粉飾されたものだったのだ。そんなものにお墨付きを与えてしまったアメリカ心理学会にも批判が起こる。1988年に科学的な心理学者たちが大挙してAPAを離れ、新たに別の「アメリカ心理学会(American Psychological Society: APS)」を作ったのも、これが原因だったのだ。APSがScience-Firstを標語にしているのもAPAへの「あてつけ」なのだろう。
第10章から12章の最後の3つの章は3通りのまとめである。第10章がふつうのまとめ。第11章はそれでもロールシャッハを信じたい人のための、なぜ人は信じたことを止められないのかについての説明を中心としたまとめ。『人間この信じやすきもの』の要約版みたいだ。そして、第12章は裁判でのロールシャッハ・テストの取り扱いに向けて弁護士のための戦略が紹介されている。
2千円ちょいで買えて、本棚に飾っても見栄えが良く、もちろん読んでみれば面白く、勉強にもなる。夏休みに原書を一冊読み通すというのもいい経験になるぞ。
(守 一雄)