毎月1日発行[発行責任者:守 一雄]
(kazmori@gipnc.shinshu-u.ac.jp)
素人の日曜大工ではこんなことがあっても、プロの仕事にはこんなことはないと思いこんでいましたが、この本を読むとプロの仕事にも信頼がおけないことがわかって愕然とします。なによりも、最近頻発しているトンネル内でのコンクリート崩落事故が、この本の正しさを証明しているようで本当に不安になります。天下の岩波新書ですし、今年の春に発売以来、ベストセラーの上位に常に登場してきている本なので、あえてここで紹介するまでもないかなとも思ったのですが、1900年代最後のDOHCに「1900年代の負の遺産」について記しておきたいと考え取り上げることにしました。マジで恐い本です。(守 一雄)
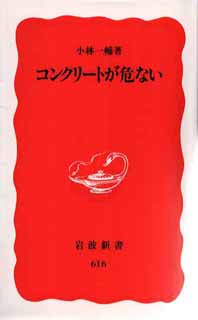
�
あちこちで報告されているコンクリート建造物の異変について紹介した次の章で、著者はいきなりこう「予言」する。建設省運輸技術研究所、東大生産技術研究所教授という経歴をもつ(現在は千葉工業大学教授)コンクリート工学の専門家である著者の予言はノストラダムスの予言よりもずっと恐ろしい。
引き続く章で、なぜ「コンクリートが危ない」のかが説明される。専門的で難しい部分もあるが、要点はよくわかる。原因は「塩分を含んだ海砂の使用」「アルカリ分の異常に多いセメントへの品質の変化」そして工事現場での「不法加水」である。
コンクリートの品質を悪化させるこうした3つの問題は、すべて1964年の東京オリンピック以降の高度成長期に起こってきた。莫大な量のコンクリート構造物が建設されるようになったために、塩分を含まない川砂が足りなくなった。高度成長期にはセメント需要も急激に増えたため、量産に適した製造工法が取られるようになった。そして、工事現場でも作業効率を高めるために生コンを規定以上に軟らかくする「不法加水」が日常化することになったのだという。
このようにして作られた欠陥コンクリートも、私のブロック塀修理の時と同様、工事直後には異常の検出が難しいという根本問題もある。コンクリートの欠陥は何年も経ってから現れてくるのだ。そして、そうなってからではもうどうしようもない。
著者の小林氏には、建設省やJRなど体制側を敵に回してでも真実を追求しようとする科学者・技術者の反骨精神が伝わってきて好感がもてる。しかし、そうした著者の真摯な人柄が伝わってくるだけに、内容の真実味が一層増してとても恐い。「山陽新幹線には乗れない。分譲マンションは買えない。」と本気で思った。 (守 一雄)