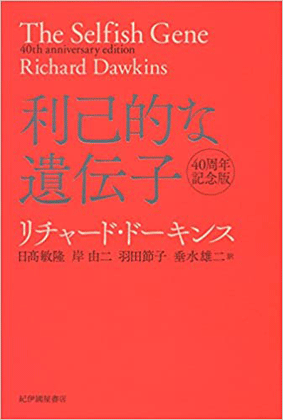
毎月1日発行 [発行責任者:守 一雄]
(kazuo.mori[at-sign]t.matsu.ac.jp)
http://www.avis.ne.jp/~uriuri/kaz/dohc/dohchp-j.html
さて、連休後半は天候にも恵まれて、ちょうど帰省してきていた孫たちと長野市内の恐竜公園やアスレチック広場で初夏のような日々を堪能しました。なんてことをツラツラと書いているのは、今月号で紹介する本がないからで、休号にしてしまおうかとも思ったのですが、「3年に一度は紹介する」としていたドーキンスの『利己的な遺伝子』をもう6年も紹介していなかったことに気づき、新しい視点から紹介してみることにしました。
ドーキンス先生は1941年生まれなので、私より10歳上で、今年82歳になりました。ありがたいことに、Twitterでツイートが読めるので、元気に世界各地で講演をしていることがわかります。残念ながら日本へ来る予定はしばらくなさそうです。
この本のペーパーバック版を1978年にトロント空港で夜明かししながら読んだ時の衝撃は、さすがにだいぶ薄れてきました。それでもその後しばらくは、いろいろなところでドーキンス教の布教に努め、当時は「いつかきっとノーベル賞を取るだろう」と考えていました。生物学賞はありませんが、ドーキンス先生の先生にあたるニコ・ティンバーゲンは、1973年にローレンツやフリッシュと一緒に医学生理学賞を受賞しているので、「いつかは医学生理学賞を」と考えていたわけです。
しかし、その後はむしろ「ノーベル文学賞こそが相応しいのではないか」と考えるようになりました。ドーキンス先生は出身のオクスフォード大学の教授を永年にわたって勤めてきましたが、大学での所属は生物学科ではなく、Charles Simonyi Professor of the Public Understanding of Science(科学啓蒙のためのチャールズ・シモニー教授)という寄付講座の教授職でした。科学啓蒙者としての活動こそがドーキンス先生の一番の貢献だと思います。Google Scholarで被引用業績を調べてみても、上位に並ぶのは著書ばかりで、中でもThe Selfish Geneは4万件近いもので、被引用総数も11万件を超えています。(守 一雄)
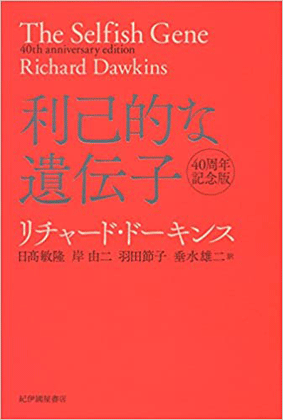
|
|
(c)紀伊国屋書店 |
「善とは遺伝子を存続させること」である。食用の牛を殺しても良いのは「遺伝子を殺している」わけではないからである。むしろ、人が牛肉をたくさん食べるほど、人気の品種の牛の遺伝子は増えていく。年寄りよりも子どもが大事なのは、子どもはこれから遺伝子を残すからである。小説の中で、二人の恋人のどちらを選ぶか迷う主人公は「どちらを選ぶ方が遺伝子の存続に有利か」の予測をしているのである。しかし、そうした予測を正しく行うために進化してきた私たちの脳は、何億年と生き続けてきた「利己的な遺伝子」に逆らうことはできない。だからこそ小説は面白いのである。(守 一雄)