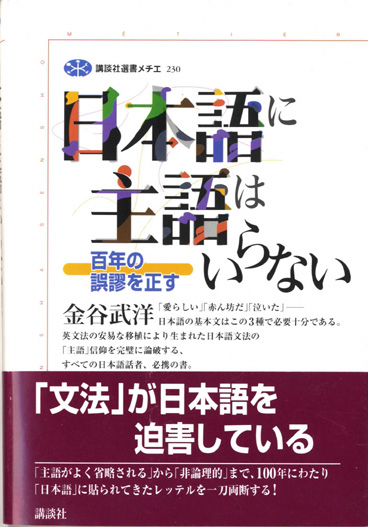
毎月1日発行[発行責任者:守 一雄]
(kazmori@shinshu-u.ac.jp)
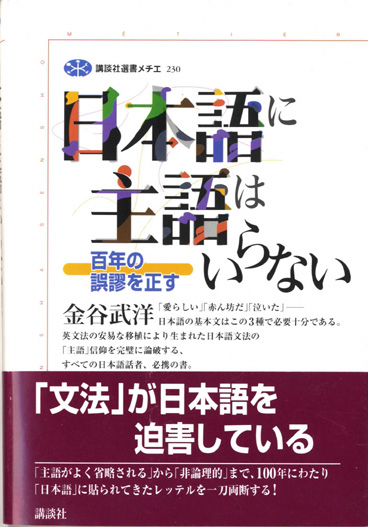
|
|
(c)講談社 |
「十二月も五日である。」「もういいかげんDOHC月報12月号を出さないといけない時期だ。」という文は日本語として普通に使われる文であるが、どちらも主語はない。しかし、学校で習った国語文法では日本語にも主語はあることになっている。主語がないように見える文は、「主語が省略されている」だけなのだ。それでは、上の文では何がその「省略された主語」なのか?文を作った本人にも何が主語なのかわからない。「今は」とか「今日は」とかのような気もするが、しかし、「今はもういいかげん12月号を出さないといけない時期だ」という文にすると、私が言いたかったこととは違う文になってしまう。むしろ、「もういいかげん12月号を出さないといけない時期」全体を主語にして、「そういう時期が来ている」とする方が意味的に近い。
そもそも無理に主語を探すよりも、「主語はないのだ」と考える方がすっきりする。そして「主語不要論」と言えば、学部4年生の頃に読んだ三上章の『象は鼻が長い』(くろしお出版)は衝撃的だった。三上文法の切れ味にハマり、当時手に入る三上の著作をすべて手に入れて読んだ。三上章の主張は明解であるだけでなく、ユーモアやウィットが感じられ、すっかりファンになってしまった。以来、日本語には主語はないという三上の主張の信奉者でありつづけている。
その後、生成文法に基づく日本語文法論などを読んだりもしたが、三上のこれらの著作を越えるものはなかった。今回のこの本も、「また三上章の焼き直しか、亜流かかな」と思って手にしたものだったが、これは三上章を越える面白さがあった。これは面白い本だ。
著者の金谷氏は年齢的には私と同じ。カナダのモントリオール大学で日本語を教えている日本語教育学者である。どこが三上章を越えているのかと言えば、フランス系カナダ人に実際に日本語を教えるという具体的な目標に基づく「実用性」だと思う。私たちが学校で習った学校文法はまったく実用的ではない。もうすでに何の不自由も感じることなく使っている日本語の文法を習うことに何の意味があったのだろう?しかも、文法を習っても、自分の作った文の「主語」を見つけることさえできない。これに対し、金谷氏の提案する日本語文法は役に立つ。なるほど、これならカナダ人に日本語が教えられるという納得がいくのである。
ユーモアのセンスも三上章に負けていない。英語やフランス語の文が「突出した主語を頂点に持つクリスマスツリー型」の構造であるのに対し、日本語の文は「背が低く、たくさんの枝を広げた盆栽型」だという比喩もウィットに富んでいる。実は、冒頭の主語のない文も見事に盆栽のように示せる。さらには、係助詞の「は」は、盆栽の横に掲揚された日の丸であるという比喩もわかりやすく面白い。「は」は一つの文だけで役割を終えないのだ。(ここでは図が示せないのが残念である。ぜひ本書を見ていただきたい。)
後半で展開される日本語の動詞の分類も目から鱗が落ちるものだった。日本語の動詞は自動詞他動詞の区別よりも先に、「自然の勢い」か「人為的意図的行為」かの大分類があるというのである。日本語の動詞は「ある」型(自然)と「する」型(人為)に分かれるというわけである。また日本語の動詞の基本形は五段活用(「立つ(自然)」「焼く(人為)」)であるが、派生形では下一段活用(「立てる(自然→人為)」「焼ける(人為→自然)」になる。さらに、自然をさらに強めた「ARE形(受け身/自発/可能/尊敬)」と人為をさらに強めた「ASE形(使役)」があることなど、思わぬ法則の存在に気づくのは本当に楽しい。この本の初めの方にある「日本語には人称代名詞という品詞がない」という指摘にも納得がいった。この本を読むと、外国人に日本語を教えたくなる。 (守 一雄)