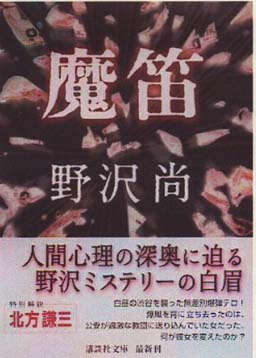
毎月1日発行[発行責任者:守 一雄]
(kaz-mori[at-mark]cc.tuat.ac.jp)
新任地での1ヶ月がすぎました。いろいろな事情から正式な研究室が用意されていなかったりしたため、机・椅子などの購入から始めねばならず、しばらくは仕事もできませんでしたが、なんとか落ち着いてきました。電車通勤は以前と同様で、自宅から駅までと駅から大学までの歩く距離もちょうど同じくらいです。もっとも、乗車時間だけは1時間近くとかなり長くなり、読書時間がぐっと増えました。授業はすべて夕方からなので、朝はゆっくりの「時差通勤」にしているのですが、それでも首都圏の電車はいつでも混雑していて、改めて首都圏の人の多さに驚く毎日です。そんなわけで、電車の中での読書はやはり文庫本になってしまいます。宮部みゆき・乃南アサの文庫もほぼ読み尽くし、他の作家の中から面白いものを探しているのですが、なかなかこの2人のレベルに達しているものが見つかりません。そうした中で、これはスゴいと思ったのが野沢尚でした。(守 一雄)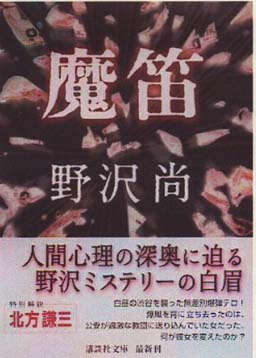 |
| (c)講談社 |
オウム真理教事件を題材にした長編小説である。犯人である照屋礼子の手記というスタイルで全編が描かれていて、推理小説における最後のタネ明かしの部分が拡大されて小説全体になったという感じである。「当事者」が自ら語るのであるから、本人にしか知り得ない詳細な情報の開示とその背景となる心理の説明がなされていく。もちろん、犯人以外の関係者もたくさん登場してくるわけで、視点がめまぐるしく転換するのだが、不思議に混乱することもなく、どんどんと読み進んで行けるのは作者の見事な文章表現技量のおかげである。
犯人の次に重要な位置づけを占めるのが刑事の鳴尾良輔である。犯人・照屋の手記でありながら、刑事・鳴尾の視点で書かれた部分がその大半を占めていて、これは「この数ヶ月、接見を繰り返し、彼がいかにして私という人間に辿り着いたか、その過程をつぶさに聞くことができた」からであるとされている。同じ内容を、鳴尾による「調書」という形式で描くこともできたはずであるが、こちらの形式を選んだことが作者・野沢のセンスなのだと思う。
話のスジは単純ではない。犯人・照屋の生い立ち、過去の経歴、なぜ犯行に至ったかの複雑な事情。それに合わせて登場してくる2人の重要人物、公安のエリート官僚・阿南威一郎とメシア神道の女教祖・坂上輪水。刑事・鳴尾を陰で支える妻の籐子。そして、もう一人のヒーロー爆発物特別処理隊SBSS隊員の真杉。こうした脇役たちにもそれぞれの人生のドラマが用意されていて、長編小説の深みを作り出している。
作者の野沢は映画やテレビドラマの脚本家としてデビューし、北野武監督主演『その男、凶暴につき』などの原作者である。この小説でも、映像がありありと目に浮かぶようなシーンが多いのはそのためなのだろうと思う。脚本から小説家へ転身した経緯は、『その男・・・』を小説化した『烈火の月』(これもむちゃくちゃ面白い)の「あとがき」に述べられている。細部にこだわりリアリティを描き尽くそうとする粘着質の性格がすべてを自分で決定できる小説を選んだのだ。小説になったことは、それを楽しむ側にもありがたいことであった。それぞれのシーンの詳細な描写はリアリティがありすぎて読んでいて苦しくなるほどで、途中でしばしば本を閉じた。思えば、こうして読者側が読むのをちょっと休むことができるのも、小説の利点である。映画やテレビでは一方的に見せられる側が逃げ出すこともできない。それはちょっと苦しすぎる。
犯人の手記という形式でこの小説が書かれていたことも、私のように刺激に弱い読者には救いだった。ハラハラどきどきの展開が続くのだが、「これは最終的に照屋が逮捕された後で書いているのだから、我らがヒーローたちは最後にはきっと成功するはずなのだ」と考えることでなんとか読み進むことができたからである。ものすごく怖いけれど、ホントに墜落しちゃう飛行機に乗っているのではないという、ジェットコースターに乗っているときに感じる安心感のようなものだろうか。
最後にどうしても触れざるをえないことは、これだけの才能を持つ野沢が自殺によって自らの命を絶ってしまっていることである。死と向かい合う場面の描写がここまでリアルにできたのも、野沢自身がこれに近い体験を何度もしていたからなのか。私は本を閉じて「野沢の作った現実から逃避」できたが、野沢本人にはそれができなかったのだろう。(守 一雄)