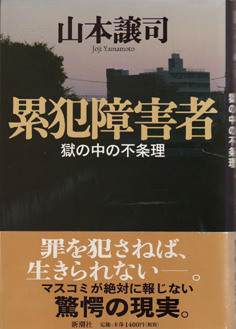
毎月1日発行[発行責任者:守 一雄]
(kazmori@shinshu-u.ac.jp)
新年あけましておめでとうございます。今年もDOHCをどうぞよろしくお願いします。
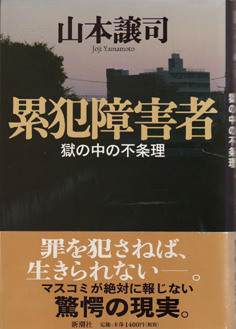
|
|
(c)新潮社 |
先月の読売新聞に元聾学校校長による「手話よりも『読唇』優先で」という論考が掲載された。手話は明確な文法体系がないため、聾児が手話を使って成長すると論理的な思考力がつかないというのである。それに対し、話し手の口の動きを読んで日本語そのものを理解させる「聴覚口話法(読唇)」は、聾児への指導は並大抵ではないが、その成功例の中には弁護士にまでなった人もいる。だから「手話よりも読唇を」というわけだ。
ところが、2週間後にその「成功例の弁護士」自身が同じ読売新聞に自分は「聴覚口話法の失敗例である」という反論を投稿してきた。手話も一つの言語体系であり、手話をしっかりと獲得することは母語を獲得することに相当し、日本語力の向上にも資するものであるというのである。手話を母語とする聾の人々の文化や世界観は通常の音声言語を母語とする私たちには理解ができないものなのかもしれない。にもかかわらず、私たちは元聾学校長のような「親心」から的はずれの教育をしてきたのである。その結果、手話を禁じてきた日本の聾教育は、読唇も手話も中途半端で使えない状態を作り出すことになってしまった。
外国人よりも異星人に近いかもしれない聾の人々が犯した罪でも、もちろん罪にはちがいない。しかし、警察や検察での取り調べにおいても、裁判の場においても、たとえ手話通訳がついたとしても、どれだけ正確にコミュニケーションがとれているかはきわめてアヤシイものなのだという。ましてや、上記のような聾教育の勘違いによって抽象的な思考能力の育成にも失敗してしまっている。そんな彼らに「黙秘権」の意味を伝えることができようはずがない。
「日本のマスコミは、努力する障害者については、美談として頻繁に取り上げる。」だが、健常者と同様に、問題行動を起こす障害者もいるのである。そして、ひとたび、問題行動を起こしてしまうと、警察でも裁判所でも正当な扱いをされず不当に重い刑が科せられがちだ。さらには、刑期を終えてからも福祉的支援も受けられない。聾唖者だったり、知的障害者だったり、あるいはその両方を併せ持つ者だったりする受刑者は、刑務所以外にその生活を保障してくれるところがないのである。こうした人々は軽微な犯罪を繰り返し、一生の大半を刑務所で過ごすことにならざるをえない。
刑務所に戻りたいがために犯した他愛もないことが、結果的に大火災を引き起こしたり、殺人につながったりすることさえある。刑務所を福祉施設代わりに使うような現状を改めて、ちゃんとした福祉施設を作っていれば、そんなことにもならずに済んだのである。この本でルポルタージュされているのもそうした犯罪である。序章を含めた6つの章で取り上げられている事例はどれも衝撃的であり、読むのを止めてしばらく呆然としてしまう。
悪いことをする政治家は後を絶たない。刑務所に入れられた者も数少なくないはずである。にもかかわらず、どうして今までこうしたことが見過ごされてきたのだろうか。彼らは皆、服役中もいかにして復権するかだけしか考えなかったのだろう。そうした中で、唯一の例外がこの本の著者、山本譲司氏である。氏は2000年の9月に政策秘書給与不正受給によって衆議院議員を辞め、実刑判決を受けて1年2ヶ月の服役を体験した。山本氏は、議員であった頃には「福祉の問題に関しては自分なりに一生懸命に取り組んでいた」つもりだったが、服役中に多くの累犯障害者たちと出会ったことで、この問題を真剣に直視する日本で最初の(元)政治家となった。知的障害者による刑事事件の弁護を専門的に行っている副島洋明弁護士からは「よくぞ服役してくれました。心から感謝します。」とまで言われたそうだ。私もこの本を読んで、著者が服役してくれたことに感謝したいと思った。 (守 一雄)