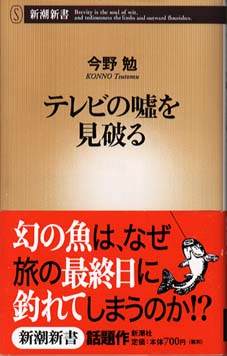
毎月1日発行[発行責任者:守 一雄]
(kazmori@gipnc.shinshu-u.ac.jp)
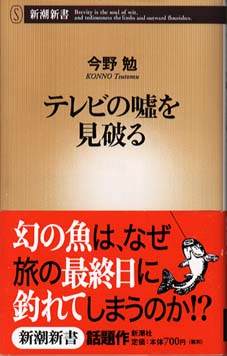
|
|---|
|
(c)新潮社 |
出だしに、いくつかの映像の嘘の種明かしが書いてある。全部それを書いてしまうと、これから読む楽しみがなくなるので、一つだけ紹介すると、ロシアのある強制収容所を訪ねるドキュメンタリーで、「ロシアの大地を収容所に向かって走るバスの映像は実は帰りに撮影したもの」だという。行きの段階では、どの辺が撮影に適しているかはわからない。そこで、行きは下見だけをしておいて、帰りに「バスをUターンさせて」撮影したのだそうだ。行きにやみくもに撮影したり、あらかじめ下見をしてから必要な場所だけ撮影したりするよりもこの方がずっと効率的・経済的だからである。
この本の面白いところは、こうした種明かしをしながら、その理由を示し、「はたしてこの『嘘』は許されるか、そもそも「嘘」と言えるか」を読者に問いかけていることである。たとえば、このバスの撮影の場合はどうだろう。収容所に向かうバスだと思って見た視聴者は騙されたことになるが、それによって視聴者がどんな不利益を被っただろうか。こうした嘘を許さない「潔癖な」番組作りをすれば、費用は余分にかかり、その余分な費用は結局のところ視聴者の負担となるのである。
ところが「視聴者に不利益でなければよい」という単純な話では済まない。著者はいろいろな具体例を示しながら、「どこまでの演出や工夫が許されるのか」を問いかけてくる。演出なり工夫なりを視聴者に「正直に明かすべきかどうか」という問いかけもなされる。前述の例で言えば、「このバスの撮影は実際には帰路になされました。」とテロップを入れることも可能であった。だが、こうすることで制作者の正直さは示せるが、その反面、視聴者は一種の「臨場感」を失ってしまうかも知れない。簡単なことのように思えた「テレビの嘘」や「やらせ」についての問題が、実は「ドキュメンタリーとは何か」とか「そもそも事実と何か」とかにまで広がっていく。
考えてみると、映像や写真と言葉とには決定的な違いがある。言葉はどんなにがんばっても「今」を語ったりはできないが、テレビ映像は「今」を映し出せる。そして、後からその「今」を再現して見せることができるのだ。一方で、映像は「今」でないものまで「今であるかのように」見せることもできるために、「やらせ」が問題とされるのである。これに対し、言葉はもともと「今」を示しようがないので、「今であるかのように」示すことも不可能なのである。だから、新聞では「やらせ」問題が起こりようがない。
もっとも、よく考えてみると、言葉だって嘘はつけるのだから、「やらせ」もできるはずである。たとえば、あるスポーツ選手が本当は「緊張してました」と言ったのに、「全然余裕でしたよ」と言い直してもらうことはできるはずだ。そして、後のコメントを新聞記事にして「A選手は『全然余裕でしたよ』と試合後にコメントした」と書けば立派な「やらせ」になる。しかし、言葉の場合は、そんな面倒なことをしなくても、最初からそう書けば済むだけのことだ。ただ、普通それは「やらせ」とは言わない。言葉の方がずっと簡単に嘘がつけることを誰もが知っているので、誰もが嘘を見破るための知恵も持つようになっているのである。一方、映像の場合には簡単には嘘がつけないため、受け手側は言葉よりも信用してしまいがちなのだ。その信用への裏切りが「やらせ」である。
そこで、著者の今野氏が提案する「やらせ」への対応策は、メディア・リテラシー教育である。受け手の側が、映像に対しても言葉と同程度に嘘に敏感になればいいのである。この本では取り上げられなかったが、コンピュータグラフィックス技術の発展によって、映像で嘘をつくことはいっそう容易になった。もう既に証明写真も写「真」と言えなくなりつつある。(ちなみに、私のwebページにある学会発表の写真も「やらせ」である。当日は発表自体に頭が一杯でとても写真を撮っている余裕がなかった。そこで、翌日に同じ会場で写真だけ撮ったものである。さて、この「嘘」は許されるか?)
(守 一雄)