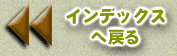
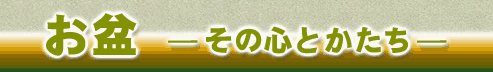
| お盆行事とはなんだろう |
| 私たちは、普段、正月休みや、お盆休みを年中の休息の日として自然に受け入れ、ふるさとを離れて働く人たちは、正月やお盆に帰郷することを楽しみにしています。 働き過ぎといわれる日本人も、お盆と正月だけは仕事から離れて、日頃、ごぶさたしている親族や親しい知人、世話になっている近隣の人たちに挨拶し、また、仏壇や、神棚を磨いて祈り、特にお盆には、なによりもお墓まいりをいたします。 これほど、なにげなく、習慣として受け入れている休みの日々には、どんな意味があるのでしょうか。 お盆の行事も、正月行事同様、地域ごとに違ってきますが、その意味においては、それほど違いがありません。 ふつう、お盆行事(まつり)は、祖霊がお盆の期間だけ家に帰って家族ともども過ごし、再びあの世に旅立つまでの間の行事(まつり)とされています。 お盆行事(まつり)には、三つの要素があります。 1 祖霊まつり (死者祭祀) 2 豊穣まつり (穀霊まつり) 3 魂まつり (生命の更新) この三つの要素がつながりあるものとして受け取られてきたのが、日本人の古くからお盆行事(まつり)に対する考え方だったのです。 |
| 盆と正月 |
|
かつて、年の始まりには、二つの考え方がありました。 |
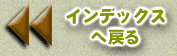
|