
●非木材紙って何?
製紙原料には、木材や古紙のほかに非木材繊維と呼ばれるものがあります(表1)。もともと、中国で紙が発明された頃の紙の原料は非木材繊維でした。ちなみに中国では現在でもワラやアシを主な原料として年間1,600万トン(1997年)の非木材パルプが生産されており、これは世界のパルプ生産総量の実に8.8%にのぼります。また、わが国ではコウゾ、ミツマタ、ガンピが、西洋では麻類、綿などがかつては製紙の主原料に使われ、現在も和紙、紙幣、たばこの巻き紙などの原料となっています。ほかにバガス(サトウキビの絞りかす)やトウモロコシといった食料作物の廃物も非木材繊維に数えられます。
わが国の製紙原料の構成比(表2)によれば、木材パルプ44.9%・古紙54.9%に対して非木材繊維は0.2%にとどまっており、この数字をみる限りでは、非木材繊維の普及がもっと進んでもよいのではという気がするのですが……?
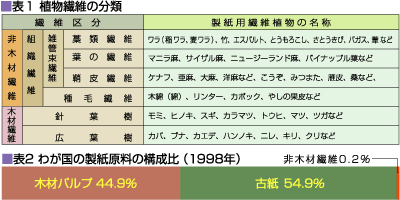
●ケナフの利点
さて、非木材繊維のなかでも何かと話題になっているのがケナフです。DENSAN MONTHLY Vol.1でもとりあげたように、このアオイ科の植物は、栽培範囲の広さと短期間で多くの収穫が可能な点、そして炭酸ガスを多量に吸収することなどから、新しい紙資源としての関心が高まってきているのは既報のとおりです。 非木材紙普及協会発行のパンフレットには、ケナフは成熟すると下部が直径3〜5cm、高さが3〜4mになる植物で、広く東南アジアや中国、アフリカ、カリブ海沿岸、米国南部で栽培されており、120日〜180日で7〜12トン/haの収穫が可能と説明されています。 次に、同協会発行の冊子『ケナフの話』から「ケナフの効果」を抜粋して引用しておきます。
- 1 炭酸ガス(二酸化炭素)を吸収する ◇赤松は伐採まで40年もかかるため、1年間に1エーカーあたりの収穫量は約1.1トン(1haあたり2.7トン) です。一方、ケナフの1エーカーあたりの収穫量は3〜10トン(1haあたり7.4〜24.7トン)で、比較するとケナフは赤松の約3〜10倍の炭酸ガスを吸収していることになります。 ◇さらに、ケナフは炭酸ガスをたくさん吸収して生長するという性質をもっています。たとえば、かりに5倍の炭酸ガスを発生させると、ケナフは5倍の大きさに生長するということがわかっていますので、大気中の温度が上昇するのを防ぐことができるようになります。また、それだけ多くの紙の原料を作ることができるのです。つまり、一石二鳥の効果をあげることができるわけです。
- 2 ケナフは水をきれいにします ◇実は、ケナフは葦よりもっとたくさんのチッ素やリンを水から吸収します。ケナフは葦に比べてリンを1.9倍、チッ素を1.25倍も多く取り除く力があります。ケナフは陸で育つ植物なので、そのまま水中で栽培することは不可能です。しかし、水路を作ってやれば、栽培が可能になります。 冊子では、このほか「ケナフの使いみち」として「いい紙ができます」「袋、紐、クロスもできます」「食べられます」「キノコを育てることができます」「織物の繊維としても使えます」「不織布の原料にもなります」「建材にもなります」と項目別にマンガ入りで分かりやすく説明しています。
いいことづくめのようなケナフですが、印刷・製紙業界では普及が遅々としているのが現実です。なぜでしょうか。最大の原因は価格です。ケナフ紙が高く、また安定かつ大量な供給が難しいのは次のような要因によるものです(日本製紙連合会『森林はパートナー』より)
◆ケナフは草本植物であるため、毎年、耕作・収穫等の栽培経費がかかる。
◆日本では、収穫は通常1年に1回に限られ、原料として使用するまでの保管場所が必要となる。
◆木材チップに比べ重量当たり容積が約3倍となるため、輸送や保管の効率が悪い。
◆パルプの収率(原料のうちパルプ抽出の割合)は約44%で木材の約50%より低い。
◆連作により土地が痩せることを考慮しながら、毎年一定のケナフの収穫量を保つには、広大な土地が必要となる。
◆日本の製紙工場でケナフパルプを製造するためのコストは、現状では、木材の場合に比べ5〜6倍かかる。
さらに「『ケナフが森を救う』とか、『木材紙以上に地球温暖化の防止に役立つ』というのは、真の姿を映しているとは言えません。」と述べ、その理由に、前号で述べたように現在の森林減少問題とわが国の製紙とは直接関係がないこと、ユーカリの年間成長量はケナフとほぼ同等で二酸化炭素の吸収量もほとんど差がないことなどを挙げながら「ケナフを木材の代替として大規模に利用するという考えは、現実的ではありません。」と主張し、「大切なことはケナフという素材の適性を正しく把握して活かすことにあると考えています。」と結んでいます。

では、製紙産業が積極的に進める「環境」への取り組みとは何か。それは植林です。もともと森林は再生可能な資源であり、収穫(伐採)〜更新(天然更新、人工植林)といったサイクルを適切に回転させることにより、持続可能な森林経営を行うことができます。この点にいち早く着目した製紙産業各社は、今のように地球環境問題への関心が高まる以前の1970年代に海外植林事業をスタートさせ、これまでに38万haを植林、今後はこれを2010年までに55万ha(東京都の面積の約2.5倍!)にまで広げていく考えのもとで、現在も24件の海外植林プロジェクトが進行中です。
1 なぜ海外なのか
製紙各社は現在国内に産業界でも有数の約30万haに及ぶ社有林などを持っていますが、国土本来の狭さと植林可能地が限定されること、林業労働力や植林コストの問題などがあり、今以上の植林は望めない現状にあります。一方、海外植林には、地域によって多少の差はあるもののおよそ次のようなメリットがあります。
しやすい。
b広大・平坦な土地が多く、伐出作業
等も機械化できる。
c成長の早い樹種が育つ。
d土地価格や人件費が安い。

2製紙産業以外の業界からの参加も
進行中の植林プロジェクトには、他産業各社からの共同出資も増えています。一例を挙げると、伊藤忠商事、日商岩井、講談社、小学館、千趣会、凸版印刷、大日本印刷、東北電力、富士ゼロックス、トヨタ自動車、東京海上などの社名が資料に見られます。植林は全産業界の問題なのですね。
3適切なサイクルで森を更新
植林開始にあたっては、成木になるまでの年月を踏まえて土地を区分(例:8年で成木になるユーカリなら8区域に分ける)。毎年違う場所に順々に植えていき、計画的に保育・管理と収穫(伐採)のサイクルを回すことにより、毎年一定の収穫量を得ることができます。
〔資料:平和紙業(株)『循環型社会とエコロジーペーパーの使命』、非木材紙普及協会『ケナフの話』、日本製紙連合会『森林はパートナー』、大王製紙(株)『再生紙動向について』、王子製紙(株)『森の響No.12』〕